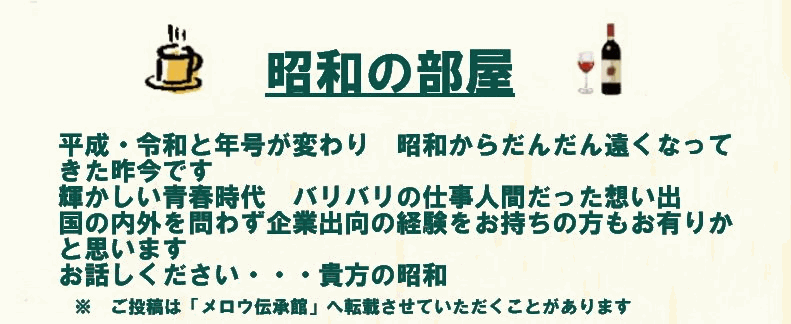
[トップに戻る] [スレッド表示] [トピック表示] [アルバム] [留意事項] [ワード検索] [過去ログ] [管理用]
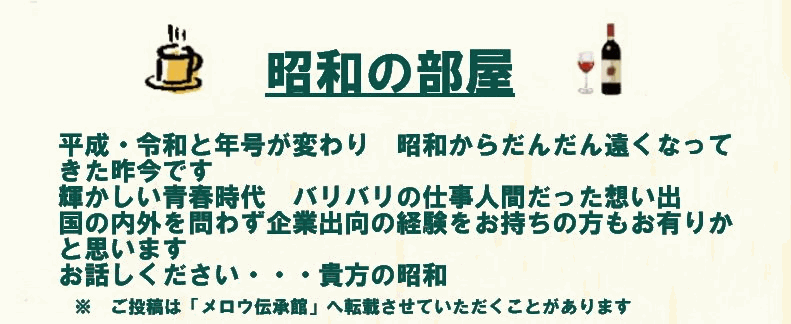
あす15日は「終戦の日」
この日毎年必ず流れるテレビの画面に、敗戦を告げる
「玉音放送」に皇居・二重橋前で泣き崩れる人たち。
ラジオを前に突っ伏して嘆き悲しむ人たち。
だが、5歳だった私の記憶に前後のいろんな事柄は
鮮明に残っているのに、この「玉音放送」にまつわる
記憶がポッカリと穴をあけている。
ゴーゴーガーガー雑音が入り、音が切れると叩いては
放送を聴いていたラジオは貧しくともわが家にはあった。
でも「その日」皆がラジオの前に集まっていたということも
放送のあと嘆き悲しんでいた・・・という記憶も何も無い。
長く続いた戦争にみんなが疲れ果て、「終わるこの日」を
待ちかねていた人たちがどれだけいたことか・・・
正しい発言をしていても、当時「非国民」と呼ばれののしられた
人たちがどれだけいたことか・・・
思うに、京・伏見のわが家をはじめ近所の大人たちはこの
「敗戦」であっても「戦争」に終止符がうたれる事にホッとして、
喜んでいたとしか思えない。
すでに物心両面のダメージは極限に達していただろうし、
今から待ち構えるそれ以上の「戦後の困窮」にも、「戦争」が
続くこと以上に「終わること」を皆が選んだのだと思う。
最近「きな臭い」発言をする人たちがあちこちにいるが、
人間として絶対に繰り返してはいけない事、それは「戦争」!!
祈ろう! 「恒久世界平和」!!
(2006.8.14 投稿の私のブログから)
私は 昭和の20年代の後半に生まれましたから 戦争のことはまるで分からないのですが 子供の頃は まだ戦後の名残が残っていました
小学校に上がる前あたりだったか 蚤・虱(のみ・しらみ)の駆除のためだったのか 近くの子供たちと一列に並び DDTなる白い粉を浴びた思い出も残っています
鹿児島市の城山の麓の町(山下町)に住んでいたのですが 近くに防空壕が有り そこに一人の男性が住んでいました
子供たちは何か怖い人のような近づけないイメージで彼(「防空壕のオジチャン」って呼んでいた)を見ていたと思いますが 或るときそのオジチャンが近くで遊んでいた子供たちに面子(メンコ)のような絵の付いた真新しい束をくださったのです
その時から あぁ、このオジチャンは怖くないんだって考え直したのでしたが 暫くしてオジチャンは防空壕の中で息を引き取られた(まだそんなに年を取っていたわけでは無かったと思っています)ということで 市の係の人たちがその防空壕に網をかけて入れなくなったことを覚えています 寂しくて悲しい思い出です
戦後、物のない時代の懐かしい写真を、インターネットで見つけた。
「コークス」というものをご存じだろうか?
燃料として「石炭」を使っていた時代の話。
その「石炭」の燃えかすを「コークス」と言って、この「コークス」も
燃料として使用した。
私の生家は京都・伏見の京町10丁目。
同じ町内に『津田電線(“津田はん”と呼んでいた)』の伏見工場があった。
(この伏見工場は1912(明治27)年開設とある)
今朝、テレビの「平和祈念式典」で黙とうを捧げながら、ふと、戦後の事を
考え出し、食料どころか薪や炭も手に入りにくい時代、近所にあった『津田
はん』の「コークス拾い」で、近隣の者はずい分助けてもらったな・・・と
思い返した。
今はその跡地は住宅が立ち並んでいて、昔の面影はないが、「津田はんは今も
あるのかな・・・?」と、インターネットで調べたら、京都・久御山町に今も健在!
嬉しくなってきた。
“伏見工場”は1967年に閉鎖されていたが、戦後の物のない時代、燃料と
して使われた石炭の燃えかすを、京町通りに面した工場の一角に山のように
放り出してくださる。 (今なら消防署からの禁止令が来るだろうな)
今思うと、何か合図を出して下さっていたのかもしれないが、私、当時6-7才前後
では何も覚えていない。
手に手にカネのバケツと小さい熊手やスコップを持ち、手には火傷防止の軍手を
はめて、少しでも多く集めたい家は小さい子まで動員して、その「コークス」の
山に取りついた。
冷めると白っぽくなって、これを「七輪(コンロ)」で燃やすと再び赤々と今の
木炭以上の火力になって、煮炊き物をするのに欠かせないものだった。
私も遊び半分で何度か手伝ったことがある。
何と言っても「レクリェーション」のない時代、これも子供たちにとっては、
コミュニケーションの場、楽しいレクリェーションになっていた気がする。
子供たちが“縦にも横にも繋がっていた時代”の切ないけれど、楽しい話。
そのまま横丁の広場や路地裏、伏見ダムの広場へ行ってはみんなで遊んだものだ。
『津田はん』の地元住民への優しさだったのだろう。
今となると何もかもが懐かしい・・・
(2011.8.6 の私のブログから)
子どもたちの幼少期、三重県鳥羽市在住時に在籍していた「鳥羽こども劇場」(今は無い)の1980.12.1に発行された文集 『はまなでしこ』 第2号に「お母さんから子供への手紙」と題して親たちが書き記したものの中、私が投稿していた“作文”を、世界のあちこちが何やらきな臭い今、ここにアップしておこうと思う。
「ある日の雑記帳から」
夕焼けの、オレンジ色の空を見ると、思い出すひとつの空があります。
それは、幼い心に焼きついた京・伏見区の生家の前から見える大阪の街をこがす戦火が染めぬいた、焼けただれた空の色。
あの空の下で、何人の人が殺されて行ったのでしょう。
今も、母の作ってくれた頭巾の色や柄を覚えています。あのような物を再び被りたくも、わが子にかぶせたくもありません。
師団街道を南から北へむかう国防色のトラックには、いつも髪は焼けちぢれ、顔が赤くずるむけたいやな言葉ですが、敵国の兵隊たちが棒立ちのまま、文字通り棒か杭のように満載されていました。
撃墜された戦闘機からひっぱり出された、わずかながらも命の残された人たちだったのでしょう。そのトラックを見て、我ら多くの者が拍手をしてはやしたてたものでした。
きっとその頃、アメリカやイギリスなどでは日本兵も同じ目にあっていたでしょうに。
「空襲警報」の声であかりを消した家の中。防空ごうの暗やみの色、そして、空を走るサーチライトの光の色、これもいまだに忘れることのないイヤな色です。
原爆投下の標的に京都も候補に上がっていたと知ったとき、三十四年前にすんでしまった戦争に、背筋を冷たいものが走りました。
今日も世界のあちこちで、おろかな行為がくり返されています。富めるとも、貧しくとも、今、平和に暮らしていることのありがたさ。その時、もし、自分がこの世から抹殺されていたとしたら、今袖にすがるいとしい二人の子供はこの世に『生』をうけていなかったのでしょうから・・・
- Joyful Note -