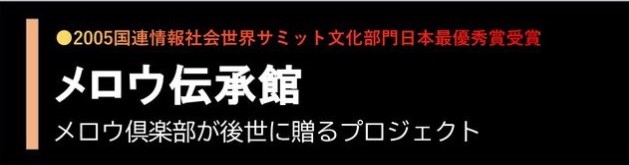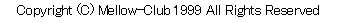紫竹のの8月15日(1)
投稿ツリー
-
 紫竹のの8月15日(1) (紫竹の, 2005/8/4 17:44)
紫竹のの8月15日(1) (紫竹の, 2005/8/4 17:44)
-
 紫竹のの8月15日(2) (紫竹の, 2005/8/5 8:21)
紫竹のの8月15日(2) (紫竹の, 2005/8/5 8:21)
-
 Re: 紫竹のの8月15日(2) (桂女, 2005/8/6 10:48)
Re: 紫竹のの8月15日(2) (桂女, 2005/8/6 10:48)
-
 Re: 紫竹のの8月15日(2) (紫竹の, 2005/8/7 16:18)
Re: 紫竹のの8月15日(2) (紫竹の, 2005/8/7 16:18)
-
-
-
- depth:
- 0
前の投稿
-
次の投稿
|
親投稿
-
|
投稿日時 2005/8/4 17:44
紫竹の
 居住地: 神戸
投稿数: 92
居住地: 神戸
投稿数: 92
 居住地: 神戸
投稿数: 92
居住地: 神戸
投稿数: 92
昭和20年《1945》 8月15日、終戦の日、敗戦の日、それは、勤労動員に行っていた工場が疎開することになり、初めて、疎開《そかい=空襲を避けて都会から田舎に住まいを移すこと》先の掘っ立て小屋《=基礎の無い粗末な家》に行った日だった。
旧制高等学校の二年生であった私たち(確か、理科8クラスのうち2クラス)は、1945年4月から、実家の遠近にかかわらず全員寮に入れられた。寮は、京都の中心部から東によったところにあったが、勤労動員《戦時中学生は強制的に工場などで働かされた》先の京都の西南にある軍用飛行機のエンジン工場に、2交替(そのうち3交替になった)で、電車を乗り継いで通うことになった。肝心の学校の勉強は二の次で、勤労動員の合間合間にしていただけのように思う。
東一条から市電に乗り、四条大宮で京阪電車(今の阪急)に乗り換えて桂まで。あとは隊列を組んで、少し南の、今は自衛隊桂駐屯地《ちゅうとんち》になっている中日本重工(今で言えば三菱重工)の工場に向かった。そこは、軍用飛行機のエンジンを一貫して作る工場だった。食事は寮ではとらず、三食とも工場でとることになった
私たちの担当は、そのエンジンのクランクシャフトを削ることだった。日本の飛行機のエンジンは、ほとんどが空冷式のエンジンで、星型といわれる形をしていた。軸の周り《まわり》に、奇数のシリンダーが放射状に並んでおり、一つおきに燃焼して2回転で一回りとなる。作っていたエンジンは、この星型が前後に2重になっていた。シリンダーが何個だったか覚えていないが、仮に9個だとすると、これが2重になると18個だ。一重が11だったかもしれない。参考 http://www.warbirds.jp/kakuki/sanko/hosigata1.htm
クランクシャフトも、一つの部品では出来るわけではないが、それより、2重のエンジンだから、ほとんど同じ形のもの、と言っても、一方の軸部分がもう一方の軸部分に作られた孔の中に入るような構造になっており、工程の途中でそれを結合させるようになっていた。その一方のものを鋳物《いもの=金属を溶解し型に流したもの》から削り出し、クランクシャフトの形にするまでが私たちの分担していた流れだった。
そういう細かい作業を伝えるのが、この文の目的ではないが、私たちが担当して短い作業の流れの中にいろんな工作機械が入っていることを知っていただけば十分。
まず、真っ黒い鋳物のかたまりが積んである。これを旋盤《せんばん=切削用工作機械》にかけて、大体の形にする。はじめは、剣先のような形をしたバイト(旋盤で使う刃のような物)で、ゴリゴリゴリとスゴイ音を立てて削るのだが、出て来る大きな削りかす(切り粉と言ったような気がするが、とても、粉と言うような小さなものではない)が、熱を持っていて、バーナーであぶったように熱くなっており、見る見るうちに青く、赤く色が変わっていった。
大体の形が出来たら、平らに削るフライス盤、孔をあけるボール盤、特殊な歯車を削る機械(名称不明)などなどを使っていくと、だんだんと形が出来ていく。最後に二つを噛《か》み合わせたものが次の工程に行く。この噛み合わせで誤差が出て大騒動になったことがある。つまり、そんなものは使い物にならないわけなのだ。そこの担当の生徒は、きちんと言われたとおり、やっていたのだが、どうしたことだったのだろう。
エンジンになるには、それはそれは沢山の部品がいるのだが、その部品を作ったり、組み立てたりしている広い、大きな工場の向こうの端では、出来たエンジンの試験設備があるらしく、毎日、凄《すご》い音を響かせていた。
(2)に続く


旧制高等学校の二年生であった私たち(確か、理科8クラスのうち2クラス)は、1945年4月から、実家の遠近にかかわらず全員寮に入れられた。寮は、京都の中心部から東によったところにあったが、勤労動員《戦時中学生は強制的に工場などで働かされた》先の京都の西南にある軍用飛行機のエンジン工場に、2交替(そのうち3交替になった)で、電車を乗り継いで通うことになった。肝心の学校の勉強は二の次で、勤労動員の合間合間にしていただけのように思う。
東一条から市電に乗り、四条大宮で京阪電車(今の阪急)に乗り換えて桂まで。あとは隊列を組んで、少し南の、今は自衛隊桂駐屯地《ちゅうとんち》になっている中日本重工(今で言えば三菱重工)の工場に向かった。そこは、軍用飛行機のエンジンを一貫して作る工場だった。食事は寮ではとらず、三食とも工場でとることになった
私たちの担当は、そのエンジンのクランクシャフトを削ることだった。日本の飛行機のエンジンは、ほとんどが空冷式のエンジンで、星型といわれる形をしていた。軸の周り《まわり》に、奇数のシリンダーが放射状に並んでおり、一つおきに燃焼して2回転で一回りとなる。作っていたエンジンは、この星型が前後に2重になっていた。シリンダーが何個だったか覚えていないが、仮に9個だとすると、これが2重になると18個だ。一重が11だったかもしれない。参考 http://www.warbirds.jp/kakuki/sanko/hosigata1.htm
クランクシャフトも、一つの部品では出来るわけではないが、それより、2重のエンジンだから、ほとんど同じ形のもの、と言っても、一方の軸部分がもう一方の軸部分に作られた孔の中に入るような構造になっており、工程の途中でそれを結合させるようになっていた。その一方のものを鋳物《いもの=金属を溶解し型に流したもの》から削り出し、クランクシャフトの形にするまでが私たちの分担していた流れだった。
そういう細かい作業を伝えるのが、この文の目的ではないが、私たちが担当して短い作業の流れの中にいろんな工作機械が入っていることを知っていただけば十分。
まず、真っ黒い鋳物のかたまりが積んである。これを旋盤《せんばん=切削用工作機械》にかけて、大体の形にする。はじめは、剣先のような形をしたバイト(旋盤で使う刃のような物)で、ゴリゴリゴリとスゴイ音を立てて削るのだが、出て来る大きな削りかす(切り粉と言ったような気がするが、とても、粉と言うような小さなものではない)が、熱を持っていて、バーナーであぶったように熱くなっており、見る見るうちに青く、赤く色が変わっていった。
大体の形が出来たら、平らに削るフライス盤、孔をあけるボール盤、特殊な歯車を削る機械(名称不明)などなどを使っていくと、だんだんと形が出来ていく。最後に二つを噛《か》み合わせたものが次の工程に行く。この噛み合わせで誤差が出て大騒動になったことがある。つまり、そんなものは使い物にならないわけなのだ。そこの担当の生徒は、きちんと言われたとおり、やっていたのだが、どうしたことだったのだろう。
エンジンになるには、それはそれは沢山の部品がいるのだが、その部品を作ったり、組み立てたりしている広い、大きな工場の向こうの端では、出来たエンジンの試験設備があるらしく、毎日、凄《すご》い音を響かせていた。
(2)に続く