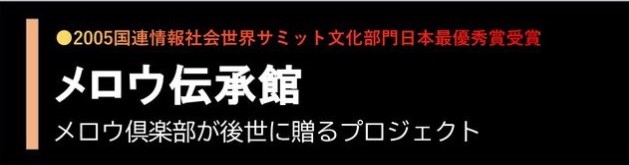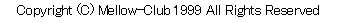Re: 夕陽残照ー渡満篇ー 澤田恵三氏の文章から
投稿ツリー
-
 夕陽残照ー渡満篇ー 澤田恵三氏の文章から (grue, 2005/8/25 16:10)
夕陽残照ー渡満篇ー 澤田恵三氏の文章から (grue, 2005/8/25 16:10)
-
 Re: 夕陽残照ー渡満篇ー 澤田恵三氏の文章から (grue, 2005/8/26 10:28)
Re: 夕陽残照ー渡満篇ー 澤田恵三氏の文章から (grue, 2005/8/26 10:28)
-
 Re: 夕陽残照ー渡満篇ー 澤田恵三氏の文章から (grue, 2005/8/27 11:33)
Re: 夕陽残照ー渡満篇ー 澤田恵三氏の文章から (grue, 2005/8/27 11:33)
-
 Re: 夕陽残照ー渡満篇ー 澤田恵三氏の文章から (grue, 2005/8/27 17:30)
Re: 夕陽残照ー渡満篇ー 澤田恵三氏の文章から (grue, 2005/8/27 17:30)
-
 Re: 夕陽残照ー渡満篇ー 澤田恵三氏の文章から (grue, 2005/8/27 18:12)
Re: 夕陽残照ー渡満篇ー 澤田恵三氏の文章から (grue, 2005/8/27 18:12)
-
-
-
-
grue
 投稿数: 8
投稿数: 8
 投稿数: 8
投稿数: 8
(その5) 満州へ ー満州鉄道・安奉線2ー
安奉線の敷設の歴史は日本軍の満州経営の歴史と一致している。日露戦争(1904-05)の最中に日本軍によって軽便鉄道《けいべんてつどう=簡単な規格で建設された鉄道》として建設された。開戦と同時に朝鮮から満州に越境攻撃を開始した軍(有名な黒木部隊)の兵站《へいたん=軍需品の補給、輸送など担当する機関》輸送路確保のためであった。1905年8月には、奉天までの全線が開通した。日本軍の艱難辛苦の結晶ではあるが、軌間《=レールの巾》はわずか762mmであり、不便で危険この上ない軽便鉄道・安奉線であった。
しかし、戦後になると新たに日本の満州経営の生命線ともいえる重要な路線として俄然《がぜん》脚光を浴びることになり、標準軌鉄道への改築と鉄道付属地権益の取得が日清間の最大課題となってきたのである。これは簡単には行かなかった。この経緯は別記(参考5)を見てもらう。
安奉線の標準軌道への改築の全面開通は、鴨緑江の大鉄橋の完成とあいまって、明治四四年(一九一一年)十一月のことである。この鉄路と橋の完成によって日本から中国東北への新しい交通路が開かれのである。
このような紆余曲折を経た、朝鮮鉄道、鴨緑江大鉄橋、安泰線を利用して、我々は、忘れることのできない「本渓湖」にたどりついた。かつて祖父のたどり着いた町(1913年)、そしてわたしたちの住んだ町「本渓湖市」は、この安奉線の途中駅であった。本渓湖は安東から約二百キロ、そして奉天へは八十キロ程の距離にある、この路線ではいちばん人ロの多い、急行の停車する町であった。九州大分を出発しておよそ2日半程の旅程であった。(参考6)
安泰線の完成二年後大正二年(1913)の厳寒二月、出来たばかりの、ピカピカの鴨緑江の橋と安奉線を旅して本渓湖駅に降り立った祖父のことを思い出さずにはいられない。霧の中の祖父に一歩近づけた気がした。
------------------------------------------------
(参考5) 標準軌巾「安奉線」建設を巡る経緯
日露戦争後大本営《だいほんえい=天皇に直属する最高の統率機関》幕僚《ばくりょう=直属の参謀や副官など》は内閣に示した意見書の中で、この安奉線について
『義州より鳳鳳城を経て奉天において東清鉄道に接続し、さらにこれを延長して新民屯(奉天の西、中国本土の北京につながる重要な路線駅)に至り、関外鉄道に連絡せしむるを軍事上有利とす』『この鉄道は満州における帝国の勢力範囲の骨格と見なすことを得ぺし』『韓国の鉄道と相まって清国に対する政略、露国に対する戦略上の枢要地《すうようち=かなめの土地》たる奉天をわが権力圏内に置くの利あり』
など、戦略、政略の両面からその重要性を強調している。
しかし、事はそうすんなりとは行かなかった、当然清国政府の強い抵抗に遭うことになった。日本がポーツマス条約でロシアから譲渡された『満州の権益』の最重点は、条文の第六条にある「長春以南の東清鉄道の本線・支線とその沿線付属地、それに付属する炭坑の経営権」であった。すなわちロシア政府が長年にわたって清国政府からかすめ取ってきた権益であり、これがロシアの既得権であったため、日本への譲渡に清国は異議申し立てはできなかった。
しかし、
『日本政府が火事泥棒式に戦争のドサクサにまぎれて建設した安東.奉天聞の軽便鉄道についても、歴史ある旧ロシア鉄道と同じ待遇を清国側に要求するに及んで、当然のことながら清国政府の抗議をまねいたのである。安奉線は、もともと安東と奉天の間を結ぶ野戦用の軽便鉄道であり、その土地は交戦中に軍が私人から買収したものであった。その間の土地売買の効力については中国側と争いがあり、解決をみない間に、居留民団《居留地に住む外国人の集り》が出来上がり、市街地を作りあげて来たものである』(「満鉄」-安藤彦大郎編・御茶の水書房・一九六五年)
という歴史経緯からして、清国がわの猛烈な抵抗にあうことになった。
これらの歴史はまさに、清国側にとっては、自国の領土と鉄道を日露両国の間で勝手に取引されていたわけである。つまり占領軍が入れ替わっただけである、
新しい占領軍はもっと欲が深い。その直後の明治三八年一二月、日本は大ロシア帝国に勝利した余勢を駆って、力の差によって清国をねじ伏せ、日本の要求を全面的に盛り込んだ「満州善後条約」と「付属協定」を清国に調印させた。そのなかに「安奉線の改築問題」をもりこみ、なおもぐずぐす引き伸ぱす清国に対し、一九〇九年明治四二年八月、武力を背景に最後通牒をつきつけ『安奉線改修二関スル覚書』が交換される。このような軋櫟《あつれき=人との和が不調になること》の中で「安奉線とその付属地・周辺の鉱山」が日本の手中に落ちた。これに対して、満州初の日貨排斥運動が起こったことも言っておかねばならない。満州ナショナリズムが既に台頭し始めていた。
------------------------------------
-----------------------------------
(参考6) 東京―奉天の旅程
明治四五年(1912)六月一五日に「東海道線一・二等特急列車の運転開始」とある。その日、日本内地-朝鮮-満州を通じて全面的な時刻改正がおこなわれた。そこで、その時刻表によって東京から奉天までどのくらいの時間でいけるか調べてみる。
東京を午前八時三〇分に特急で出発、下関到着は翌朝午前九時三八分。関釜連絡船で釜山に渡り、午後一一時二〇分発の急行に乗ると、新義州に翌日の午後三時四五分に着く。列車はそのまま鴨緑江の鉄橋を渡って、安東に到着するのは午後四時であった。安東で税関検査をうけて、安奉線をひた走り最終駅奉天到着は午後九時五五分である。この間じつに六〇時間半、東京から二日半で満州のど真ん中に到達できることになる。
-----------------------------------
渡満篇 完