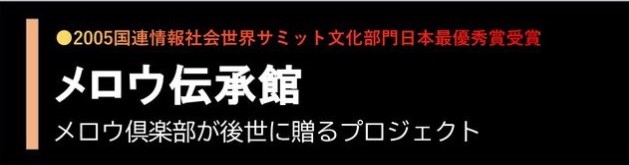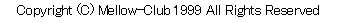私の生家「赤壁の家」その6
投稿ツリー
-
 私の生家「赤壁の家」その1 (編集者, 2007/1/9 9:33)
私の生家「赤壁の家」その1 (編集者, 2007/1/9 9:33)
-
 私の生家「赤壁の家」その2 (編集者, 2007/1/9 19:51)
私の生家「赤壁の家」その2 (編集者, 2007/1/9 19:51)
-
 私の生家「赤壁の家」その3 (編集者, 2007/1/10 19:42)
私の生家「赤壁の家」その3 (編集者, 2007/1/10 19:42)
-
 私の生家「赤壁の家」その4 (編集者, 2007/1/11 22:02)
私の生家「赤壁の家」その4 (編集者, 2007/1/11 22:02)
-
 私の生家「赤壁の家」その5 (編集者, 2007/1/13 21:04)
私の生家「赤壁の家」その5 (編集者, 2007/1/13 21:04)
-
 私の生家「赤壁の家」その6 (編集者, 2007/1/14 22:09)
私の生家「赤壁の家」その6 (編集者, 2007/1/14 22:09)
-
 私の生家「赤壁の家」その7 (編集者, 2007/1/16 20:22)
私の生家「赤壁の家」その7 (編集者, 2007/1/16 20:22)
-
 父と島崎藤村・その1 (編集者, 2007/1/17 19:07)
父と島崎藤村・その1 (編集者, 2007/1/17 19:07)
-
 父と島崎藤村・その2 (編集者, 2007/1/18 19:17)
父と島崎藤村・その2 (編集者, 2007/1/18 19:17)
-
 父と島崎藤村・その3 (編集者, 2007/1/19 17:18)
父と島崎藤村・その3 (編集者, 2007/1/19 17:18)
-
 父と島崎藤村・その4 (編集者, 2007/1/20 19:13)
父と島崎藤村・その4 (編集者, 2007/1/20 19:13)
-
 父と島崎藤村・その5 (編集者, 2007/1/21 20:05)
父と島崎藤村・その5 (編集者, 2007/1/21 20:05)
-
 父と島崎藤村・その6 (編集者, 2007/1/22 19:50)
父と島崎藤村・その6 (編集者, 2007/1/22 19:50)
-
編集者
 居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
 居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
神津家にはもう百年以上も前から毎年八月一日、親族一同が集まる「お墓参り」という年中行事が続いている。その模様は、父が明治初年には未だ珍しかった写真機をイギリスから購入して、恒例の集合写真を連綿と写してきたので、その時々の着衣や持ち物の様子が明治、大正、昭和、平成各年代の歴史的風俗を伝える貴重な記録写真となって残っている。
毎年、村を離れた遠い各地からも百人近い親類が集まるこの日は、本家の座敷を御殿まで開放してゆっくり一族の懇親を深めたあと、夫々のお墓にご焼香をして、菩提寺の法禅寺に集まり会食をするのであるが、この法禅寺はただお経を上げてもらうだけのお寺ではない。神津家とは一体となっている菩提寺である。
法禅寺は宗家が開基となったお寺なので、その住職の代が替わるときの晋山式《しんざんしき》は赤壁の家で営まれてきた。晋山式には私も参列したことがあるが、盛装した沢山の僧俗達が集まって荘厳な読経を捧げる盛大な勤行を行った後、長い行列が玄関から表門を出て法禅寺に繰り込んだ。神津家からの住職のお輿《こし》入れである。
だから、お墓とお寺は一体となって神津家の裏に位置するわけであるが、その墓地と法禅寺の間に一本の細い道がある。それを北側へ正住寺山の麓《ふもと》の方に少し登ると、権現様という祠《ほこら》がある。こじんまりした石垣櫓《やぐら》の上に組まれた社殿は古いものではなく、たぶん明治中期の神仏混交《しんぶつこんこう=神道と仏教が融合調和すること》、廃仏毀釈《はいぶつきしゃく=仏教排斥運動、仏像の破壊や僧侶への迫害など》の波に圧されて造られたものだと思うが、今も神津家の氏神様になっている。
毎年、村を離れた遠い各地からも百人近い親類が集まるこの日は、本家の座敷を御殿まで開放してゆっくり一族の懇親を深めたあと、夫々のお墓にご焼香をして、菩提寺の法禅寺に集まり会食をするのであるが、この法禅寺はただお経を上げてもらうだけのお寺ではない。神津家とは一体となっている菩提寺である。
法禅寺は宗家が開基となったお寺なので、その住職の代が替わるときの晋山式《しんざんしき》は赤壁の家で営まれてきた。晋山式には私も参列したことがあるが、盛装した沢山の僧俗達が集まって荘厳な読経を捧げる盛大な勤行を行った後、長い行列が玄関から表門を出て法禅寺に繰り込んだ。神津家からの住職のお輿《こし》入れである。
だから、お墓とお寺は一体となって神津家の裏に位置するわけであるが、その墓地と法禅寺の間に一本の細い道がある。それを北側へ正住寺山の麓《ふもと》の方に少し登ると、権現様という祠《ほこら》がある。こじんまりした石垣櫓《やぐら》の上に組まれた社殿は古いものではなく、たぶん明治中期の神仏混交《しんぶつこんこう=神道と仏教が融合調和すること》、廃仏毀釈《はいぶつきしゃく=仏教排斥運動、仏像の破壊や僧侶への迫害など》の波に圧されて造られたものだと思うが、今も神津家の氏神様になっている。