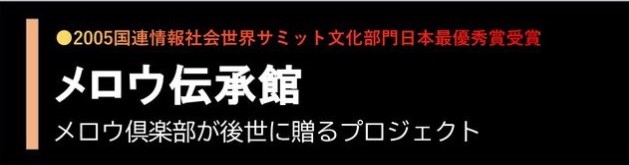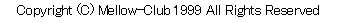жқұжқ‘еұұ гҒөгӮӢгҒ•гҒЁжҳ”иӘһгӮҠ гҒқгҒ®пј•
жҠ•зЁҝгғ„гғӘгғј
-
 жқұжқ‘еұұ гҒөгӮӢгҒ•гҒЁжҳ”иӘһгӮҠ гҒҜгҒҳгӮҒгҒ« (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/23 7:36)
жқұжқ‘еұұ гҒөгӮӢгҒ•гҒЁжҳ”иӘһгӮҠ гҒҜгҒҳгӮҒгҒ« (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/23 7:36)
-
 жқұжқ‘еұұ гҒөгӮӢгҒ•гҒЁжҳ”иӘһгӮҠ гҒқгҒ®пј‘ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/23 7:40)
жқұжқ‘еұұ гҒөгӮӢгҒ•гҒЁжҳ”иӘһгӮҠ гҒқгҒ®пј‘ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/23 7:40)
-
 жқұжқ‘еұұ гҒөгӮӢгҒ•гҒЁжҳ”иӘһгӮҠ гҒқгҒ®пј’ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/24 8:02)
жқұжқ‘еұұ гҒөгӮӢгҒ•гҒЁжҳ”иӘһгӮҠ гҒқгҒ®пј’ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/24 8:02)
-
 жқұжқ‘еұұ гҒөгӮӢгҒ•гҒЁжҳ”иӘһгӮҠ гҒқгҒ®пј“ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/25 7:28)
жқұжқ‘еұұ гҒөгӮӢгҒ•гҒЁжҳ”иӘһгӮҠ гҒқгҒ®пј“ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/25 7:28)
-
 жқұжқ‘еұұ гҒөгӮӢгҒ•гҒЁжҳ”иӘһгӮҠ гҒқгҒ®пј” (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/26 8:01)
жқұжқ‘еұұ гҒөгӮӢгҒ•гҒЁжҳ”иӘһгӮҠ гҒқгҒ®пј” (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/26 8:01)
-
 жқұжқ‘еұұ гҒөгӮӢгҒ•гҒЁжҳ”иӘһгӮҠ гҒқгҒ®пј• (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/27 6:52)
жқұжқ‘еұұ гҒөгӮӢгҒ•гҒЁжҳ”иӘһгӮҠ гҒқгҒ®пј• (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/27 6:52)
-
 жқұжқ‘еұұ гҒөгӮӢгҒ•гҒЁжҳ”иӘһгӮҠ гҒқгҒ®пј– (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/28 7:31)
жқұжқ‘еұұ гҒөгӮӢгҒ•гҒЁжҳ”иӘһгӮҠ гҒқгҒ®пј– (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/28 7:31)
-
 жқұжқ‘еұұ гҒөгӮӢгҒ•гҒЁжҳ”иӘһгӮҠ гҒқгҒ®пј— (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/29 7:45)
жқұжқ‘еұұ гҒөгӮӢгҒ•гҒЁжҳ”иӘһгӮҠ гҒқгҒ®пј— (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/29 7:45)
-
 жқұжқ‘еұұ гҒөгӮӢгҒ•гҒЁжҳ”иӘһгӮҠ гҒқгҒ®пј— (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/7/2 7:29)
жқұжқ‘еұұ гҒөгӮӢгҒ•гҒЁжҳ”иӘһгӮҠ гҒқгҒ®пј— (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/7/2 7:29)
-
 жқұжқ‘еұұ гҒөгӮӢгҒ•гҒЁжҳ”иӘһгӮҠ гҒқгҒ®пјҳ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/7/3 8:55)
жқұжқ‘еұұ гҒөгӮӢгҒ•гҒЁжҳ”иӘһгӮҠ гҒқгҒ®пјҳ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/7/3 8:55)
-
 жқұжқ‘еұұ гҒөгӮӢгҒ•гҒЁжҳ”иӘһгӮҠ гҒқгҒ®пјҷ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/7/4 7:42)
жқұжқ‘еұұ гҒөгӮӢгҒ•гҒЁжҳ”иӘһгӮҠ гҒқгҒ®пјҷ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/7/4 7:42)
-
гҒ“гҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜгҒ®жҠ•зЁҝдёҖиҰ§гҒё
- depth:
- 1
з·ЁйӣҶиҖ…
 еұ…дҪҸең°: гғЎгғӯгӮҰеҖ¶жҘҪйғЁ
жҠ•зЁҝж•°: 4298
еұ…дҪҸең°: гғЎгғӯгӮҰеҖ¶жҘҪйғЁ
жҠ•зЁҝж•°: 4298
 еұ…дҪҸең°: гғЎгғӯгӮҰеҖ¶жҘҪйғЁ
жҠ•зЁҝж•°: 4298
еұ…дҪҸең°: гғЎгғӯгӮҰеҖ¶жҘҪйғЁ
жҠ•зЁҝж•°: 4298
гҖҖеӨҡж‘©ж№–гҒ®еҸӨиҖҒгҒ«иҒһгҒҸ
гҖҖиІҜж°ҙжұ
в—ӢиІҜж°ҙжұ гҒҜгҖҒжқ‘еұұгҒЁеұұеҸЈгҒ®дёЎж–№гҒ§гҖҒжҳӯе’Ңд№қе№ҙгҒҫгҒ§гҒӢгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖдёҠеұұеҸЈгҒЁдёҠең°гҒЁдёӢең°гҒЁдёүгҒӨгҒ§гҖҒжқ‘еұұгҒ®дёҠе °е ӨгҖҠгҒҲгӮ“гҒҰгҒ„пјқе ӨйҳІгҖӢгҒЁдёӢе °е ӨгҒЁгҒҢгҖҒеӨ§жӯЈдёүе№ҙиө·е·ҘејҸгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒЁиЁҳжҶ¶гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮе®ҢжҲҗгҒҜгҖҒеӨ§жӯЈеҚҒеӣӣе№ҙгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮпјҲжіЁпјү
гҖҖгҖҢеҸӮиҖғгҖҚгҖҖ
гҖҖиІҜж°ҙжұ е·ҘдәӢвҖҰеӨ§жӯЈдә”е№ҙпјҲпј‘пјҷпј‘пј–пјүдә”жңҲдәҢеҚҒдёүж—ҘзқҖе·ҘгҖҒе…ӯжңҲеӣӣж—Ҙең°йҺ®зҘӯгҖҒеӨ§жӯЈеҚҒдәҢе№ҙдёғжңҲдёҠиІҜж°ҙжұ гҒҢе®ҢжҲҗгҖҒжҳӯе’ҢдәҢе№ҙпјҲдёҖд№қдәҢдёғпјүдёүжңҲдёӢиІҜж°ҙжұ е®ҢжҲҗпјҲгҖҺжқұжқ‘еұұеёӮеҸІгҖҸйҖҡеҸІдёӢпјүгҖӮ
в—Ӣз§ҒгҒҜгҖҒеӨ§жӯЈдёғе№ҙгҒ®е…«жңҲгҒӢгӮүе·ҘдәӢгҒ«еҫ“дәӢгҒ—гҒҹгҖӮиө·е·ҘејҸгҒҜгҖҒеӨ§жӯЈдә”е№ҙгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮеӨ§жӯЈдёғе№ҙе…«жңҲгҖҒгҒқгҒ®жҷӮгҒ®ж—ҘзөҰгҒҜгҖҒеӣӣеҚҒдә”йҠӯгҒ гҒЈгҒҹгҖӮ
пјҜиІҜж°ҙжұ гӮ’йҖ гӮӢгҒ®гҒ«гҖҒдёҖз•ӘжҖқгҒ„еҮәгҒҷгҒ®гҒҜиЈңеҠ©йҒ“дёғеҸ·з·ҡгҒ§гҖҒгҒ“гҒ“гҒҢз ӮеҲ©йҒ“гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹжҷӮгҖҒзІҳеңҹгӮ’д»ҠгҒ®з¬¬дёүдҝқиӮІең’пјҲеӨҡж‘©ж№–з”әпј‘пјҚпј’пј“пјүгҖҒйҮҺеҸЈз”әгҒ®гҒ“гҒЈгҒЎгҒ«зІҳеңҹгҒҢеҮәгҒҰгҖҒйҰ¬гҒ«гғҲгғӯгғғгӮігӮ’гҒӨгҒ‘гҒҹгҖҢйҰ¬гғҲгғӯгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгҖҒйҰ¬гҒҢдәҢеҸ°гҒҡгҒӨгғҲгғӯгғғгӮігӮ’йҖЈзөҗгҒ—гҒҰгҖҒгҒқгҒ®зІҳеңҹгӮ’з·ҡи·ҜйҒ“гӮ’жӯ©гҒ„гҒҰеј•гҒЈејөгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гҒ“гҒ®йҒ“гӮ’еәғгҒҸгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖв—ӢгҖҖе»»з”°еўғпјҲжіЁпјүгҒ®жүҖгҖҒеӯҰж ЎпјҲ第еӣӣдёӯеӯҰж ЎпјүгҒ®гҒӮгӮӢжүҖгҖҒз”°еҸЈе–ңеҚҒйғҺгҒ•гӮ“гҒ®гҒЁгҒ“гҒ®еҗ‘гҒ“гҒҶеҒҙпјҲеӨҡж‘©ж№–з”әпј‘пјҚпј’пј“гҒӮгҒҹгӮҠгҒӢгӮүжқұеҒҙпјүгҒҜгҖҒгҒҝгӮ“гҒӘжҺҳгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖвҖ»гҖҖе»»з”°еўғпҪҘпҪҘпҪҘйҮҺеҸЈз”әгҒЁеӨҡж‘©ж№–з”әгғ»е»»з”°з”әгҒ®еўғгҖӮ
в—ӢгғҹгӮӯгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгҖҒдёҖз•ӘеңҹгҒ®дёӢгҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҒ®зІҳеңҹгҒӨгҒЎгҒҜгҖҒйқһеёёгҒ«иүҜгҒ„гҖҒгҒқгҒ®зІҳеңҹгҒ«з ӮеҲ©гӮ’ж··гҒңгҒҰгҖҒгҒ“гӮҢгӮ’е·»гҒҚдёҠгҒ’гҒҰгҖҒд»ҠгҒ®е ӨйҳІгҒ®иҠҜгҒ«е…ҘгӮҢгҒҰгҖҒгҒ“гӮҢгӮ’гғӯгғјгғ©гғјгҒ§з©ҚгҒҝдёҠгҒ’гҒҰгҖҒдёҖе°әпјҲдёҖе°әгҒҜзҙ„дёүгҖҮгӮ»гғігғҒпјүеҺҡгӮҒгҒ«з©ҚгҒҝдёҠгҒ’гҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҖӮдҝ—гҒ«зІҳеңҹгӮігғігӮҜгғӘгғјеҚңгҒЁиЁҖгҒЈгҒҹгҖӮ
в—Ӣж—ҘеҪ“гҖҒеӣӣеҚҒдә”йҠӯгҒҢгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ§гҖҒдә”еҚҒйҠӯгҒҜгӮҲгҒҸеғҚгҒҸдәәгҖӮ
в—ӢеҪ“жҷӮгҖҒжҷҜж°—гҒҢжӮӘгҒҸгҒҰгҖҒиҫІе®¶гҒ®дәәгӮӮд»•дәӢгҒҢе°‘гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮд№…зұіе·қгҒ®дәәгҒ«гҒҚгҒҸгҒЁиІҜж°ҙжұ гҒ®д»•дәӢгҒҜиіғйҮ‘гҒҢгӮҲгҒ„гӮӮгҒ®гҒ гҒӢгӮүдәәгҒҢгҒӮгҒөгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ§гҖҒдә”жҷӮгҒ«гҒҜиө·гҒҚгҒҰеҮәгҒӢгҒ‘гҒҹгҒЁгҖӮ
в—ӢгҒқгҒ®гҒ“гӮҚгҖҒй…’гҒҜдёҖеҚҮгҖҒдәҢеҚҒйҠӯгҒҗгӮүгҒ„гҒ гҒЈгҒҹгҖӮ
в—Ӣз§ҒгҒҜгҖҒеӨ§жӯЈд№қе№ҙпјҲпј‘пјҷпј’пјҗпјүгҖҒж—ҘзөҰдёҖеҶҶе…ӯеҚҒйҠӯгҖҒеҚҒдёҖе№ҙгҒ«гҒҜдёҖеҶҶе…«еҚҒйҠӯгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹпјҲжіЁпјү
гҖҖвҖ»гҖҖи©ұгҒ—гҒҹдәәгҒҜзҸҫе ҙгҒ§иІ¬д»»гӮ’жҢҒгҒ гҒ•гӮҢгҒҰд»•дәӢгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
гҖҖ и»Ҫдҫҝйү„йҒ“гҒҜгҖҒжқұжқ‘еұұгҒ®й§…гҒӢгӮүгҒ©гҒ“гҒҫгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒӢгҖӮ
в—Ӣй§…гҒӢгӮүеҮәгҒҰгҖҒй·№гҒ®йҒ“гӮ’йҖҡгҒЈгҒҰгҖҒжё…ж°ҙгҒ®гғҲгғігғҚгғ«гӮ’йҖҡгҒЈгҒҰгҖҒе ӨйҳІгҒ®дёӢгҒ«еҸ–ж°ҙеЎ”гҒҢгҒӮгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҖҒгҒқгҒ“гӮ’еҮәгҒҰгҖҒдёҠе °е ӨгҒ®жүҖгҒҫгҒ§гҖӮ
гҖҖд»ҠгҒҜжё…ж°ҙпјҲжқұеӨ§е’ҢеёӮпјүгҒ«з§»и»ўгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒе®…йғЁпјҲгҒ“гҒ“гҒ§гҒҜдёӢе®…йғЁгҒ®гҒ“гҒЁпјүгҒЁеҗҢгҒҳзұіе·қзҘһзӨҫгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒи»Ҫдҫҝйү„йҒ“гҒҜгҒқгҒ®еүҚгӮ’йҖҡгҒЈгҒҰгҖҒгҒҡгҒҶгҒЈгҒЁз”°гӮ“гҒјгҒ®еҚ—еҒҙгӮ’йҖҡгӮҠгҖҒгӮ»гғЎгғігғҲеҖүеә«гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ“гҒ§гҖҒгҒқгҒ®е…ҲгҒ®дёҠе °е ӨгӮ’зҜүгҒҚгҒӮгҒ’гҒҹгҖӮж¬ЎгҒ«дёӢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ
в—ӢгҖҢгғҜгғғгӮ»гғігҖҚгҒ®жүҖгҒ§гҖҒд»ҠгҒ§гӮӮгҖҢгғҜгғғгӮ»гғігҖҚгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
пјҜе °е ӨгҒ®еңҹгӮ’йҒӢгҒ¶гҒ®гҒ«гҖҒдёӢгҒ®ж–№гҒ«гҒҜгҖҒеҢ—еҒҙгҒ®ж–№гҒ®еңҹгӮ’еҸ–гҒЈгҒҰйҒӢгҒігҖҒеҚ—еҒҙгҒӢгӮүеңҹгӮ’йҒӢгҒ¶гҒ®гҒ«гҒҜгҖҒе °е ӨгҒ®й«ҳгҒҝгҒ®ж–№гҒӢгӮүйҒӢгҒ¶з·ҡгҒҢй«ҳгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒгҖҢдёҠгҒЈз·ҡгҖҚгҒЁиЁҖгҒЈгҒҹгҒ®гҒҢгҖҒгҒ„гҒӨгҒӢгҖҢгӮҰгғҜгӮ»гғігҖҚгҖҢгғҜгғғгӮ»гғігҖҚгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ гҖӮ
в—Ӣж·Җж©ӢгҒ®пјҲжіЁпјүжө„ж°ҙе ҙгҒҜгҖҒжқұжқ‘еұұгҒ«з§»гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ
гҖҖвҖ»жө„ж°ҙе ҙи·Ўең°пҪҘпҪҘпҪҘж–°е®ҝиҘҝеҸЈгҒ®гғ“гғ«иЎ—гҒЁж–°е®ҝдёӯеӨ®е…¬ең’гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖжқ‘еұұиІҜж°ҙжұ е ӨйҳІе·ҘдәӢгҖҖеҲҮгӮҠеҙ©гҒ—гҒҹеңҹгӮ’гғҲгғӯгғғгӮігҒ«зӣӣгӮӢгҖӮ(зҙ°ж·өжәҗжІ»ж°ҸгҖҖжҸҗдҫӣ)

гҖҖиІҜж°ҙжұ
в—ӢиІҜж°ҙжұ гҒҜгҖҒжқ‘еұұгҒЁеұұеҸЈгҒ®дёЎж–№гҒ§гҖҒжҳӯе’Ңд№қе№ҙгҒҫгҒ§гҒӢгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖдёҠеұұеҸЈгҒЁдёҠең°гҒЁдёӢең°гҒЁдёүгҒӨгҒ§гҖҒжқ‘еұұгҒ®дёҠе °е ӨгҖҠгҒҲгӮ“гҒҰгҒ„пјқе ӨйҳІгҖӢгҒЁдёӢе °е ӨгҒЁгҒҢгҖҒеӨ§жӯЈдёүе№ҙиө·е·ҘејҸгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒЁиЁҳжҶ¶гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮе®ҢжҲҗгҒҜгҖҒеӨ§жӯЈеҚҒеӣӣе№ҙгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮпјҲжіЁпјү
гҖҖгҖҢеҸӮиҖғгҖҚгҖҖ
гҖҖиІҜж°ҙжұ е·ҘдәӢвҖҰеӨ§жӯЈдә”е№ҙпјҲпј‘пјҷпј‘пј–пјүдә”жңҲдәҢеҚҒдёүж—ҘзқҖе·ҘгҖҒе…ӯжңҲеӣӣж—Ҙең°йҺ®зҘӯгҖҒеӨ§жӯЈеҚҒдәҢе№ҙдёғжңҲдёҠиІҜж°ҙжұ гҒҢе®ҢжҲҗгҖҒжҳӯе’ҢдәҢе№ҙпјҲдёҖд№қдәҢдёғпјүдёүжңҲдёӢиІҜж°ҙжұ е®ҢжҲҗпјҲгҖҺжқұжқ‘еұұеёӮеҸІгҖҸйҖҡеҸІдёӢпјүгҖӮ
в—Ӣз§ҒгҒҜгҖҒеӨ§жӯЈдёғе№ҙгҒ®е…«жңҲгҒӢгӮүе·ҘдәӢгҒ«еҫ“дәӢгҒ—гҒҹгҖӮиө·е·ҘејҸгҒҜгҖҒеӨ§жӯЈдә”е№ҙгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮеӨ§жӯЈдёғе№ҙе…«жңҲгҖҒгҒқгҒ®жҷӮгҒ®ж—ҘзөҰгҒҜгҖҒеӣӣеҚҒдә”йҠӯгҒ гҒЈгҒҹгҖӮ
пјҜиІҜж°ҙжұ гӮ’йҖ гӮӢгҒ®гҒ«гҖҒдёҖз•ӘжҖқгҒ„еҮәгҒҷгҒ®гҒҜиЈңеҠ©йҒ“дёғеҸ·з·ҡгҒ§гҖҒгҒ“гҒ“гҒҢз ӮеҲ©йҒ“гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹжҷӮгҖҒзІҳеңҹгӮ’д»ҠгҒ®з¬¬дёүдҝқиӮІең’пјҲеӨҡж‘©ж№–з”әпј‘пјҚпј’пј“пјүгҖҒйҮҺеҸЈз”әгҒ®гҒ“гҒЈгҒЎгҒ«зІҳеңҹгҒҢеҮәгҒҰгҖҒйҰ¬гҒ«гғҲгғӯгғғгӮігӮ’гҒӨгҒ‘гҒҹгҖҢйҰ¬гғҲгғӯгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгҖҒйҰ¬гҒҢдәҢеҸ°гҒҡгҒӨгғҲгғӯгғғгӮігӮ’йҖЈзөҗгҒ—гҒҰгҖҒгҒқгҒ®зІҳеңҹгӮ’з·ҡи·ҜйҒ“гӮ’жӯ©гҒ„гҒҰеј•гҒЈејөгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гҒ“гҒ®йҒ“гӮ’еәғгҒҸгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖв—ӢгҖҖе»»з”°еўғпјҲжіЁпјүгҒ®жүҖгҖҒеӯҰж ЎпјҲ第еӣӣдёӯеӯҰж ЎпјүгҒ®гҒӮгӮӢжүҖгҖҒз”°еҸЈе–ңеҚҒйғҺгҒ•гӮ“гҒ®гҒЁгҒ“гҒ®еҗ‘гҒ“гҒҶеҒҙпјҲеӨҡж‘©ж№–з”әпј‘пјҚпј’пј“гҒӮгҒҹгӮҠгҒӢгӮүжқұеҒҙпјүгҒҜгҖҒгҒҝгӮ“гҒӘжҺҳгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖвҖ»гҖҖе»»з”°еўғпҪҘпҪҘпҪҘйҮҺеҸЈз”әгҒЁеӨҡж‘©ж№–з”әгғ»е»»з”°з”әгҒ®еўғгҖӮ
в—ӢгғҹгӮӯгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгҖҒдёҖз•ӘеңҹгҒ®дёӢгҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҒ®зІҳеңҹгҒӨгҒЎгҒҜгҖҒйқһеёёгҒ«иүҜгҒ„гҖҒгҒқгҒ®зІҳеңҹгҒ«з ӮеҲ©гӮ’ж··гҒңгҒҰгҖҒгҒ“гӮҢгӮ’е·»гҒҚдёҠгҒ’гҒҰгҖҒд»ҠгҒ®е ӨйҳІгҒ®иҠҜгҒ«е…ҘгӮҢгҒҰгҖҒгҒ“гӮҢгӮ’гғӯгғјгғ©гғјгҒ§з©ҚгҒҝдёҠгҒ’гҒҰгҖҒдёҖе°әпјҲдёҖе°әгҒҜзҙ„дёүгҖҮгӮ»гғігғҒпјүеҺҡгӮҒгҒ«з©ҚгҒҝдёҠгҒ’гҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҖӮдҝ—гҒ«зІҳеңҹгӮігғігӮҜгғӘгғјеҚңгҒЁиЁҖгҒЈгҒҹгҖӮ
в—Ӣж—ҘеҪ“гҖҒеӣӣеҚҒдә”йҠӯгҒҢгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ§гҖҒдә”еҚҒйҠӯгҒҜгӮҲгҒҸеғҚгҒҸдәәгҖӮ
в—ӢеҪ“жҷӮгҖҒжҷҜж°—гҒҢжӮӘгҒҸгҒҰгҖҒиҫІе®¶гҒ®дәәгӮӮд»•дәӢгҒҢе°‘гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮд№…зұіе·қгҒ®дәәгҒ«гҒҚгҒҸгҒЁиІҜж°ҙжұ гҒ®д»•дәӢгҒҜиіғйҮ‘гҒҢгӮҲгҒ„гӮӮгҒ®гҒ гҒӢгӮүдәәгҒҢгҒӮгҒөгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ§гҖҒдә”жҷӮгҒ«гҒҜиө·гҒҚгҒҰеҮәгҒӢгҒ‘гҒҹгҒЁгҖӮ
в—ӢгҒқгҒ®гҒ“гӮҚгҖҒй…’гҒҜдёҖеҚҮгҖҒдәҢеҚҒйҠӯгҒҗгӮүгҒ„гҒ гҒЈгҒҹгҖӮ
в—Ӣз§ҒгҒҜгҖҒеӨ§жӯЈд№қе№ҙпјҲпј‘пјҷпј’пјҗпјүгҖҒж—ҘзөҰдёҖеҶҶе…ӯеҚҒйҠӯгҖҒеҚҒдёҖе№ҙгҒ«гҒҜдёҖеҶҶе…«еҚҒйҠӯгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹпјҲжіЁпјү
гҖҖвҖ»гҖҖи©ұгҒ—гҒҹдәәгҒҜзҸҫе ҙгҒ§иІ¬д»»гӮ’жҢҒгҒ гҒ•гӮҢгҒҰд»•дәӢгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
гҖҖ и»Ҫдҫҝйү„йҒ“гҒҜгҖҒжқұжқ‘еұұгҒ®й§…гҒӢгӮүгҒ©гҒ“гҒҫгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒӢгҖӮ
в—Ӣй§…гҒӢгӮүеҮәгҒҰгҖҒй·№гҒ®йҒ“гӮ’йҖҡгҒЈгҒҰгҖҒжё…ж°ҙгҒ®гғҲгғігғҚгғ«гӮ’йҖҡгҒЈгҒҰгҖҒе ӨйҳІгҒ®дёӢгҒ«еҸ–ж°ҙеЎ”гҒҢгҒӮгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҖҒгҒқгҒ“гӮ’еҮәгҒҰгҖҒдёҠе °е ӨгҒ®жүҖгҒҫгҒ§гҖӮ
гҖҖд»ҠгҒҜжё…ж°ҙпјҲжқұеӨ§е’ҢеёӮпјүгҒ«з§»и»ўгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒе®…йғЁпјҲгҒ“гҒ“гҒ§гҒҜдёӢе®…йғЁгҒ®гҒ“гҒЁпјүгҒЁеҗҢгҒҳзұіе·қзҘһзӨҫгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒи»Ҫдҫҝйү„йҒ“гҒҜгҒқгҒ®еүҚгӮ’йҖҡгҒЈгҒҰгҖҒгҒҡгҒҶгҒЈгҒЁз”°гӮ“гҒјгҒ®еҚ—еҒҙгӮ’йҖҡгӮҠгҖҒгӮ»гғЎгғігғҲеҖүеә«гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ“гҒ§гҖҒгҒқгҒ®е…ҲгҒ®дёҠе °е ӨгӮ’зҜүгҒҚгҒӮгҒ’гҒҹгҖӮж¬ЎгҒ«дёӢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ
в—ӢгҖҢгғҜгғғгӮ»гғігҖҚгҒ®жүҖгҒ§гҖҒд»ҠгҒ§гӮӮгҖҢгғҜгғғгӮ»гғігҖҚгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
пјҜе °е ӨгҒ®еңҹгӮ’йҒӢгҒ¶гҒ®гҒ«гҖҒдёӢгҒ®ж–№гҒ«гҒҜгҖҒеҢ—еҒҙгҒ®ж–№гҒ®еңҹгӮ’еҸ–гҒЈгҒҰйҒӢгҒігҖҒеҚ—еҒҙгҒӢгӮүеңҹгӮ’йҒӢгҒ¶гҒ®гҒ«гҒҜгҖҒе °е ӨгҒ®й«ҳгҒҝгҒ®ж–№гҒӢгӮүйҒӢгҒ¶з·ҡгҒҢй«ҳгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒгҖҢдёҠгҒЈз·ҡгҖҚгҒЁиЁҖгҒЈгҒҹгҒ®гҒҢгҖҒгҒ„гҒӨгҒӢгҖҢгӮҰгғҜгӮ»гғігҖҚгҖҢгғҜгғғгӮ»гғігҖҚгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ гҖӮ
в—Ӣж·Җж©ӢгҒ®пјҲжіЁпјүжө„ж°ҙе ҙгҒҜгҖҒжқұжқ‘еұұгҒ«з§»гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ
гҖҖвҖ»жө„ж°ҙе ҙи·Ўең°пҪҘпҪҘпҪҘж–°е®ҝиҘҝеҸЈгҒ®гғ“гғ«иЎ—гҒЁж–°е®ҝдёӯеӨ®е…¬ең’гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖжқ‘еұұиІҜж°ҙжұ е ӨйҳІе·ҘдәӢгҖҖеҲҮгӮҠеҙ©гҒ—гҒҹеңҹгӮ’гғҲгғӯгғғгӮігҒ«зӣӣгӮӢгҖӮ(зҙ°ж·өжәҗжІ»ж°ҸгҖҖжҸҗдҫӣ)