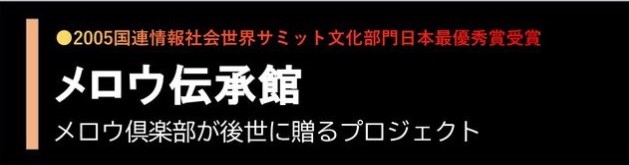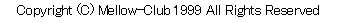南十字星の下で (1) ホベン
投稿ツリー
-
 南十字星の下で (1) ホベン (編集者, 2007/7/16 7:14)
南十字星の下で (1) ホベン (編集者, 2007/7/16 7:14)
-
 南十字星の下で (2) ホベン (編集者, 2007/7/17 7:47)
南十字星の下で (2) ホベン (編集者, 2007/7/17 7:47)
-
 南十字星の下で (3) ホベン (編集者, 2007/7/18 10:27)
南十字星の下で (3) ホベン (編集者, 2007/7/18 10:27)
-
 南十字星の下で (4) ホベン (編集者, 2007/7/19 7:44)
南十字星の下で (4) ホベン (編集者, 2007/7/19 7:44)
-
 南十字星の下で (5)ホベン (編集者, 2007/7/20 7:33)
南十字星の下で (5)ホベン (編集者, 2007/7/20 7:33)
-
 南十字星の下で (6) ホベン (編集者, 2007/7/24 7:44)
南十字星の下で (6) ホベン (編集者, 2007/7/24 7:44)
-
 南十字星の下で (7) ホベン (編集者, 2007/7/24 7:46)
南十字星の下で (7) ホベン (編集者, 2007/7/24 7:46)
-
 南十字星の下で (8) ホベン (編集者, 2007/7/24 7:48)
南十字星の下で (8) ホベン (編集者, 2007/7/24 7:48)
-
 南十字星の下で (9) ホベン (編集者, 2007/7/24 7:49)
南十字星の下で (9) ホベン (編集者, 2007/7/24 7:49)
-
 南十字星の下で (10) ホベン (編集者, 2007/7/25 7:54)
南十字星の下で (10) ホベン (編集者, 2007/7/25 7:54)
-
 南十字星の下で (11) 最終回 ホベン (編集者, 2007/7/26 7:13)
南十字星の下で (11) 最終回 ホベン (編集者, 2007/7/26 7:13)
-
-
 Re: 南十字星の下で (5)ホベン (岡田義明, 2008/4/16 13:05)
Re: 南十字星の下で (5)ホベン (岡田義明, 2008/4/16 13:05)
- depth:
- 0
前の投稿
-
次の投稿
|
親投稿
-
|
投稿日時 2007/7/16 7:14
編集者
 居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
 居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
(はじめに)
インターネットが一般家庭にまで普及したのは20世紀末で、それ以前は、パソコン通信による交流が行われており、このメロウ倶楽部の出身母体もニフティーサーブの運営していたパソコン通信の高齢者向けフォーラムの「メロウフォーラム」です。
この投稿は、その当時、パソコン通信上に掲載されたものをご本人のご了承を得た上転載するものです。
(メロウ伝承館スタッフ)
前書き 97/02/11 06:57
昨年三月勤めを辞めて、ずっと家にこもる様になってから、なんだかだんだんと太りはじめて、以前より五キロぐらいオーバーしてしまい、六十八キロにもなり,ズボンはチャックが出来なくなるわ、一日一時間と決めていた散歩も大儀になり、掛かりつけの医者に相談したところ、今更運動で減らすのも大変だから、食事を減らす以外に無い、とのことで、困っています、特に贅沢《ぜいたく》な食事をしているわけでもないのに、これも体質なのかと半ば諦《あきら》めてはいますが、勤務中は特に運動をしていたわけでもないのに、現在の生活がいかにカロリーがオーバーになっているかを痛切に感じています。
それにつけても思い出されるのは、大戦《=第2次世界大戦1939~1945》の末期に南海派遣軍《南方の海に送り出された部隊》で暁部隊の一兵卒として、パラオでの二年間の地獄のような飢餓との戦いが思い出されます。
玉砕《ぎょくさい=玉が砕けるように潔く死ぬこと》の島ペリリューは三十キロほど離れておりましたが、夜になると対岸の火事さながらあかあかと見え遠雷のような音が聞き取れ激戦の模様がうかがえました。
同島の玉砕後は敵が何時こちらに上陸してくるのか、分からない中で,兵站《へいたん=物資補給機関》を絶たれ自活を余儀なくされ、文字どうりに木の芽草の実、蛇トカゲとあらゆる物を食べて生き長らえてきました、その間半数の仲間は日本の土を踏む事も出来ずに散っていったのです。 終戦の知らせがあってから、張り詰めていた気持ちが一気に崩れ診療所に身を横たえることになり、帰還船に乗る時点での体重測定は日本人の生死の限界点の二十七キロになっていました、自らの血肉を糧にして生き長らえていたのです。
今は只《ただ》自分の強運を神に感謝するとともに、この繁栄した日本の姿を見ることも出来ずに、嫁も取れずに散っていった戦友たちのご冥福《めいふく》を祈るのみです。
塩と兵隊 10726/10757
戦争体験記のようなものをかいてみましたが、発表の場がなくて、自費出版をする余裕もないので、ボツボツとそのエピソードを取り上げてみたいと思いますが、興味の或る方は覗《のぞ》いてください。
南海のパラオでは戦争も末期に近く主食の米は言うにおよばず、味噌《みそ》、醤油《しょうゆ》、塩までも底をついたのである。ご存知のように空気、水に次いで塩は必要不可欠のものである、そこで上層部では製塩班なるものをつくり、海水からの製塩に踏み切ったのである、海水の取得は簡単であるが、問題はドラム缶にくみ込んだ海水をいかにして、蒸発させるかにあった、ペリリュウ島に米軍の飛行場が設営されてから、四六時中敵機の監視下にあったので、昼間は全く動けなかったのだ、農民や牛が畑で機銃掃射《きじゅうそうしゃ=飛行機が低空で機関銃で狙い撃つ》でやられた話はよく聞いた,製塩は恐らくは海岸に近いジャングルで煙が出ないように、炎をたてないようにで、大変の苦労があったものと思う。そして一昼夜も炊くとドラム缶の底に赤茶けた数センチのびしょびしょしたニガリのある塩が残るのである。
そのまた出来た塩の分配が大変で携帯燃料の空缶 4cX 4cぐらいのものに一杯が一人一ヶ月分で、配給された、つまり早くなめてしまえば、塩絶ちの日が何日か続くのだった。兵隊はそれを宝物のように大事に扱ったのである。
事件は帰還の船中で起こった、我々の船は第2回目の船だった、1回目は赤十字船で担架で運ぶ程の重病人を300人ほどが乗船していたのだが、空き腹に急に米の飯が出たため消化できずに、下痢患者が続出して、約半数が死んだとのことだった。そこで我々の時は乗船から下船までずっとお粥《かゆ》と梅干しだった、それすら泣くようにして食べたのを思いだす。船は海軍の元揚子江に配備されていたと言う底の浅い砲艦《河や沿岸を警備する小型の軍艦》だった、行くときの貨物船の2,500人乗った蚕だな《=蚕の棚のように幾つか重ねた寝台》とは違つて学校の教室のような平らのところに250名程が雑魚寝《ざこね》だった。水兵は痩《や》せさらばえた我々を異様なものでも見るような目で見ていた。途中グアムに寄港して、祖国に向かっていた、そしていよいよ明日は浦賀に入港するという前の晩に一人の兵隊が炊事場に入り飯盒《はんごう=炊飯も出来る弁当箱》に一掬《いっきく=一すくい》の塩を掠《かす》め取り、水兵に捕まり、班長を呼んでこいと責められて、思いあまって入水自殺したのである。班長に申し出ても、殴られるか説諭ぐらいで済んだと思うのだが祖国の土を踏める前の晩の出来事だった、今にして思えば真っ白い塩は彼には宝石程に見えたのかも....なんと哀れの話だろうか。