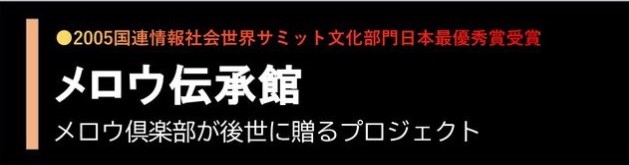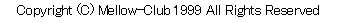南十字星の下で (6) ホベン
投稿ツリー
-
 南十字星の下で (1) ホベン (編集者, 2007/7/16 7:14)
南十字星の下で (1) ホベン (編集者, 2007/7/16 7:14)
-
 南十字星の下で (2) ホベン (編集者, 2007/7/17 7:47)
南十字星の下で (2) ホベン (編集者, 2007/7/17 7:47)
-
 南十字星の下で (3) ホベン (編集者, 2007/7/18 10:27)
南十字星の下で (3) ホベン (編集者, 2007/7/18 10:27)
-
 南十字星の下で (4) ホベン (編集者, 2007/7/19 7:44)
南十字星の下で (4) ホベン (編集者, 2007/7/19 7:44)
-
 南十字星の下で (5)ホベン (編集者, 2007/7/20 7:33)
南十字星の下で (5)ホベン (編集者, 2007/7/20 7:33)
-
 南十字星の下で (6) ホベン (編集者, 2007/7/24 7:44)
南十字星の下で (6) ホベン (編集者, 2007/7/24 7:44)
-
 南十字星の下で (7) ホベン (編集者, 2007/7/24 7:46)
南十字星の下で (7) ホベン (編集者, 2007/7/24 7:46)
-
 南十字星の下で (8) ホベン (編集者, 2007/7/24 7:48)
南十字星の下で (8) ホベン (編集者, 2007/7/24 7:48)
-
 南十字星の下で (9) ホベン (編集者, 2007/7/24 7:49)
南十字星の下で (9) ホベン (編集者, 2007/7/24 7:49)
-
 南十字星の下で (10) ホベン (編集者, 2007/7/25 7:54)
南十字星の下で (10) ホベン (編集者, 2007/7/25 7:54)
-
 南十字星の下で (11) 最終回 ホベン (編集者, 2007/7/26 7:13)
南十字星の下で (11) 最終回 ホベン (編集者, 2007/7/26 7:13)
-
-
 Re: 南十字星の下で (5)ホベン (岡田義明, 2008/4/16 13:05)
Re: 南十字星の下で (5)ホベン (岡田義明, 2008/4/16 13:05)
編集者
 居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
 居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
南十字星の下で その11 97/04/07 07:23
”ジャングル”へ
うっそうと言うほどではないが、木漏れ日がさす程度の、ジャングルの空からは見えない場所に我が分隊が宿泊できそうなバラックを建て、そしてそこに落ち付くことになった。
南方では冬の暖房のことを考えずに設営出来るから其《そ》の点は楽である、屋根は大きな天幕を掛けるだけである、外壁はビンロウ樹か椰子《やし》の葉で代用するが、蚊の出入りは自由である、蚊の媒介はデング熱だけでマラリヤが無くてよかった、デング熱は内地のはしかの様なもので皆一度は掛かった黄疸《おうだん》の様な症状になり発熱するが4,5日で治った。炊事班の小屋は後から建てた、トイレは海水の満ち退きするところに造った、自然の水洗便所だ,潮が満ちてくると魚が集まってきた、落下物をねらってくるのだ背中に斑点のある魚で兵隊は俗っぽく”クソックイ”と呼んでいた。
敵機に見付からないように、炊事班は朝早く煮炊きをするのだ、それも食料受領のたびにその配給量は減っていくのである。兵糧などもっと本島にも備蓄して置くべきだったろうに、全く残念だった、焼残りかまたは難を逃れた僅《わず》かな食料を遅蒔き《おそまき》ながら分散して保管するようにはなったのだが、ちょっと後手だった。 個人的の煮炊きは庭先の防空壕《ぼうくうごう》の奥に造ったかまどを使ってやった、煙を避けて腹ばいでの難行だった。補給が少なくなるに連れて、流通中に何か不正があったらしい、運搬途上に抜かれる、炊事班に着いてから将校用に抜かれる,炊事班の兵隊が当然の権利として頂く、古手の班長用に横流する、これでは末端の兵隊に届くのは定量の何分の1かになってしまうのだ。
半年もすると米は全く入らなくなった、補給路が断たれているのだから無理も無い、米が無くなってそれに替わってサツマイモか配給されるようになった、それも握りこぶし位のやつが1日に2個だった、子どもの頃祖母が胸が焼けると言っていた意味が体験を通じてやっと分かって来た。 このぐらいの量で大のおとながいきていけるとは思えない。
開墾
生きるための自活の闘いが始まるのである。島民の畑を取り上げるわけにもいかず、ジャングルを切り開いて開墾することになったのである、食べ物が無なり体力も衰えて来た兵隊が一抱えもある大木を切り倒して畑を作るのである、島民から借りて来たであろう鋸《のこぎり》や斧《おの》で伐採していくのである、敵機がくればジャングルに逃げ込み、出て来てはまた続ける能率は全く上がらない100坪の土地を切り開いても倒した木を適当に切ってあちこちに積んで置くので、それに場所を取られるそれに切り倒した木の抜根ができないので使える土地はせいぜい1/3位のものだ、斜面なので一坪《=約3,3平方メートル》ほどの土まんじゅうのような畑が10個所ほどできた、堆肥《たいひ=わらやごみなどの積み肥》の替わりに木の葉や草を埋めて、芋の苗を貰《もら》ってきてそれぞれ2,30本も植えたか、土地が痩《や》せており、たしか鼠《ねずみ》のシッポのような藷《いも》が取れただけだったと思う。帰還後知ったのだが生の堆肥はそれ自体が腐るのに窒素を取るから植物にはマイナスになってもプラスにはならないとかだった。
労多くして益の無い企画だった。
苗は植えてから収穫まで4ケ月もかかる、待っているわけにもいかない、今たべるものがほしいのだ、ジャングルの中を木の芽や、動き回るものを求めてさまよった、さつまいもの葉っぱ等はご馳走の部類だった、ジャングルの中は年中じめじめしているので、ビンロウ樹を80センチほどに切って各兵舎間の通路に敷きつめてあった。そこにひ弱そうなキノコが生える、このキノコは便所の床などにも生えるのだが、これを大事に帽子の中などに摘んできては雑炊に中にいれる。
雑炊と言っても米の一粒も入っていないものだったが、キノコ毒とかなんとかは考えた事もなかった。最近日本農業技術協会の茸《きのこ》に関する本を読んだが世界には毒茸《どくたけ》は結構多くて時には死ぬ事もあるとか、毒があったにしても一度に食べる量が少なかったから良かったのかもしれない。
或る時蔦(つた)かつらの様な葉っぱを大量に摘んできて大なべで何時間も茹《ゆ》であくを抜いて、食べてみたがゴワゴワしていてとても食べられしろものでは無かった。尾ろうな話だが真っ黒いウンコが出た。こんな中でも初年兵は労働を強いられるのだ、
薪《たきぎ》拾いから風呂《ふろ》(ドラム缶)の水汲みと休む暇も無い、班長や古年兵はいろいろのルートから栄養の補給が出来るようだが、初年兵にはそんなルートは無いのだ。いわば最低の栄養で最大の労働を強いられるのだ、従って真っ先に倒れるのは初年兵である、初年兵3人の中で一人倒れれば残るものに其の負担が掛かってくるのである、たまったものではない、何時の時代も世の中は弱肉強食なのである、原隊にでもいれば後から来る新兵にバトン タッチ出来る頃なのに後が来ないのだ。
南十字星の下で その12 97/04/08 10:56
戦 況
我々はペリリュウに敵が上陸して来たのはかなり早い時期だとばっかり思っていたが、後で分かったのだが海空からの砲爆撃を加えてはいたものの、敵が実際上陸を開始したのは9月の下旬頃からだったらしい、コロールに近くに小高い山があり、兵隊はこれを哨戒《しょうかい=見張り》山と呼んでいたが、そこに登りマラカル沖を見渡すと60数隻の船舶の残骸《ざんがい》のかなたに敵の大船団が見えたそうだ。
その軍艦がペリリューに猛攻を加える傍ら《かたわら》時折本島にも艦砲射撃を仕掛けてくるのだ、これは弾丸が大きいだけ恐ろしかった、幸い我々の宿舎は島の裏側らしく直接の被害はなかったが、一方的の攻撃で当方は傍観するのみだった、夜間には砲撃の爆発音がよく聞こえた、これは破壊が目的ではなく威嚇《いかく=おどかし》が目的のものだったと思う。砲兵隊での経験から言えば、砲兵が一旦《いったん》目標をきめれば、初弾が命中しなくても、2弾、3弾と微調整で修正していけば必ず命中するようには成っているのだが、真昼の砲撃は本島にはなかった様に思う。
びんろう樹
ビンロウ樹 は年輪の無い南方特有の木で成長が早く葉は一見して椰子《やし》の葉に似ていて、木の芯《しん》は白い繊維を束ねたようで水分を多く含んでいて柔かくて外皮から取除き易い、そして非常に成長が早いが外皮は硬く、竹のようで割りやすく、丸太の場合は柱になり、割った場合は芯を取り除いて床などに張れ、利用度の高い木である、年数がたつとギンナンのようで真っ赤な実がたくさんなり、現地の人達はそれを口に入れて唇《くちびる》を真っ赤にして噬《か》んでいた。その時石灰を少し付けるのだそうだ、酸味を中和するのかもしれない。ビンロウ樹は倒して、これから芽になって行く部分の20センチぐらいの芯を煮て食べた、これはアクが強く旨くはないが腹の足しにはなった。
椰 子《やし》
椰子は南方を代表する樹である、各民家の庭先などに多く植えられ高いところに、沢山と花が咲き4ケ月ほどで食べられる、いわゆる椰子の実で貴重な食料となる。民家で子どもに頼んだら10メートメも有る木にするすると登り実を落としてくれた、すこし若いものを蛮刀で、頭部を切り落とし穴を開けてくれた、これが意外に冷えており旨く格好の飲料水となった、また中の硬い殻を割り周りに付いている白色のコプラは スプーンで削れるほど柔らかく美味《うま》かった。
充分熟した椰子はコプラの肉が厚く堅くなりこれから椰子油を取るのである。コプラは戦前はパラオの地場産業になっていた。 植林した椰子林に行ったことがあるが、当時は管理する人も無く荒れ果てていた落下した椰子の実がゴロゴロと転がっていた、この中で芽の出かけたものを拾いそれを割ってみると中は柔らかいスポンジ状になっており島民の人はこれを椰子リンゴと呼んでいた、本当にリンゴの味がした。
珍味だったのは隣の班の軍曹が椰子の木を一本切り倒してビンロウ樹の時と同じ要領でてっぺんの芽の芯のところを取り出し50センチほどのもの(普通の筍《たけのこ》の10本分ほど)を煮ておすそ分けして呉れたが、これはあくだししなくても旬の筍以上で、甘みがあり絶品だった。しかしこの椰子の木を切るのは実は堅く禁じられていたのであった。椰子が成長して実を付けるのには5,6年かかるのだから、そして最後に頼れる栄養源だったのだらう。
タビオカ (キャッサバ)
タビオカ芋は内地には無い珍しい芋である、主として澱粉《でんぷん》を取る為に植えられるのだ、桑の枝の様な棒を差しておくと半年程でかなり大きな芋になるのである。
茹でて食べれば淡白でホクホクとして美味く腹の足しにもなる、ところがこれが畑で一年も過ぎれば青酸性を帯びてくるのである、ある兵隊が島民の畑からくすねてきたイモを食べて物すごい下痢症状になりダウンしてしまった、相当重傷だったらしい、それ以来上部から絶対タビオカ畑には近づかないようにとの指令がでた、詰まらぬ事で死にでもしたらたまらない、君子危うきに近寄らずである。
このイモをおろし澱粉をしぼり、カスを蒸して臼《うす》でつけば餅《もち》になる、これは本物の餅と見まがうものである、実はこれで正月の雑煮を作ったのである。
”ジャングル”へ
うっそうと言うほどではないが、木漏れ日がさす程度の、ジャングルの空からは見えない場所に我が分隊が宿泊できそうなバラックを建て、そしてそこに落ち付くことになった。
南方では冬の暖房のことを考えずに設営出来るから其《そ》の点は楽である、屋根は大きな天幕を掛けるだけである、外壁はビンロウ樹か椰子《やし》の葉で代用するが、蚊の出入りは自由である、蚊の媒介はデング熱だけでマラリヤが無くてよかった、デング熱は内地のはしかの様なもので皆一度は掛かった黄疸《おうだん》の様な症状になり発熱するが4,5日で治った。炊事班の小屋は後から建てた、トイレは海水の満ち退きするところに造った、自然の水洗便所だ,潮が満ちてくると魚が集まってきた、落下物をねらってくるのだ背中に斑点のある魚で兵隊は俗っぽく”クソックイ”と呼んでいた。
敵機に見付からないように、炊事班は朝早く煮炊きをするのだ、それも食料受領のたびにその配給量は減っていくのである。兵糧などもっと本島にも備蓄して置くべきだったろうに、全く残念だった、焼残りかまたは難を逃れた僅《わず》かな食料を遅蒔き《おそまき》ながら分散して保管するようにはなったのだが、ちょっと後手だった。 個人的の煮炊きは庭先の防空壕《ぼうくうごう》の奥に造ったかまどを使ってやった、煙を避けて腹ばいでの難行だった。補給が少なくなるに連れて、流通中に何か不正があったらしい、運搬途上に抜かれる、炊事班に着いてから将校用に抜かれる,炊事班の兵隊が当然の権利として頂く、古手の班長用に横流する、これでは末端の兵隊に届くのは定量の何分の1かになってしまうのだ。
半年もすると米は全く入らなくなった、補給路が断たれているのだから無理も無い、米が無くなってそれに替わってサツマイモか配給されるようになった、それも握りこぶし位のやつが1日に2個だった、子どもの頃祖母が胸が焼けると言っていた意味が体験を通じてやっと分かって来た。 このぐらいの量で大のおとながいきていけるとは思えない。
開墾
生きるための自活の闘いが始まるのである。島民の畑を取り上げるわけにもいかず、ジャングルを切り開いて開墾することになったのである、食べ物が無なり体力も衰えて来た兵隊が一抱えもある大木を切り倒して畑を作るのである、島民から借りて来たであろう鋸《のこぎり》や斧《おの》で伐採していくのである、敵機がくればジャングルに逃げ込み、出て来てはまた続ける能率は全く上がらない100坪の土地を切り開いても倒した木を適当に切ってあちこちに積んで置くので、それに場所を取られるそれに切り倒した木の抜根ができないので使える土地はせいぜい1/3位のものだ、斜面なので一坪《=約3,3平方メートル》ほどの土まんじゅうのような畑が10個所ほどできた、堆肥《たいひ=わらやごみなどの積み肥》の替わりに木の葉や草を埋めて、芋の苗を貰《もら》ってきてそれぞれ2,30本も植えたか、土地が痩《や》せており、たしか鼠《ねずみ》のシッポのような藷《いも》が取れただけだったと思う。帰還後知ったのだが生の堆肥はそれ自体が腐るのに窒素を取るから植物にはマイナスになってもプラスにはならないとかだった。
労多くして益の無い企画だった。
苗は植えてから収穫まで4ケ月もかかる、待っているわけにもいかない、今たべるものがほしいのだ、ジャングルの中を木の芽や、動き回るものを求めてさまよった、さつまいもの葉っぱ等はご馳走の部類だった、ジャングルの中は年中じめじめしているので、ビンロウ樹を80センチほどに切って各兵舎間の通路に敷きつめてあった。そこにひ弱そうなキノコが生える、このキノコは便所の床などにも生えるのだが、これを大事に帽子の中などに摘んできては雑炊に中にいれる。
雑炊と言っても米の一粒も入っていないものだったが、キノコ毒とかなんとかは考えた事もなかった。最近日本農業技術協会の茸《きのこ》に関する本を読んだが世界には毒茸《どくたけ》は結構多くて時には死ぬ事もあるとか、毒があったにしても一度に食べる量が少なかったから良かったのかもしれない。
或る時蔦(つた)かつらの様な葉っぱを大量に摘んできて大なべで何時間も茹《ゆ》であくを抜いて、食べてみたがゴワゴワしていてとても食べられしろものでは無かった。尾ろうな話だが真っ黒いウンコが出た。こんな中でも初年兵は労働を強いられるのだ、
薪《たきぎ》拾いから風呂《ふろ》(ドラム缶)の水汲みと休む暇も無い、班長や古年兵はいろいろのルートから栄養の補給が出来るようだが、初年兵にはそんなルートは無いのだ。いわば最低の栄養で最大の労働を強いられるのだ、従って真っ先に倒れるのは初年兵である、初年兵3人の中で一人倒れれば残るものに其の負担が掛かってくるのである、たまったものではない、何時の時代も世の中は弱肉強食なのである、原隊にでもいれば後から来る新兵にバトン タッチ出来る頃なのに後が来ないのだ。
南十字星の下で その12 97/04/08 10:56
戦 況
我々はペリリュウに敵が上陸して来たのはかなり早い時期だとばっかり思っていたが、後で分かったのだが海空からの砲爆撃を加えてはいたものの、敵が実際上陸を開始したのは9月の下旬頃からだったらしい、コロールに近くに小高い山があり、兵隊はこれを哨戒《しょうかい=見張り》山と呼んでいたが、そこに登りマラカル沖を見渡すと60数隻の船舶の残骸《ざんがい》のかなたに敵の大船団が見えたそうだ。
その軍艦がペリリューに猛攻を加える傍ら《かたわら》時折本島にも艦砲射撃を仕掛けてくるのだ、これは弾丸が大きいだけ恐ろしかった、幸い我々の宿舎は島の裏側らしく直接の被害はなかったが、一方的の攻撃で当方は傍観するのみだった、夜間には砲撃の爆発音がよく聞こえた、これは破壊が目的ではなく威嚇《いかく=おどかし》が目的のものだったと思う。砲兵隊での経験から言えば、砲兵が一旦《いったん》目標をきめれば、初弾が命中しなくても、2弾、3弾と微調整で修正していけば必ず命中するようには成っているのだが、真昼の砲撃は本島にはなかった様に思う。
びんろう樹
ビンロウ樹 は年輪の無い南方特有の木で成長が早く葉は一見して椰子《やし》の葉に似ていて、木の芯《しん》は白い繊維を束ねたようで水分を多く含んでいて柔かくて外皮から取除き易い、そして非常に成長が早いが外皮は硬く、竹のようで割りやすく、丸太の場合は柱になり、割った場合は芯を取り除いて床などに張れ、利用度の高い木である、年数がたつとギンナンのようで真っ赤な実がたくさんなり、現地の人達はそれを口に入れて唇《くちびる》を真っ赤にして噬《か》んでいた。その時石灰を少し付けるのだそうだ、酸味を中和するのかもしれない。ビンロウ樹は倒して、これから芽になって行く部分の20センチぐらいの芯を煮て食べた、これはアクが強く旨くはないが腹の足しにはなった。
椰 子《やし》
椰子は南方を代表する樹である、各民家の庭先などに多く植えられ高いところに、沢山と花が咲き4ケ月ほどで食べられる、いわゆる椰子の実で貴重な食料となる。民家で子どもに頼んだら10メートメも有る木にするすると登り実を落としてくれた、すこし若いものを蛮刀で、頭部を切り落とし穴を開けてくれた、これが意外に冷えており旨く格好の飲料水となった、また中の硬い殻を割り周りに付いている白色のコプラは スプーンで削れるほど柔らかく美味《うま》かった。
充分熟した椰子はコプラの肉が厚く堅くなりこれから椰子油を取るのである。コプラは戦前はパラオの地場産業になっていた。 植林した椰子林に行ったことがあるが、当時は管理する人も無く荒れ果てていた落下した椰子の実がゴロゴロと転がっていた、この中で芽の出かけたものを拾いそれを割ってみると中は柔らかいスポンジ状になっており島民の人はこれを椰子リンゴと呼んでいた、本当にリンゴの味がした。
珍味だったのは隣の班の軍曹が椰子の木を一本切り倒してビンロウ樹の時と同じ要領でてっぺんの芽の芯のところを取り出し50センチほどのもの(普通の筍《たけのこ》の10本分ほど)を煮ておすそ分けして呉れたが、これはあくだししなくても旬の筍以上で、甘みがあり絶品だった。しかしこの椰子の木を切るのは実は堅く禁じられていたのであった。椰子が成長して実を付けるのには5,6年かかるのだから、そして最後に頼れる栄養源だったのだらう。
タビオカ (キャッサバ)
タビオカ芋は内地には無い珍しい芋である、主として澱粉《でんぷん》を取る為に植えられるのだ、桑の枝の様な棒を差しておくと半年程でかなり大きな芋になるのである。
茹でて食べれば淡白でホクホクとして美味く腹の足しにもなる、ところがこれが畑で一年も過ぎれば青酸性を帯びてくるのである、ある兵隊が島民の畑からくすねてきたイモを食べて物すごい下痢症状になりダウンしてしまった、相当重傷だったらしい、それ以来上部から絶対タビオカ畑には近づかないようにとの指令がでた、詰まらぬ事で死にでもしたらたまらない、君子危うきに近寄らずである。
このイモをおろし澱粉をしぼり、カスを蒸して臼《うす》でつけば餅《もち》になる、これは本物の餅と見まがうものである、実はこれで正月の雑煮を作ったのである。