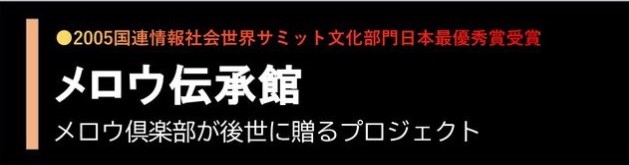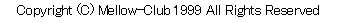祖父の戦死記録調査5
投稿ツリー
-
 ある学徒兵の死 (スカッパー) <一部英訳あり> (スカッパー, 2007/2/3 15:26)
ある学徒兵の死 (スカッパー) <一部英訳あり> (スカッパー, 2007/2/3 15:26)
-
 ルソン島 クラーク西方での戦死者(祖父)について (KyoYamO, 2007/4/29 3:46)
ルソン島 クラーク西方での戦死者(祖父)について (KyoYamO, 2007/4/29 3:46)
-
 Re: ルソン島 クラーク西方での戦死者(祖父)について (スカッパー, 2007/4/29 19:33)
Re: ルソン島 クラーク西方での戦死者(祖父)について (スカッパー, 2007/4/29 19:33)
-
 Re: ルソン島 クラーク西方での戦死者(祖父)について (KyoYamO, 2007/4/29 23:18)
Re: ルソン島 クラーク西方での戦死者(祖父)について (KyoYamO, 2007/4/29 23:18)
-
 Re: ルソン島 クラーク西方での戦死者(祖父)について (スカッパー, 2007/4/30 15:16)
Re: ルソン島 クラーク西方での戦死者(祖父)について (スカッパー, 2007/4/30 15:16)
-
 Re: ルソン島 クラーク西方での戦死者(祖父)について (スカッパー, 2007/4/30 19:10)
Re: ルソン島 クラーク西方での戦死者(祖父)について (スカッパー, 2007/4/30 19:10)
-
 Re: ルソン島 クラーク西方での戦死者(祖父)について (スカッパー, 2007/4/30 21:07)
Re: ルソン島 クラーク西方での戦死者(祖父)について (スカッパー, 2007/4/30 21:07)
-
 Re: ルソン島 クラーク西方での戦死者(祖父)について (KyoYamO, 2007/5/1 0:30)
Re: ルソン島 クラーク西方での戦死者(祖父)について (KyoYamO, 2007/5/1 0:30)
-
 Re: ルソン島 クラーク西方での戦死者(祖父)について (スカッパー, 2007/5/2 11:42)
Re: ルソン島 クラーク西方での戦死者(祖父)について (スカッパー, 2007/5/2 11:42)
-
 Re: ルソン島 クラーク西方での戦死者(祖父)について (KyoYamO, 2007/5/3 18:23)
Re: ルソン島 クラーク西方での戦死者(祖父)について (KyoYamO, 2007/5/3 18:23)
-
 Re: ルソン島 クラーク西方での戦死者(祖父)について (スカッパー, 2007/5/3 21:33)
Re: ルソン島 クラーク西方での戦死者(祖父)について (スカッパー, 2007/5/3 21:33)
-
 Re: ルソン島 クラーク西方での戦死者(祖父)について (スカッパー, 2007/5/4 8:33)
Re: ルソン島 クラーク西方での戦死者(祖父)について (スカッパー, 2007/5/4 8:33)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 Re: ルソン島 クラーク西方での戦死者(祖父)について (KyoYamO, 2007/5/4 16:27)
Re: ルソン島 クラーク西方での戦死者(祖父)について (KyoYamO, 2007/5/4 16:27)
-
 戦没者調査の参考として (KyoYamO, 2007/5/15 23:00)
戦没者調査の参考として (KyoYamO, 2007/5/15 23:00)
-
 祖父の戦死記録調査1 (KyoYamO, 2007/6/15 0:48)
祖父の戦死記録調査1 (KyoYamO, 2007/6/15 0:48)
-
 祖父の戦死記録調査2 (KyoYamO, 2007/6/15 0:49)
祖父の戦死記録調査2 (KyoYamO, 2007/6/15 0:49)
-
 祖父の戦死記録調査3 (KyoYamO, 2007/6/15 0:51)
祖父の戦死記録調査3 (KyoYamO, 2007/6/15 0:51)
-
 祖父の戦死記録調査4 (KyoYamO, 2007/6/15 0:53)
祖父の戦死記録調査4 (KyoYamO, 2007/6/15 0:53)
-
 祖父の戦死記録調査5 (KyoYamO, 2007/6/15 0:55)
祖父の戦死記録調査5 (KyoYamO, 2007/6/15 0:55)
-
 祖父の戦死記録調査6 (KyoYamO, 2007/6/15 0:56)
祖父の戦死記録調査6 (KyoYamO, 2007/6/15 0:56)
-
 祖父の戦死記録調査7 (KyoYamO, 2007/6/15 0:58)
祖父の戦死記録調査7 (KyoYamO, 2007/6/15 0:58)
KyoYamO
 投稿数: 13
投稿数: 13
 投稿数: 13
投稿数: 13
6.西方山地への敗走
西方山地というのは、ピナツボ山とピナツボ山の北にあるナマコ山、そしてそれ以北に広がるザンバレス山系をさすようです。しかし、ほとんどの部隊が山篭り《やまごもり》の準備をしていなかったため、たちまちのうちに食糧難が襲い掛かりました。
4月中旬、司令部は今後の作戦方針を以下のように発表しています。
1) 治療を要しない病人と負傷者は西方およびイバに先行分散、自活をはかる
2) 戦闘可能なものは集団行動によりピナツボ山西方またはイバ方面に出て畑を占領、自活を計り、後期に乗じてゲリラ戦を行う
食糧難のため、フィリピンの地元民の畑や家屋から略奪を行い、時にはフィリピンの人々を殺し、山にあっては植物や果物、昆虫など食べられるものを手当たり次第に食べたそうです。劣悪な食糧事情と熱帯の気候、そして衛生状態の悪化があいまって、餓死したり赤痢《せきり=下痢を繰り返す伝染病》、マラリア、チフスなどに罹患《りかん》する兵士が続出しました。山中を行軍する兵士たちは常に食糧のことを考えていた、といいます。民家や畑があるところにはすでに米軍がいて、畑の作物を採ろうとすることはイコール米軍あるいは比米軍に撃たれる、ということだったそうです。そのため、米軍や比米軍に気づかれないようにするには険しい山中を行軍するしかなく、食糧はつねに欠乏し、体力も限界まで消耗し、本当にいつ倒れてもおかしくない状況だったといいます。生還した人々が手記の中で、「死んだほうがよっぽど幸せ」書いておられたほど、ルソン島での敗走は悲惨だったようです。
山中では方向を容易に見誤るため、隊から迷い出る兵士も多くあったそうですが、単独で行動するとほぼ確実に死が待っている状況でした。クラーク防衛隊司令部からの生還者たちの手記によると、部隊をはなれた「離れガラス」たちは埋葬してくれる戦友もなく、獣道《けものみち》の脇にごろごろと倒れていたそうです。
4月下旬以降、山中で残存していた兵たちは徐々に5人前後や10人前後の隊に分かれるようになりました。祖父の最期の時が判明しているのも、きっと小隊になって行動していたからだと思います。絶望的な状況でも、友軍が駆けつけてくれると信じて必死で生き延びようとしていたようです。しかし、空に見えるのは米軍の飛行機だけだったと生還者は語っています(石長真華氏の著書より)。
米軍機は時々「落下傘ニュース」という、日本語、中国語、タガログ語で書かれた国際情勢や戦況を記した新聞を、日本軍が潜伏している場所にばら撒《ま》いたそうですから、祖父もある程度戦況は把握していたのではないかと思います。ただ、祖父の戦死はポツダム宣言より以前なので、祖父の心境としては、敗戦の色は濃いが、きっと友軍が助けに来てくれる、と思っていたのではないでしょうか。
クラーク防衛隊に関しては、終戦後戦犯の審議対象にはなっていません。というのも、岩崎敏夫 第219設営隊副隊長の著書『ルソン海軍設営隊戦記』光人社 によると、防衛隊の兵士たちはクラークに配備されてすぐに山に追われる結果となってしまい、密林の中でひたすら米軍から逃げ惑う生活だったため、フィリピンの地元民たちと出会う機会がまったくなかったそうです。4月下旬になり、残存部隊が小隊に分かれて山中を彷徨《ほうこう》するようになって初めてフィリピン人ゲリラに遭遇し、何も知らない日本兵は「ハロー」といって手を振ったところ、撃たれた、という記述がありました。残存兵たちは、そのとき初めてフィリピン人ゲリラの存在を知ったそうです(88頁)。
陸軍が終戦後に編纂《へんさん=編集》した記録によると、建武集団は編成時に約3万人だったのが終戦時には1300人程になっていたといいます。建武集団の約8割の人々は終戦までに命を落とした計算です。そして、陸軍建武集団の公式な戦闘記録は昭和20年4月20日ごろで終わってしまいます。兵士がみな散り散りになってしまって、かれらの行く先もたどることが出来なかっただからだと推測します。一方、海軍所属のクラーク防衛隊の記録は比較的よく残っていました。これは、クラーク防衛隊の本部(第16戦区)の士官たちの生還数が比較的多かったことと関係があると思います。
318設営隊の副隊長だった岡沢氏の手記によると、318設営隊は17戦区とともに行動しながら、比較的早い時期にザンバレス山系を北へ向かっていったそうです。というのは、本部(第16戦区)が通るときの道を開いておかなければならなかったからです。
17戦区は他の部隊に比べると、比較的食糧を多く携行していたらしく、かえってそれが仇《あだ》になった、という話を生還者から聞きました。17戦区は、本部が通るための前哨《ぜんしょう=本隊の前に配置して警戒に当たる小隊》の役割を果たすと同時に、本部が必要とする食糧を安全に移動させる任務もあったと推測します。缶詰や塩などが重く、一人あたり30kgにもなる装備になっていて、身軽に行動ができなかったようです。重い荷物を携行する兵士の体力も当然消耗します。さらに、飢えた友軍の兵士により、食糧の略奪が横行し、ついには食糧をめぐって17戦区の兵士と別部隊の兵士が殺し合いをしたこともあったそうです。
***後に続く***
西方山地というのは、ピナツボ山とピナツボ山の北にあるナマコ山、そしてそれ以北に広がるザンバレス山系をさすようです。しかし、ほとんどの部隊が山篭り《やまごもり》の準備をしていなかったため、たちまちのうちに食糧難が襲い掛かりました。
4月中旬、司令部は今後の作戦方針を以下のように発表しています。
1) 治療を要しない病人と負傷者は西方およびイバに先行分散、自活をはかる
2) 戦闘可能なものは集団行動によりピナツボ山西方またはイバ方面に出て畑を占領、自活を計り、後期に乗じてゲリラ戦を行う
食糧難のため、フィリピンの地元民の畑や家屋から略奪を行い、時にはフィリピンの人々を殺し、山にあっては植物や果物、昆虫など食べられるものを手当たり次第に食べたそうです。劣悪な食糧事情と熱帯の気候、そして衛生状態の悪化があいまって、餓死したり赤痢《せきり=下痢を繰り返す伝染病》、マラリア、チフスなどに罹患《りかん》する兵士が続出しました。山中を行軍する兵士たちは常に食糧のことを考えていた、といいます。民家や畑があるところにはすでに米軍がいて、畑の作物を採ろうとすることはイコール米軍あるいは比米軍に撃たれる、ということだったそうです。そのため、米軍や比米軍に気づかれないようにするには険しい山中を行軍するしかなく、食糧はつねに欠乏し、体力も限界まで消耗し、本当にいつ倒れてもおかしくない状況だったといいます。生還した人々が手記の中で、「死んだほうがよっぽど幸せ」書いておられたほど、ルソン島での敗走は悲惨だったようです。
山中では方向を容易に見誤るため、隊から迷い出る兵士も多くあったそうですが、単独で行動するとほぼ確実に死が待っている状況でした。クラーク防衛隊司令部からの生還者たちの手記によると、部隊をはなれた「離れガラス」たちは埋葬してくれる戦友もなく、獣道《けものみち》の脇にごろごろと倒れていたそうです。
4月下旬以降、山中で残存していた兵たちは徐々に5人前後や10人前後の隊に分かれるようになりました。祖父の最期の時が判明しているのも、きっと小隊になって行動していたからだと思います。絶望的な状況でも、友軍が駆けつけてくれると信じて必死で生き延びようとしていたようです。しかし、空に見えるのは米軍の飛行機だけだったと生還者は語っています(石長真華氏の著書より)。
米軍機は時々「落下傘ニュース」という、日本語、中国語、タガログ語で書かれた国際情勢や戦況を記した新聞を、日本軍が潜伏している場所にばら撒《ま》いたそうですから、祖父もある程度戦況は把握していたのではないかと思います。ただ、祖父の戦死はポツダム宣言より以前なので、祖父の心境としては、敗戦の色は濃いが、きっと友軍が助けに来てくれる、と思っていたのではないでしょうか。
クラーク防衛隊に関しては、終戦後戦犯の審議対象にはなっていません。というのも、岩崎敏夫 第219設営隊副隊長の著書『ルソン海軍設営隊戦記』光人社 によると、防衛隊の兵士たちはクラークに配備されてすぐに山に追われる結果となってしまい、密林の中でひたすら米軍から逃げ惑う生活だったため、フィリピンの地元民たちと出会う機会がまったくなかったそうです。4月下旬になり、残存部隊が小隊に分かれて山中を彷徨《ほうこう》するようになって初めてフィリピン人ゲリラに遭遇し、何も知らない日本兵は「ハロー」といって手を振ったところ、撃たれた、という記述がありました。残存兵たちは、そのとき初めてフィリピン人ゲリラの存在を知ったそうです(88頁)。
陸軍が終戦後に編纂《へんさん=編集》した記録によると、建武集団は編成時に約3万人だったのが終戦時には1300人程になっていたといいます。建武集団の約8割の人々は終戦までに命を落とした計算です。そして、陸軍建武集団の公式な戦闘記録は昭和20年4月20日ごろで終わってしまいます。兵士がみな散り散りになってしまって、かれらの行く先もたどることが出来なかっただからだと推測します。一方、海軍所属のクラーク防衛隊の記録は比較的よく残っていました。これは、クラーク防衛隊の本部(第16戦区)の士官たちの生還数が比較的多かったことと関係があると思います。
318設営隊の副隊長だった岡沢氏の手記によると、318設営隊は17戦区とともに行動しながら、比較的早い時期にザンバレス山系を北へ向かっていったそうです。というのは、本部(第16戦区)が通るときの道を開いておかなければならなかったからです。
17戦区は他の部隊に比べると、比較的食糧を多く携行していたらしく、かえってそれが仇《あだ》になった、という話を生還者から聞きました。17戦区は、本部が通るための前哨《ぜんしょう=本隊の前に配置して警戒に当たる小隊》の役割を果たすと同時に、本部が必要とする食糧を安全に移動させる任務もあったと推測します。缶詰や塩などが重く、一人あたり30kgにもなる装備になっていて、身軽に行動ができなかったようです。重い荷物を携行する兵士の体力も当然消耗します。さらに、飢えた友軍の兵士により、食糧の略奪が横行し、ついには食糧をめぐって17戦区の兵士と別部隊の兵士が殺し合いをしたこともあったそうです。
***後に続く***