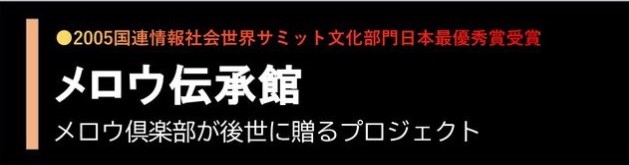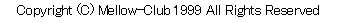アジア鎮魂の旅・その8
投稿ツリー
-
 アジア鎮魂の旅 (編集者, 2008/4/11 7:26)
アジア鎮魂の旅 (編集者, 2008/4/11 7:26)
-
 アジア鎮魂の旅・その2 (編集者, 2008/4/13 8:58)
アジア鎮魂の旅・その2 (編集者, 2008/4/13 8:58)
-
 アジア鎮魂の旅・その3 (編集者, 2008/4/14 8:18)
アジア鎮魂の旅・その3 (編集者, 2008/4/14 8:18)
-
 アジア鎮魂の旅・その4 (編集者, 2008/4/16 7:23)
アジア鎮魂の旅・その4 (編集者, 2008/4/16 7:23)
-
 アジア鎮魂の旅・その5 (編集者, 2008/4/18 8:11)
アジア鎮魂の旅・その5 (編集者, 2008/4/18 8:11)
-
 アジア鎮魂の旅・その6 (編集者, 2008/4/20 7:59)
アジア鎮魂の旅・その6 (編集者, 2008/4/20 7:59)
-
 アジア鎮魂の旅・その7 (編集者, 2008/4/22 7:41)
アジア鎮魂の旅・その7 (編集者, 2008/4/22 7:41)
-
 アジア鎮魂の旅・その8 (編集者, 2008/4/24 7:44)
アジア鎮魂の旅・その8 (編集者, 2008/4/24 7:44)
-
 アジア鎮魂の旅・その9 (編集者, 2008/4/26 7:31)
アジア鎮魂の旅・その9 (編集者, 2008/4/26 7:31)
-
 アジア鎮魂の旅・その10 (編集者, 2008/4/28 7:49)
アジア鎮魂の旅・その10 (編集者, 2008/4/28 7:49)
-
 アジア鎮魂の旅・その11 (編集者, 2008/4/30 8:15)
アジア鎮魂の旅・その11 (編集者, 2008/4/30 8:15)
-
 アジア鎮魂の旅・その12 (編集者, 2008/5/3 7:59)
アジア鎮魂の旅・その12 (編集者, 2008/5/3 7:59)
-
 アジア鎮魂の旅・その13 (編集者, 2008/5/16 9:04)
アジア鎮魂の旅・その13 (編集者, 2008/5/16 9:04)
-
編集者
 居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
 居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
筏を漕いで食糧受領
第三回目の 食糧受領の頃から、少量ながらも米が配給される様になった。当番は夫々2㌔程の米を 背嚢<はいのう>に詰め 之を背負い 潅木<かんぼく>の湿地帯に足を取られながら13㌔の道程を帰るのだが、栄養失調の体には大変な重労働であった。 空腹の為受領した生米をポリポリ噛み、杖に縋って歩く姿は、今にも行き倒れに成りそうな哀れな光景であった。
この様な状況下では、人間の理性を失って本能を剥き出した、悲しい事件も現実に起こった。 ジャングルの街道筋に、同じ日本人の「 追い剥ぎ 」が現れたのである。
元は互いに命を掛け滅私奉公<めっしほうこう>を誓い合った同士でありながら、惨めな姿で食糧を受領して帰る当番一行を、事も有ろうに 丸太棒で威嚇し 「 やい・・・米を置いて行け! 」と言うのである。
仲間達が命の綱とし 首を長くして待っている大事な 大事な米ではあるが、この弱った体に乱暴されて死ぬ様な事が有っては 馬鹿々々しい・・・と已む無く 一人両手に一杯ぐらいを盗られ、無念な思いで帰る事が屡々起こった。
今考えると、両手一杯ずつの米を盗って行った 追い剥ぎ 達も、全部の米を奪う程の悪党ではなかったと思えるが、其の後は追い剥ぎの被害を防ぐ為 ジャングルから伐採した木を集めて「筏」を作り、海上を利用する運搬作業に一部変更した。全長7~8㍍の筏に携帯天幕の帆を張り、潮流の激しいガラン島との海峡「早瀬水道」を櫂だけでなく 、マングロープの根に掴まりながら進むのは、陸上の倍以上の労力を費やした。
追い剥ぎの危険が無いとはいえ、之も命懸けの仕事である。 そんな我々の 喘ぐ様な姿を笑うかのように、筏の周りにはイルカ達が遊んでいたが之も懐かしい思い出である。
島に上陸以来、日を追う毎に、食糧の量的不足とカロリー不足で、衰弱していった。更に非衛生的のため アメーバー赤痢や脚気などの病気に罹る者や、蚊によってマラリヤに罹り 発熱する者が続出して来た。特に全員が罹り、悩まされたのが 南方浮腫<なんぽうふしゅ>である。
之は皮膚病で、別名「飢餓浮腫<きがふしゅ>」とも言い、体中に天然痘のような小豆粒くらいの浮腫が出来て化膿し、 痛い! 痒い!と苦しむのである。 私も之に罹り 大変な思いをした。
皆が 何かしらの病気に罹<かか>ったが、僅かに持参した薬品は其処を尽き 13㌔も離れた司令部の診療所へ行く事も病人としては不可能な事であり、結果的には休養して回復を待つより他は無かった。
この様な栄養失調患者の多い我々多根村にも、使役の割り当ては容赦<ようしゃ>なく回って来た。
使役の内容は千鳥港や宝港の沖合いに停泊した船から、荷物を機汎船に積み替え、さらに其の荷物を揚陸し整理する仕事であり、比較的に丈夫であった若者には頻繁にこの仕事が回って来た。 また この使役に行く時には必ず一名の員数外の者がついて行き、連合国側の監視兵たちが捨てたタバコの吸殻を拾う「モクヒロイ」と袋のキズからこぼれ落ちた「アタ粉」を集めるのが仕事である。 ねぐらに持ち帰ったタバコは、天日で乾燥した「南方葉ぼたん」と混ぜ合せ、古い雑誌の紙に巻き全員で回して吸いながら レンパン製ラッキーストライクのうまさを味わい 又砂の混じった アタ粉は風を使って砂を分離するのだが中々上手く行かない。 多少砂が混じっても、空腹さえ満たされれば満足であったので、使役に出た班の役得として分かち合って腹の足しにした。
2006年8月24日 (木) 記
第三回目の 食糧受領の頃から、少量ながらも米が配給される様になった。当番は夫々2㌔程の米を 背嚢<はいのう>に詰め 之を背負い 潅木<かんぼく>の湿地帯に足を取られながら13㌔の道程を帰るのだが、栄養失調の体には大変な重労働であった。 空腹の為受領した生米をポリポリ噛み、杖に縋って歩く姿は、今にも行き倒れに成りそうな哀れな光景であった。
この様な状況下では、人間の理性を失って本能を剥き出した、悲しい事件も現実に起こった。 ジャングルの街道筋に、同じ日本人の「 追い剥ぎ 」が現れたのである。
元は互いに命を掛け滅私奉公<めっしほうこう>を誓い合った同士でありながら、惨めな姿で食糧を受領して帰る当番一行を、事も有ろうに 丸太棒で威嚇し 「 やい・・・米を置いて行け! 」と言うのである。
仲間達が命の綱とし 首を長くして待っている大事な 大事な米ではあるが、この弱った体に乱暴されて死ぬ様な事が有っては 馬鹿々々しい・・・と已む無く 一人両手に一杯ぐらいを盗られ、無念な思いで帰る事が屡々起こった。
今考えると、両手一杯ずつの米を盗って行った 追い剥ぎ 達も、全部の米を奪う程の悪党ではなかったと思えるが、其の後は追い剥ぎの被害を防ぐ為 ジャングルから伐採した木を集めて「筏」を作り、海上を利用する運搬作業に一部変更した。全長7~8㍍の筏に携帯天幕の帆を張り、潮流の激しいガラン島との海峡「早瀬水道」を櫂だけでなく 、マングロープの根に掴まりながら進むのは、陸上の倍以上の労力を費やした。
追い剥ぎの危険が無いとはいえ、之も命懸けの仕事である。 そんな我々の 喘ぐ様な姿を笑うかのように、筏の周りにはイルカ達が遊んでいたが之も懐かしい思い出である。
島に上陸以来、日を追う毎に、食糧の量的不足とカロリー不足で、衰弱していった。更に非衛生的のため アメーバー赤痢や脚気などの病気に罹る者や、蚊によってマラリヤに罹り 発熱する者が続出して来た。特に全員が罹り、悩まされたのが 南方浮腫<なんぽうふしゅ>である。
之は皮膚病で、別名「飢餓浮腫<きがふしゅ>」とも言い、体中に天然痘のような小豆粒くらいの浮腫が出来て化膿し、 痛い! 痒い!と苦しむのである。 私も之に罹り 大変な思いをした。
皆が 何かしらの病気に罹<かか>ったが、僅かに持参した薬品は其処を尽き 13㌔も離れた司令部の診療所へ行く事も病人としては不可能な事であり、結果的には休養して回復を待つより他は無かった。
この様な栄養失調患者の多い我々多根村にも、使役の割り当ては容赦<ようしゃ>なく回って来た。
使役の内容は千鳥港や宝港の沖合いに停泊した船から、荷物を機汎船に積み替え、さらに其の荷物を揚陸し整理する仕事であり、比較的に丈夫であった若者には頻繁にこの仕事が回って来た。 また この使役に行く時には必ず一名の員数外の者がついて行き、連合国側の監視兵たちが捨てたタバコの吸殻を拾う「モクヒロイ」と袋のキズからこぼれ落ちた「アタ粉」を集めるのが仕事である。 ねぐらに持ち帰ったタバコは、天日で乾燥した「南方葉ぼたん」と混ぜ合せ、古い雑誌の紙に巻き全員で回して吸いながら レンパン製ラッキーストライクのうまさを味わい 又砂の混じった アタ粉は風を使って砂を分離するのだが中々上手く行かない。 多少砂が混じっても、空腹さえ満たされれば満足であったので、使役に出た班の役得として分かち合って腹の足しにした。
2006年8月24日 (木) 記