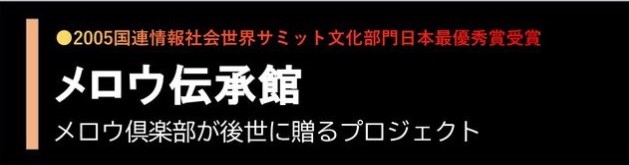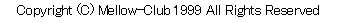朝鮮生まれの引揚者の雑記・その10
投稿ツリー
-
 朝鮮生まれの引揚者の雑記 <一部英訳あり> (編集者, 2006/9/24 21:47)
朝鮮生まれの引揚者の雑記 <一部英訳あり> (編集者, 2006/9/24 21:47)
-
 朝鮮生まれの引揚者の雑記・その1 (編集者, 2006/9/25 8:52)
朝鮮生まれの引揚者の雑記・その1 (編集者, 2006/9/25 8:52)
-
 朝鮮生まれの引揚者の雑記・その2 (編集者, 2006/9/25 8:54)
朝鮮生まれの引揚者の雑記・その2 (編集者, 2006/9/25 8:54)
-
 朝鮮生まれの引揚者の雑記・その3 (編集者, 2006/9/25 9:07)
朝鮮生まれの引揚者の雑記・その3 (編集者, 2006/9/25 9:07)
-
 朝鮮生まれの引揚者の雑記・その4 (編集者, 2006/10/18 8:18)
朝鮮生まれの引揚者の雑記・その4 (編集者, 2006/10/18 8:18)
-
 朝鮮生まれの引揚者の雑記・その5 (編集者, 2006/10/18 8:23)
朝鮮生まれの引揚者の雑記・その5 (編集者, 2006/10/18 8:23)
-
 朝鮮生まれの引揚者の雑記・その6 (編集者, 2006/10/19 19:27)
朝鮮生まれの引揚者の雑記・その6 (編集者, 2006/10/19 19:27)
-
 朝鮮生まれの引揚者の雑記・その7 (編集者, 2006/10/19 19:55)
朝鮮生まれの引揚者の雑記・その7 (編集者, 2006/10/19 19:55)
-
 朝鮮生まれの引揚者の雑記・その8 (編集者, 2006/10/22 20:47)
朝鮮生まれの引揚者の雑記・その8 (編集者, 2006/10/22 20:47)
-
 朝鮮生まれの引揚者の雑記・その9 (編集者, 2006/10/23 7:42)
朝鮮生まれの引揚者の雑記・その9 (編集者, 2006/10/23 7:42)
-
 朝鮮生まれの引揚者の雑記・その10 (編集者, 2006/10/23 7:56)
朝鮮生まれの引揚者の雑記・その10 (編集者, 2006/10/23 7:56)
-
 朝鮮生まれの引揚者の雑記・その11 (編集者, 2006/11/24 8:00)
朝鮮生まれの引揚者の雑記・その11 (編集者, 2006/11/24 8:00)
-
 朝鮮生まれの引揚者の雑記・その12 (編集者, 2006/11/24 8:09)
朝鮮生まれの引揚者の雑記・その12 (編集者, 2006/11/24 8:09)
-
 朝鮮生まれの引揚者の雑記・その13 (編集者, 2006/11/25 8:57)
朝鮮生まれの引揚者の雑記・その13 (編集者, 2006/11/25 8:57)
-
 朝鮮生まれの引揚者の雑記・その14 (編集者, 2006/11/25 9:30)
朝鮮生まれの引揚者の雑記・その14 (編集者, 2006/11/25 9:30)
-
 Re: 朝鮮生まれの引揚者の雑記 (HI0815, 2006/12/26 8:58)
Re: 朝鮮生まれの引揚者の雑記 (HI0815, 2006/12/26 8:58)
-
編集者
 居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
 居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
#3 邦人の生活と脱出 闇船
敗戦の後の双浦地区には工場の従業員と家族のほか、北から下りてきた人を併せて日本人は五千人あまりいた。この中心は工場長だがロスケが来るとすぐ、工場長と幹部とはソ連軍に連れていかれた。技師長が拉致《らち》されなかったので、この人を中心に工場の有志の若手社員が尽力に立ち上がってくれた。
危険な道を京城《ソウル》本社との連絡に三十八度線を往復もした。ソ連軍、朝鮮人との折衝《せっしょう》には、大変な苦労を重ね、やがて日本人世話会として活動するようになった。初めは北からの避難者の受け入れ、死亡者の埋葬、住居、食糧の配分等から無職者の帰国促進、後には他地区との連絡、闇船の計画交渉、編成、運行等大変な仕事をやり遂げた。そのおかげで混乱期を過ぎた後には殆ど犠牲者を出すことなしに、五千余りの者は帰国することができた。大きな功績は知る人のみぞ知る。感謝の極みである。
八月九日ソ連軍が満州と朝鮮に攻め込んで来たので、家族の疎開が始まって一部が移動している時敗戦になり、この人達は双浦にすぐ引き返してきた。十五日以後も鉄道は動いていたので、北から朝鮮人が大勢乗り込んで南下していた。双浦から日本人は極く一部の者がこれに乗って行き、京城《ソウル》に着いたのもあるが、途中北鮮で抑留され収容所で冬を過ごしたのもいる。(第一次脱出)
殆《ほとん》ど全員は双浦を離れることをせずにいたが、一時は全員南下する話があり、その時には入院患者の動かれない者をどうしようかと思案したこともあった。もしここを出ていく事になっていたらもっともっと悲惨な事になったろう。北鮮の地区によっては、「敗戦後すぐロスケが来る前に三十八度線から南に逃げておくべくだった」と、責任者を非難する記事を読んだが、双浦では動かなかったのが最善だったと信じている。
ソ連軍の乱暴狼藉が少なくなり、かなり治安が落ち着いてきた十月、工場の技術系某課長家族とその親戚の一団が船を仕立てて脱出に成功した。一行は無事南鮮に着き、京城《 ソウル》に出て二十年秋には日本へ帰っている。夜間極秘の出発で、病院の同僚もいるが(コレニツイテハ別ニ記スコトニナロウ)私は全く知らなかった。朝鮮側でも不意打ちだったのだろう、以後は警戒が厳しくなりこれに習って企てられたのは全て発見され、失敗に終わった(第二次脱出)。
年を越して暖かくなってからまだ移動禁止令は解けてなかったが、清津《チョンジン》、咸興《ハムフン》、元山《ウォンサン》等各地の日本人世帯会との連絡が取れるようになった。交渉はなかなか進まなかったが二十一年六月にようやく南への移動が黙認された。
鉄道貨車で三十八度線近くまで乗って行きあとは徒歩で山間を通り、川を渡って三十八度線を抜け、京城《ソウル》にたどり着いた。この一行は働き手のいない家族、病弱者、老人達が主な四百人の第一陣だったが、そのごすぐ鉄道貨車による南下はこの一回だけで中止された。元山《ウォンサン》にコレラが出たためと聞いた(第三次脱出)。
六月下旬からは海路で直接南鮮に行くことになった。所謂《いわゆる》、闇船で機会船や帆船で希望者の順に九百人が双浦の港を出発して行ったが、三十八度線を越える前に捕まえられて、双浦にもどされた船が多かった。家財道具を処分して出て行ったのでもどされたときは僅かな身の回りの物しかなく、次の出発まではそれまで以上の苦労だった。この闇船もまた中止になった(第四次脱出)。
世話会は計画を立て直して、南下は九月初めから再開された。今度は順調な軌道に乗って次々に双浦の港から出て行った。船は沿岸に近いと捕まえられるので陸の見えない遠くを航海し進路を誤ったり、嵐の中を漂流したり、どの船もいろいろの危険にあい苦労したが、幸運にみな南鮮の注文津に着くことが出来た。ここからは日本の迎えの船で内地に送られた。吉州の人々も城津《ソンジン》出てきてこのルートで帰国した (第五次脱出)。
私と一緒にいる六人がいつ船に乗るか、むづかしい問題だった。みな早く親元に帰りたいだろうが、始めのころは闇船の安全性は全く分らない、出発しても戻されるのが多い時もあった。九月半ばに、船頭も団長も最も信頼出来ると思われる船で送り出した。不運なことに船は台風に遭遇し舵《かじ》がこはれ、帆柱は倒れ、日本海を七日間漂流して命からがら注文津に着いたという。早い船は三日位で着いている。
二十年九月、治安が落ち着くとすぐ、人民委員会から指名された工場の技術者は集められた席で、朝鮮独立と工場の再開に協力して欲しい旨の要請を受けた。私も指名にはいっていた。生活と安全を保証する、と云う。形の上では日本人の自発的協力参加だが、言葉のはしには断れば其の逆になるということだった。
この百人余りの者は闇船での帰国を許されず、二十一年十月に出た最終の船を見送らねばならなかった。
ソ連軍が来てからは社宅やその他の建物がロスケに取り上げられるので、一軒の家にも合宿の部屋にも何所帯もが入らねばならなくなった。私たち十人が初めて病院社宅から引越したのは、六畳二、四畳半一間の家で四人家族の方と一緒だった。
ここには初め風呂がなかった。何日もたたぬのに私はカイセンにかかった。往診先で感染したのだと云うと伝染病予防の必要を皆に説明するのにいささか説得力があったかも知れない。回帰熱《=急性伝染病》、発疹チフスでなくてよかったが、この媒介color=CC9900]《ばいかい》[/color]をする蚤《のみ》、しらみ退治には入浴と洗濯が一番の予防法だといって、この二つを皆に励行してもらった。
移動禁止令が解けぬまま二十年は冬に入った。零下二十度以下になる土地なので、どうなることかと色々に心配していたが、社宅も、合宿も建物はしっかり出来ており、上水道は安全だったし、電気は豊富で十分な余裕があり無料で使うことが出来て暖房、炊事、洗濯、入浴に不自由することはなかった。
城津《ソンジン》は、夏はアメーバー赤痢と細菌性赤痢、腸チフス、マラリア、冬は発疹チフス、回帰熱、天然痘等の伝染病が多い土地なので、その流行が非常に心配だったが、皆の衛生知識とこの施設のおかげで、よその収容所のような蔓延《まんえん》はなかった。天然痘と発疹チフスとが一、二あり、犠牲者もでたがすぐに隔離できて後は続かずに済んだ。厳寒の冬は電気暖房のおかげで火災はなく、ガス中毒も凍死者もなく、肺炎も極めて少なくて無事に春を迎えられたのは奇跡的ともいえる幸いだった。
五千人余りの抑留者の生活はまちまちだったが詳しくは知らない。初めの混乱期がすぎると、世話会中心の共同生活になり、着のみ着の儘だった人たちも何とか衣食に困らないだけの物は揃ってきた。応召家族の所も頑張り抜いた。働ける者は港の荷役に出たり、工場、商店、農場等で働いていたが、なかにはバクチで日を過ごす者がいたし、ロスケの家に食べ物を乞いに来ている姿も見受けた。市場では何でも買うことが出来るので不自由なく暮らしていた者もいる。また、ソ連軍司令官のマダムも、工場長の細君も、たれそれの二号も日本人だとのことを耳にした。真偽は分からぬが正規の夫婦はあったようだ。
抑留生活と脱出終り
敗戦の後の双浦地区には工場の従業員と家族のほか、北から下りてきた人を併せて日本人は五千人あまりいた。この中心は工場長だがロスケが来るとすぐ、工場長と幹部とはソ連軍に連れていかれた。技師長が拉致《らち》されなかったので、この人を中心に工場の有志の若手社員が尽力に立ち上がってくれた。
危険な道を京城《ソウル》本社との連絡に三十八度線を往復もした。ソ連軍、朝鮮人との折衝《せっしょう》には、大変な苦労を重ね、やがて日本人世話会として活動するようになった。初めは北からの避難者の受け入れ、死亡者の埋葬、住居、食糧の配分等から無職者の帰国促進、後には他地区との連絡、闇船の計画交渉、編成、運行等大変な仕事をやり遂げた。そのおかげで混乱期を過ぎた後には殆ど犠牲者を出すことなしに、五千余りの者は帰国することができた。大きな功績は知る人のみぞ知る。感謝の極みである。
八月九日ソ連軍が満州と朝鮮に攻め込んで来たので、家族の疎開が始まって一部が移動している時敗戦になり、この人達は双浦にすぐ引き返してきた。十五日以後も鉄道は動いていたので、北から朝鮮人が大勢乗り込んで南下していた。双浦から日本人は極く一部の者がこれに乗って行き、京城《ソウル》に着いたのもあるが、途中北鮮で抑留され収容所で冬を過ごしたのもいる。(第一次脱出)
殆《ほとん》ど全員は双浦を離れることをせずにいたが、一時は全員南下する話があり、その時には入院患者の動かれない者をどうしようかと思案したこともあった。もしここを出ていく事になっていたらもっともっと悲惨な事になったろう。北鮮の地区によっては、「敗戦後すぐロスケが来る前に三十八度線から南に逃げておくべくだった」と、責任者を非難する記事を読んだが、双浦では動かなかったのが最善だったと信じている。
ソ連軍の乱暴狼藉が少なくなり、かなり治安が落ち着いてきた十月、工場の技術系某課長家族とその親戚の一団が船を仕立てて脱出に成功した。一行は無事南鮮に着き、京城《 ソウル》に出て二十年秋には日本へ帰っている。夜間極秘の出発で、病院の同僚もいるが(コレニツイテハ別ニ記スコトニナロウ)私は全く知らなかった。朝鮮側でも不意打ちだったのだろう、以後は警戒が厳しくなりこれに習って企てられたのは全て発見され、失敗に終わった(第二次脱出)。
年を越して暖かくなってからまだ移動禁止令は解けてなかったが、清津《チョンジン》、咸興《ハムフン》、元山《ウォンサン》等各地の日本人世帯会との連絡が取れるようになった。交渉はなかなか進まなかったが二十一年六月にようやく南への移動が黙認された。
鉄道貨車で三十八度線近くまで乗って行きあとは徒歩で山間を通り、川を渡って三十八度線を抜け、京城《ソウル》にたどり着いた。この一行は働き手のいない家族、病弱者、老人達が主な四百人の第一陣だったが、そのごすぐ鉄道貨車による南下はこの一回だけで中止された。元山《ウォンサン》にコレラが出たためと聞いた(第三次脱出)。
六月下旬からは海路で直接南鮮に行くことになった。所謂《いわゆる》、闇船で機会船や帆船で希望者の順に九百人が双浦の港を出発して行ったが、三十八度線を越える前に捕まえられて、双浦にもどされた船が多かった。家財道具を処分して出て行ったのでもどされたときは僅かな身の回りの物しかなく、次の出発まではそれまで以上の苦労だった。この闇船もまた中止になった(第四次脱出)。
世話会は計画を立て直して、南下は九月初めから再開された。今度は順調な軌道に乗って次々に双浦の港から出て行った。船は沿岸に近いと捕まえられるので陸の見えない遠くを航海し進路を誤ったり、嵐の中を漂流したり、どの船もいろいろの危険にあい苦労したが、幸運にみな南鮮の注文津に着くことが出来た。ここからは日本の迎えの船で内地に送られた。吉州の人々も城津《ソンジン》出てきてこのルートで帰国した (第五次脱出)。
私と一緒にいる六人がいつ船に乗るか、むづかしい問題だった。みな早く親元に帰りたいだろうが、始めのころは闇船の安全性は全く分らない、出発しても戻されるのが多い時もあった。九月半ばに、船頭も団長も最も信頼出来ると思われる船で送り出した。不運なことに船は台風に遭遇し舵《かじ》がこはれ、帆柱は倒れ、日本海を七日間漂流して命からがら注文津に着いたという。早い船は三日位で着いている。
二十年九月、治安が落ち着くとすぐ、人民委員会から指名された工場の技術者は集められた席で、朝鮮独立と工場の再開に協力して欲しい旨の要請を受けた。私も指名にはいっていた。生活と安全を保証する、と云う。形の上では日本人の自発的協力参加だが、言葉のはしには断れば其の逆になるということだった。
この百人余りの者は闇船での帰国を許されず、二十一年十月に出た最終の船を見送らねばならなかった。
ソ連軍が来てからは社宅やその他の建物がロスケに取り上げられるので、一軒の家にも合宿の部屋にも何所帯もが入らねばならなくなった。私たち十人が初めて病院社宅から引越したのは、六畳二、四畳半一間の家で四人家族の方と一緒だった。
ここには初め風呂がなかった。何日もたたぬのに私はカイセンにかかった。往診先で感染したのだと云うと伝染病予防の必要を皆に説明するのにいささか説得力があったかも知れない。回帰熱《=急性伝染病》、発疹チフスでなくてよかったが、この媒介color=CC9900]《ばいかい》[/color]をする蚤《のみ》、しらみ退治には入浴と洗濯が一番の予防法だといって、この二つを皆に励行してもらった。
移動禁止令が解けぬまま二十年は冬に入った。零下二十度以下になる土地なので、どうなることかと色々に心配していたが、社宅も、合宿も建物はしっかり出来ており、上水道は安全だったし、電気は豊富で十分な余裕があり無料で使うことが出来て暖房、炊事、洗濯、入浴に不自由することはなかった。
城津《ソンジン》は、夏はアメーバー赤痢と細菌性赤痢、腸チフス、マラリア、冬は発疹チフス、回帰熱、天然痘等の伝染病が多い土地なので、その流行が非常に心配だったが、皆の衛生知識とこの施設のおかげで、よその収容所のような蔓延《まんえん》はなかった。天然痘と発疹チフスとが一、二あり、犠牲者もでたがすぐに隔離できて後は続かずに済んだ。厳寒の冬は電気暖房のおかげで火災はなく、ガス中毒も凍死者もなく、肺炎も極めて少なくて無事に春を迎えられたのは奇跡的ともいえる幸いだった。
五千人余りの抑留者の生活はまちまちだったが詳しくは知らない。初めの混乱期がすぎると、世話会中心の共同生活になり、着のみ着の儘だった人たちも何とか衣食に困らないだけの物は揃ってきた。応召家族の所も頑張り抜いた。働ける者は港の荷役に出たり、工場、商店、農場等で働いていたが、なかにはバクチで日を過ごす者がいたし、ロスケの家に食べ物を乞いに来ている姿も見受けた。市場では何でも買うことが出来るので不自由なく暮らしていた者もいる。また、ソ連軍司令官のマダムも、工場長の細君も、たれそれの二号も日本人だとのことを耳にした。真偽は分からぬが正規の夫婦はあったようだ。
抑留生活と脱出終り
--
編集者 (代理投稿)