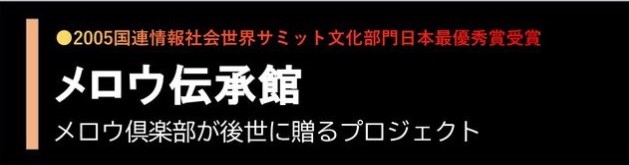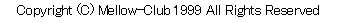チョッパリの邑 (6) 椎野 公雄
投稿ツリー
-
 チョッパリの邑 (1) 椎野 公雄 <一部英訳あり> (編集者, 2007/4/28 7:38)
チョッパリの邑 (1) 椎野 公雄 <一部英訳あり> (編集者, 2007/4/28 7:38)
-
 チョッパリの邑 (2) 椎野 公雄 (編集者, 2007/4/29 7:43)
チョッパリの邑 (2) 椎野 公雄 (編集者, 2007/4/29 7:43)
-
 チョッパリの邑 (3) 椎野 公雄 (編集者, 2007/4/30 6:49)
チョッパリの邑 (3) 椎野 公雄 (編集者, 2007/4/30 6:49)
-
 チョッパリの邑 (4) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/1 7:21)
チョッパリの邑 (4) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/1 7:21)
-
 チョッパリの邑 (5) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/2 8:31)
チョッパリの邑 (5) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/2 8:31)
-
 チョッパリの邑 (6) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/3 7:38)
チョッパリの邑 (6) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/3 7:38)
-
 チョッパリの邑 (7) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/4 8:37)
チョッパリの邑 (7) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/4 8:37)
-
 チョッパリの邑 (8) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/5 7:51)
チョッパリの邑 (8) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/5 7:51)
-
 チョッパリの邑 (9) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/6 8:12)
チョッパリの邑 (9) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/6 8:12)
-
 チョッパリの邑 (10) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/7 7:47)
チョッパリの邑 (10) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/7 7:47)
-
 チョッパリの邑 (11) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/8 7:46)
チョッパリの邑 (11) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/8 7:46)
-
 チョッパリの邑 (12) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/9 5:57)
チョッパリの邑 (12) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/9 5:57)
-
 チョッパリの邑 (13) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/20 10:17)
チョッパリの邑 (13) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/20 10:17)
-
 チョッパリの邑 (14) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/21 9:32)
チョッパリの邑 (14) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/21 9:32)
-
 チョッパリの邑 (15) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/22 8:44)
チョッパリの邑 (15) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/22 8:44)
-
 チョッパリの邑 (16) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/23 8:05)
チョッパリの邑 (16) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/23 8:05)
-
 チョッパリの邑 (17) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/24 7:23)
チョッパリの邑 (17) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/24 7:23)
-
 チョッパリの邑 (18) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/25 7:34)
チョッパリの邑 (18) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/25 7:34)
-
 チョッパリの邑 (19) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/26 6:51)
チョッパリの邑 (19) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/26 6:51)
-
 チョッパリの邑 (20) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/27 7:27)
チョッパリの邑 (20) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/27 7:27)
-
 チョッパリの邑 (21) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/28 7:07)
チョッパリの邑 (21) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/28 7:07)
-
 チョッパリの邑 (22) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/29 7:36)
チョッパリの邑 (22) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/29 7:36)
-
 チョッパリの邑 (23) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/30 7:39)
チョッパリの邑 (23) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/30 7:39)
-
 チョッパリの邑 (24) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/31 15:39)
チョッパリの邑 (24) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/31 15:39)
-
 チョッパリの邑 (25) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/1 7:56)
チョッパリの邑 (25) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/1 7:56)
-
 チョッパリの邑 (26) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/2 6:56)
チョッパリの邑 (26) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/2 6:56)
-
 チョッパリの邑 (27) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/3 7:22)
チョッパリの邑 (27) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/3 7:22)
-
 チョッパリの邑 (28) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/4 7:19)
チョッパリの邑 (28) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/4 7:19)
-
 チョッパリの邑 (29) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/5 8:04)
チョッパリの邑 (29) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/5 8:04)
-
 チョッパリの邑 (30) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/6 7:43)
チョッパリの邑 (30) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/6 7:43)
-
 チョッパリの邑 (31) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/7 7:39)
チョッパリの邑 (31) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/7 7:39)
-
 チョッパリの邑 (32) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/8 8:21)
チョッパリの邑 (32) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/8 8:21)
-
 チョッパリの邑 (33) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/9 7:20)
チョッパリの邑 (33) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/9 7:20)
-
 チョッパリの邑 (34) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/10 8:08)
チョッパリの邑 (34) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/10 8:08)
-
 チョッパリの邑 (35) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/11 7:53)
チョッパリの邑 (35) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/11 7:53)
-
 チョッパリの邑 (36) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/12 7:54)
チョッパリの邑 (36) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/12 7:54)
-
 チョッパリの邑 (37) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/13 7:15)
チョッパリの邑 (37) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/13 7:15)
-
 チョッパリの邑 (38) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/14 7:59)
チョッパリの邑 (38) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/14 7:59)
-
-
 チョッパリの邑 (39) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/15 7:52)
チョッパリの邑 (39) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/15 7:52)
-
 チョッパリの邑 (40) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/16 8:46)
チョッパリの邑 (40) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/16 8:46)
-
 チョッパリの邑 (41・最終回) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/17 7:27)
チョッパリの邑 (41・最終回) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/17 7:27)
-
編集者
 居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
 居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
父の工場のある北中面へ
新義州《シンウィジュ》の宿で一泊、翌日いよいよ目的地である北中面・元峰洞南楊市に向かった。
北中面・南楊市は新義州から多獅島線に乗り約一時間、黄海へ向けて走ったところにあり、昼前には現地に到着した。
正式な地名は、朝鮮平安北道龍川郡北中面元峰洞南楊市とまことに長たらしい。
この地名について、「道」は十五世紀初頭、朝鮮王朝になって出来上がった制度といわれ、当時は京畿《キョンギ》・忠清《チュンチョン》・慶尚《キョンサン》・全羅《チョルナ》・黄海《ファンヘ》・江原《カンウォン》・咸鏡《ハムギョン》・平安《ピョンアン》の八道であったものが十九世紀末期に夫々南・北に分割されて数は倍になった。またこの「八道」(パルド)は朝鮮を意味する愛称となったし、現地でいう「パルド」の呼称は各道の雅号《がごう》として愛用されていた。
各「道」は幾つかの「郡」から構成され、日本内地の「県」は規模では「道」に、行政感覚からすると「郡」に近い。またこの「郡」は幾つかの「邑」や「面」からなり、これが日本の町に相当した。
さらにこの下に多くの「里」や「洞」があって、これらはまた幾つかの村落(マウル)を含んでいた。
また因《ちなみ》みに、朝鮮の南北の総延長距離は約一〇〇〇キロ、古くは「三千里」と数えられて、国土の愛称でもあった。つまり、私たちは「三千里」の果て、「平安・北」パルドの「北中」という町に着いたのである。そして、この町の一角に父が勤めることになった東洋軽金属楊市工場があった。
東洋軽金属株式会社は、太平洋戦争が始まった直後の昭和十六年十二月十二日、既に三井鉱山の子会社であった東洋アルミニウム(株)が日本曹達《ソーダ》系の西鮮化学の事業を統合・継承する形で設立された会社(資本金・四五〇〇万円、会長・林新作、本店・京城府)で、当時朝鮮における三井系最大の金属工業会社であった。
前身の東洋アルミニウム(株)は、昭和十三年十二月十日に三井鉱山と南洋アルミニウム鉱業などとの共同出資によって設立され(資本金・二〇〇〇万円、本店・東京)、アルミナ製造は三井鉱山・三池工場、アルミニウム電解は同社・梅原工場で行うことになっていた。しかし昭和十五年、南洋アルミニウム鉱業のパラオ産ボーキサイト《アルミナ及びアルミニュウムの重要な原料》の増産を見込んで、より大規模な新工場の建設計画を立て、工場は豊富低廉な電力が得られる朝鮮に設置することになったが、この朝鮮進出は当時の軍部の思惑にも応えるものでもあった。
一方の斎館化学(昭和十四年十二月設立、資本金・三〇〇〇万円、社長・中野友礼)は多獅島工場(平安北道龍川郡府羅面元城洞所在、アルミナ、アルミニウム電解工場)を建設中であったが、日曹コンツェルンでは主要企業の経営悪化から傘下企業の大整理を企図しており、軍・朝鮮総督府は東洋アルミニウムに事業の継承を斡旋し、東洋アルミ側もこれを受けて新会社が設立されたという経緯があった。
こうしてできた東洋軽金属であるが、アルミナ製造は三池工場(アルミナ年産四万トン目標)で、またアルミニウム電解の方は多獅島工場ではなく、新たに楊市工場を設け、ここに設備を移すとともに、朝鮮鴨緑江水力発電(株)から電力供給を受けて年産二万トン規模のアルミニウムを生産することを目標とした。しかし工場建設が遅延したため、三池・場市両工場とも操業開始は、この年つまり昭和十八年にずれ込み、場市工場はようやく五月に動き始めたばかりであった。
工場には、日本人関係者約一〇〇人が派遣されたが、家族を入れると三〇〇人以上になったと思われる。すべての日本人が職員として工場の管理・運営にあたり、現地朝鮮人は一部を除き工員として作業に従事させられた。
私達が到着した時には日本人の約九割は既に現地入りし、生産もようやく軌道に乗り始めて、街には活気があふれていた。
新義州《シンウィジュ》の宿で一泊、翌日いよいよ目的地である北中面・元峰洞南楊市に向かった。
北中面・南楊市は新義州から多獅島線に乗り約一時間、黄海へ向けて走ったところにあり、昼前には現地に到着した。
正式な地名は、朝鮮平安北道龍川郡北中面元峰洞南楊市とまことに長たらしい。
この地名について、「道」は十五世紀初頭、朝鮮王朝になって出来上がった制度といわれ、当時は京畿《キョンギ》・忠清《チュンチョン》・慶尚《キョンサン》・全羅《チョルナ》・黄海《ファンヘ》・江原《カンウォン》・咸鏡《ハムギョン》・平安《ピョンアン》の八道であったものが十九世紀末期に夫々南・北に分割されて数は倍になった。またこの「八道」(パルド)は朝鮮を意味する愛称となったし、現地でいう「パルド」の呼称は各道の雅号《がごう》として愛用されていた。
各「道」は幾つかの「郡」から構成され、日本内地の「県」は規模では「道」に、行政感覚からすると「郡」に近い。またこの「郡」は幾つかの「邑」や「面」からなり、これが日本の町に相当した。
さらにこの下に多くの「里」や「洞」があって、これらはまた幾つかの村落(マウル)を含んでいた。
また因《ちなみ》みに、朝鮮の南北の総延長距離は約一〇〇〇キロ、古くは「三千里」と数えられて、国土の愛称でもあった。つまり、私たちは「三千里」の果て、「平安・北」パルドの「北中」という町に着いたのである。そして、この町の一角に父が勤めることになった東洋軽金属楊市工場があった。
東洋軽金属株式会社は、太平洋戦争が始まった直後の昭和十六年十二月十二日、既に三井鉱山の子会社であった東洋アルミニウム(株)が日本曹達《ソーダ》系の西鮮化学の事業を統合・継承する形で設立された会社(資本金・四五〇〇万円、会長・林新作、本店・京城府)で、当時朝鮮における三井系最大の金属工業会社であった。
前身の東洋アルミニウム(株)は、昭和十三年十二月十日に三井鉱山と南洋アルミニウム鉱業などとの共同出資によって設立され(資本金・二〇〇〇万円、本店・東京)、アルミナ製造は三井鉱山・三池工場、アルミニウム電解は同社・梅原工場で行うことになっていた。しかし昭和十五年、南洋アルミニウム鉱業のパラオ産ボーキサイト《アルミナ及びアルミニュウムの重要な原料》の増産を見込んで、より大規模な新工場の建設計画を立て、工場は豊富低廉な電力が得られる朝鮮に設置することになったが、この朝鮮進出は当時の軍部の思惑にも応えるものでもあった。
一方の斎館化学(昭和十四年十二月設立、資本金・三〇〇〇万円、社長・中野友礼)は多獅島工場(平安北道龍川郡府羅面元城洞所在、アルミナ、アルミニウム電解工場)を建設中であったが、日曹コンツェルンでは主要企業の経営悪化から傘下企業の大整理を企図しており、軍・朝鮮総督府は東洋アルミニウムに事業の継承を斡旋し、東洋アルミ側もこれを受けて新会社が設立されたという経緯があった。
こうしてできた東洋軽金属であるが、アルミナ製造は三池工場(アルミナ年産四万トン目標)で、またアルミニウム電解の方は多獅島工場ではなく、新たに楊市工場を設け、ここに設備を移すとともに、朝鮮鴨緑江水力発電(株)から電力供給を受けて年産二万トン規模のアルミニウムを生産することを目標とした。しかし工場建設が遅延したため、三池・場市両工場とも操業開始は、この年つまり昭和十八年にずれ込み、場市工場はようやく五月に動き始めたばかりであった。
工場には、日本人関係者約一〇〇人が派遣されたが、家族を入れると三〇〇人以上になったと思われる。すべての日本人が職員として工場の管理・運営にあたり、現地朝鮮人は一部を除き工員として作業に従事させられた。
私達が到着した時には日本人の約九割は既に現地入りし、生産もようやく軌道に乗り始めて、街には活気があふれていた。
--
編集者 (代理投稿)