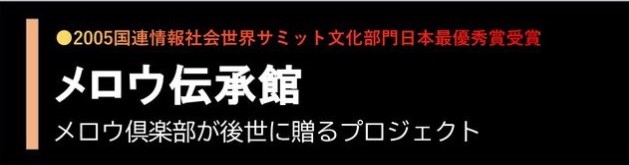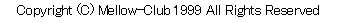チョッパリの邑 (35) 椎野 公雄
投稿ツリー
-
 チョッパリの邑 (1) 椎野 公雄 <一部英訳あり> (編集者, 2007/4/28 7:38)
チョッパリの邑 (1) 椎野 公雄 <一部英訳あり> (編集者, 2007/4/28 7:38)
-
 チョッパリの邑 (2) 椎野 公雄 (編集者, 2007/4/29 7:43)
チョッパリの邑 (2) 椎野 公雄 (編集者, 2007/4/29 7:43)
-
 チョッパリの邑 (3) 椎野 公雄 (編集者, 2007/4/30 6:49)
チョッパリの邑 (3) 椎野 公雄 (編集者, 2007/4/30 6:49)
-
 チョッパリの邑 (4) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/1 7:21)
チョッパリの邑 (4) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/1 7:21)
-
 チョッパリの邑 (5) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/2 8:31)
チョッパリの邑 (5) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/2 8:31)
-
 チョッパリの邑 (6) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/3 7:38)
チョッパリの邑 (6) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/3 7:38)
-
 チョッパリの邑 (7) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/4 8:37)
チョッパリの邑 (7) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/4 8:37)
-
 チョッパリの邑 (8) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/5 7:51)
チョッパリの邑 (8) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/5 7:51)
-
 チョッパリの邑 (9) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/6 8:12)
チョッパリの邑 (9) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/6 8:12)
-
 チョッパリの邑 (10) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/7 7:47)
チョッパリの邑 (10) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/7 7:47)
-
 チョッパリの邑 (11) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/8 7:46)
チョッパリの邑 (11) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/8 7:46)
-
 チョッパリの邑 (12) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/9 5:57)
チョッパリの邑 (12) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/9 5:57)
-
 チョッパリの邑 (13) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/20 10:17)
チョッパリの邑 (13) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/20 10:17)
-
 チョッパリの邑 (14) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/21 9:32)
チョッパリの邑 (14) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/21 9:32)
-
 チョッパリの邑 (15) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/22 8:44)
チョッパリの邑 (15) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/22 8:44)
-
 チョッパリの邑 (16) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/23 8:05)
チョッパリの邑 (16) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/23 8:05)
-
 チョッパリの邑 (17) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/24 7:23)
チョッパリの邑 (17) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/24 7:23)
-
 チョッパリの邑 (18) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/25 7:34)
チョッパリの邑 (18) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/25 7:34)
-
 チョッパリの邑 (19) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/26 6:51)
チョッパリの邑 (19) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/26 6:51)
-
 チョッパリの邑 (20) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/27 7:27)
チョッパリの邑 (20) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/27 7:27)
-
 チョッパリの邑 (21) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/28 7:07)
チョッパリの邑 (21) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/28 7:07)
-
 チョッパリの邑 (22) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/29 7:36)
チョッパリの邑 (22) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/29 7:36)
-
 チョッパリの邑 (23) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/30 7:39)
チョッパリの邑 (23) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/30 7:39)
-
 チョッパリの邑 (24) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/31 15:39)
チョッパリの邑 (24) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/31 15:39)
-
 チョッパリの邑 (25) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/1 7:56)
チョッパリの邑 (25) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/1 7:56)
-
 チョッパリの邑 (26) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/2 6:56)
チョッパリの邑 (26) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/2 6:56)
-
 チョッパリの邑 (27) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/3 7:22)
チョッパリの邑 (27) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/3 7:22)
-
 チョッパリの邑 (28) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/4 7:19)
チョッパリの邑 (28) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/4 7:19)
-
 チョッパリの邑 (29) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/5 8:04)
チョッパリの邑 (29) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/5 8:04)
-
 チョッパリの邑 (30) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/6 7:43)
チョッパリの邑 (30) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/6 7:43)
-
 チョッパリの邑 (31) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/7 7:39)
チョッパリの邑 (31) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/7 7:39)
-
 チョッパリの邑 (32) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/8 8:21)
チョッパリの邑 (32) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/8 8:21)
-
 チョッパリの邑 (33) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/9 7:20)
チョッパリの邑 (33) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/9 7:20)
-
 チョッパリの邑 (34) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/10 8:08)
チョッパリの邑 (34) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/10 8:08)
-
 チョッパリの邑 (35) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/11 7:53)
チョッパリの邑 (35) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/11 7:53)
-
 チョッパリの邑 (36) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/12 7:54)
チョッパリの邑 (36) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/12 7:54)
-
 チョッパリの邑 (37) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/13 7:15)
チョッパリの邑 (37) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/13 7:15)
-
 チョッパリの邑 (38) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/14 7:59)
チョッパリの邑 (38) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/14 7:59)
-
-
 チョッパリの邑 (39) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/15 7:52)
チョッパリの邑 (39) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/15 7:52)
-
 チョッパリの邑 (40) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/16 8:46)
チョッパリの邑 (40) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/16 8:46)
-
 チョッパリの邑 (41・最終回) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/17 7:27)
チョッパリの邑 (41・最終回) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/17 7:27)
-
編集者
 居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
 居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
京城(ソウル)近郊の収容所生活
船着場のはずれ、少し広いところに着くと、点呼のあと五台の大型トラックに乗せられた。
頑丈なアメリカ製のトラックは荷台も高く、弱った身体には登るのも一苦労だ。先ず私が登り、弟を引き上げる。姉、母を下から押し上げた父が最後に登り、他の家族も順次荷台に落ち着くと、トラックは砂煙をあげて一路ソウル近郊の難民収容所へ向かって走りだした。
暫《しばら》くして大きな川(漢江)を渡ると賑やかな京城《ソウル》の街中に入るが、車は止まる様子もなく更に北へ向かって走る。仁川から一時間以上走ったろうか、学校かと思われるところで降ろされた。「ここが収容所だ」と言われてよく見ると、米軍施設の一部らしく仮設の小屋が何棟かあるほか、屋根だけの大きなテントが10個ほど張られている。収容者は殆どが日本人、数にして二〇〇〇人はいたのではなかろうか。
南朝鮮では終戦直後からアメリカ軍政庁によって日本人の「引き揚げ」が実行され、この時期には残留禁止令も出てもう殆《ほとん》ど残っていなかったから、いるのは北もしくは満州からの帰還途中の人間だけだったろう。しかも我々のような立場の人間は南の全地域で未だ数万人以上いたと思われ、京城・釜山《プサン》など10数箇所にここと同じような施設が作られていたが、我々の収容所はそのうちの一つ、京城北部の議政府《ウィジョンプ》という町に設《もう》けられたものであった。
この「議政府」という土地の名前は、十九世紀末、大韓帝国が成立するころ最高行政官庁として大きな権限・機能を持っていた行政府名で、当時この地に置かれたことに由来していたといわれる。収容所自体は少なくとも街中から離れていたので周《まわ》りには何もない静かな場所であるが、二〇〇〇人もの収容者でごった返す所内は、ここまでの旅で疲れ果て、多数の病人までいるにしては賑やかであった。
車から降ろされた私達は一列に並ばされ、先ずDDT散布の洗礼を受ける。
米兵が背負った散布機のノズルから勢いよく吹き出される白いDDTの粉は、私達の頭から足先までを真っ白にし、恰《あたか》も油に放り込まれる前の天ぷらの「具」のよう。その恰好がいかにもおかしくてお互いに顔を見合わせて笑ってしまう。
DDTの洗礼が終わると、各自に毛布と乾パン・缶詰などの食料が入った袋を一つずつ渡された。お腹も空いてるし早く食べたいが、とにかく宿営《軍隊が宿泊するところ》に落ち着くまではお預けである。
先着組は仮設の小屋をあてがわれているが、新入りは取りあえず下にアンペラ(茣蓙)の敷かれたテント小屋に入れられ、船と同じように家族単位で一定のスペースを確保すると、ようやく落ち着くことができた。未だ身体には白い粉が付いているが、頓着《とんちゃく=気にする》している暇はない。早速渡された袋から乾パンを取り出すと一斉に口に放り込む。暫く確なものをロにしていないので美味《おいし》いことこの上ない。瞬《またた》く間に半分を食べてしまった。
お腹も膨《ふく》れたので、疲れた身体を毛布に包みゴロリと横になると、そのまま眠り込んでしまう。
どのくらい眠ったろうか。父の声で目を覚ますと夕方近かったから四~五時間は寝たと思われる。下は固いが船の中と違って身体は揺れないし、もう警備艇を心配することもないから本当にグッスリであった。
夜食はトウモロコシを湯がいたものと、丸麦のお粥《かゆ》。各家庭毎に持参の器を持って受け取りにいく。おかずは先ほど配られた鯨肉《げいにく》の缶詰、粗末ではあるが久しぶりに汁気のある食事にありつけた。
この収容所に入った頃は、北と違って未だ朝晩が少し冷えるな」という程度で、野宿同然とはいえ寒さも気にならなかったが、何日か経って九月も下旬に入る頃にはさすがに厳しくなってくる。
身の安全は確保され、不満足とはいえ食事も一日二回は与えられるから、餓死《がし》することはないが「何時までこんな状態が続くんだろう」、「少なくとも仮設の小屋に入れて貰いたいね」といった苦情も出始める。そうこうするうちに先着組が少しずつ釜山《プサン》経由で帰還すると、仮設小屋にも空きが出て私達も漸《ようや》くそのあとに入れるようになった。
一歩改善された収容所生活ではあるが、食事は毎日同じようなものしか出ず、特に主食のトウモロコシや丸麦は、身体が弱っているのだろうか、食べると消化されず殆どそのまま排泄《はいせつ》される。つまり毎日下痢ということは、食べたものが身に付いていないことの証で、日を追って体力が低下していくのがわかる。これまで脱走者として張り詰めていた気が急に緩《ゆる》んでいるのも事実だし、このままでは病人が急増していくことも懸念《けねん》された。
事実、収容者の中では一週間に一人は死人も出て、その度に朝鮮式の葬儀が行われ、「泣き女」によって先導される行列が、銅鑼《どら》鉦《かね》とともに近所の埋葬墓地まで続くのが習わしであった。
「それにしても、私達は何時日本に帰れるんだろうか」
十月になっても帰還の日程など何の音沙汰もなく、毎日同じような収容所生活が続いてうんざりしていた或る日、「十日過ぎに仁川から日本の引揚船で正式に帰還することになった。行き先は佐世保だそうだ」との報告が入る。とにかく日本であれば何処でもいいから早く帰りたい。
そしてその日が十月十四日と決まり、待ちに待った出発の朝がやってきた。
船着場のはずれ、少し広いところに着くと、点呼のあと五台の大型トラックに乗せられた。
頑丈なアメリカ製のトラックは荷台も高く、弱った身体には登るのも一苦労だ。先ず私が登り、弟を引き上げる。姉、母を下から押し上げた父が最後に登り、他の家族も順次荷台に落ち着くと、トラックは砂煙をあげて一路ソウル近郊の難民収容所へ向かって走りだした。
暫《しばら》くして大きな川(漢江)を渡ると賑やかな京城《ソウル》の街中に入るが、車は止まる様子もなく更に北へ向かって走る。仁川から一時間以上走ったろうか、学校かと思われるところで降ろされた。「ここが収容所だ」と言われてよく見ると、米軍施設の一部らしく仮設の小屋が何棟かあるほか、屋根だけの大きなテントが10個ほど張られている。収容者は殆どが日本人、数にして二〇〇〇人はいたのではなかろうか。
南朝鮮では終戦直後からアメリカ軍政庁によって日本人の「引き揚げ」が実行され、この時期には残留禁止令も出てもう殆《ほとん》ど残っていなかったから、いるのは北もしくは満州からの帰還途中の人間だけだったろう。しかも我々のような立場の人間は南の全地域で未だ数万人以上いたと思われ、京城・釜山《プサン》など10数箇所にここと同じような施設が作られていたが、我々の収容所はそのうちの一つ、京城北部の議政府《ウィジョンプ》という町に設《もう》けられたものであった。
この「議政府」という土地の名前は、十九世紀末、大韓帝国が成立するころ最高行政官庁として大きな権限・機能を持っていた行政府名で、当時この地に置かれたことに由来していたといわれる。収容所自体は少なくとも街中から離れていたので周《まわ》りには何もない静かな場所であるが、二〇〇〇人もの収容者でごった返す所内は、ここまでの旅で疲れ果て、多数の病人までいるにしては賑やかであった。
車から降ろされた私達は一列に並ばされ、先ずDDT散布の洗礼を受ける。
米兵が背負った散布機のノズルから勢いよく吹き出される白いDDTの粉は、私達の頭から足先までを真っ白にし、恰《あたか》も油に放り込まれる前の天ぷらの「具」のよう。その恰好がいかにもおかしくてお互いに顔を見合わせて笑ってしまう。
DDTの洗礼が終わると、各自に毛布と乾パン・缶詰などの食料が入った袋を一つずつ渡された。お腹も空いてるし早く食べたいが、とにかく宿営《軍隊が宿泊するところ》に落ち着くまではお預けである。
先着組は仮設の小屋をあてがわれているが、新入りは取りあえず下にアンペラ(茣蓙)の敷かれたテント小屋に入れられ、船と同じように家族単位で一定のスペースを確保すると、ようやく落ち着くことができた。未だ身体には白い粉が付いているが、頓着《とんちゃく=気にする》している暇はない。早速渡された袋から乾パンを取り出すと一斉に口に放り込む。暫く確なものをロにしていないので美味《おいし》いことこの上ない。瞬《またた》く間に半分を食べてしまった。
お腹も膨《ふく》れたので、疲れた身体を毛布に包みゴロリと横になると、そのまま眠り込んでしまう。
どのくらい眠ったろうか。父の声で目を覚ますと夕方近かったから四~五時間は寝たと思われる。下は固いが船の中と違って身体は揺れないし、もう警備艇を心配することもないから本当にグッスリであった。
夜食はトウモロコシを湯がいたものと、丸麦のお粥《かゆ》。各家庭毎に持参の器を持って受け取りにいく。おかずは先ほど配られた鯨肉《げいにく》の缶詰、粗末ではあるが久しぶりに汁気のある食事にありつけた。
この収容所に入った頃は、北と違って未だ朝晩が少し冷えるな」という程度で、野宿同然とはいえ寒さも気にならなかったが、何日か経って九月も下旬に入る頃にはさすがに厳しくなってくる。
身の安全は確保され、不満足とはいえ食事も一日二回は与えられるから、餓死《がし》することはないが「何時までこんな状態が続くんだろう」、「少なくとも仮設の小屋に入れて貰いたいね」といった苦情も出始める。そうこうするうちに先着組が少しずつ釜山《プサン》経由で帰還すると、仮設小屋にも空きが出て私達も漸《ようや》くそのあとに入れるようになった。
一歩改善された収容所生活ではあるが、食事は毎日同じようなものしか出ず、特に主食のトウモロコシや丸麦は、身体が弱っているのだろうか、食べると消化されず殆どそのまま排泄《はいせつ》される。つまり毎日下痢ということは、食べたものが身に付いていないことの証で、日を追って体力が低下していくのがわかる。これまで脱走者として張り詰めていた気が急に緩《ゆる》んでいるのも事実だし、このままでは病人が急増していくことも懸念《けねん》された。
事実、収容者の中では一週間に一人は死人も出て、その度に朝鮮式の葬儀が行われ、「泣き女」によって先導される行列が、銅鑼《どら》鉦《かね》とともに近所の埋葬墓地まで続くのが習わしであった。
「それにしても、私達は何時日本に帰れるんだろうか」
十月になっても帰還の日程など何の音沙汰もなく、毎日同じような収容所生活が続いてうんざりしていた或る日、「十日過ぎに仁川から日本の引揚船で正式に帰還することになった。行き先は佐世保だそうだ」との報告が入る。とにかく日本であれば何処でもいいから早く帰りたい。
そしてその日が十月十四日と決まり、待ちに待った出発の朝がやってきた。
--
編集者 (代理投稿)