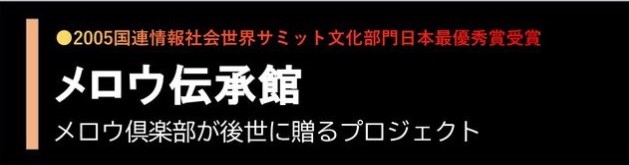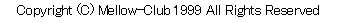チョッパリの邑 (11) 椎野 公雄
投稿ツリー
-
 チョッパリの邑 (1) 椎野 公雄 <一部英訳あり> (編集者, 2007/4/28 7:38)
チョッパリの邑 (1) 椎野 公雄 <一部英訳あり> (編集者, 2007/4/28 7:38)
-
 チョッパリの邑 (2) 椎野 公雄 (編集者, 2007/4/29 7:43)
チョッパリの邑 (2) 椎野 公雄 (編集者, 2007/4/29 7:43)
-
 チョッパリの邑 (3) 椎野 公雄 (編集者, 2007/4/30 6:49)
チョッパリの邑 (3) 椎野 公雄 (編集者, 2007/4/30 6:49)
-
 チョッパリの邑 (4) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/1 7:21)
チョッパリの邑 (4) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/1 7:21)
-
 チョッパリの邑 (5) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/2 8:31)
チョッパリの邑 (5) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/2 8:31)
-
 チョッパリの邑 (6) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/3 7:38)
チョッパリの邑 (6) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/3 7:38)
-
 チョッパリの邑 (7) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/4 8:37)
チョッパリの邑 (7) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/4 8:37)
-
 チョッパリの邑 (8) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/5 7:51)
チョッパリの邑 (8) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/5 7:51)
-
 チョッパリの邑 (9) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/6 8:12)
チョッパリの邑 (9) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/6 8:12)
-
 チョッパリの邑 (10) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/7 7:47)
チョッパリの邑 (10) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/7 7:47)
-
 チョッパリの邑 (11) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/8 7:46)
チョッパリの邑 (11) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/8 7:46)
-
 チョッパリの邑 (12) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/9 5:57)
チョッパリの邑 (12) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/9 5:57)
-
 チョッパリの邑 (13) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/20 10:17)
チョッパリの邑 (13) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/20 10:17)
-
 チョッパリの邑 (14) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/21 9:32)
チョッパリの邑 (14) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/21 9:32)
-
 チョッパリの邑 (15) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/22 8:44)
チョッパリの邑 (15) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/22 8:44)
-
 チョッパリの邑 (16) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/23 8:05)
チョッパリの邑 (16) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/23 8:05)
-
 チョッパリの邑 (17) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/24 7:23)
チョッパリの邑 (17) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/24 7:23)
-
 チョッパリの邑 (18) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/25 7:34)
チョッパリの邑 (18) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/25 7:34)
-
 チョッパリの邑 (19) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/26 6:51)
チョッパリの邑 (19) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/26 6:51)
-
 チョッパリの邑 (20) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/27 7:27)
チョッパリの邑 (20) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/27 7:27)
-
 チョッパリの邑 (21) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/28 7:07)
チョッパリの邑 (21) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/28 7:07)
-
 チョッパリの邑 (22) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/29 7:36)
チョッパリの邑 (22) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/29 7:36)
-
 チョッパリの邑 (23) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/30 7:39)
チョッパリの邑 (23) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/30 7:39)
-
 チョッパリの邑 (24) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/31 15:39)
チョッパリの邑 (24) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/31 15:39)
-
 チョッパリの邑 (25) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/1 7:56)
チョッパリの邑 (25) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/1 7:56)
-
 チョッパリの邑 (26) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/2 6:56)
チョッパリの邑 (26) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/2 6:56)
-
 チョッパリの邑 (27) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/3 7:22)
チョッパリの邑 (27) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/3 7:22)
-
 チョッパリの邑 (28) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/4 7:19)
チョッパリの邑 (28) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/4 7:19)
-
 チョッパリの邑 (29) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/5 8:04)
チョッパリの邑 (29) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/5 8:04)
-
 チョッパリの邑 (30) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/6 7:43)
チョッパリの邑 (30) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/6 7:43)
-
 チョッパリの邑 (31) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/7 7:39)
チョッパリの邑 (31) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/7 7:39)
-
 チョッパリの邑 (32) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/8 8:21)
チョッパリの邑 (32) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/8 8:21)
-
 チョッパリの邑 (33) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/9 7:20)
チョッパリの邑 (33) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/9 7:20)
-
 チョッパリの邑 (34) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/10 8:08)
チョッパリの邑 (34) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/10 8:08)
-
 チョッパリの邑 (35) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/11 7:53)
チョッパリの邑 (35) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/11 7:53)
-
 チョッパリの邑 (36) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/12 7:54)
チョッパリの邑 (36) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/12 7:54)
-
 チョッパリの邑 (37) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/13 7:15)
チョッパリの邑 (37) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/13 7:15)
-
 チョッパリの邑 (38) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/14 7:59)
チョッパリの邑 (38) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/14 7:59)
-
-
 チョッパリの邑 (39) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/15 7:52)
チョッパリの邑 (39) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/15 7:52)
-
 チョッパリの邑 (40) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/16 8:46)
チョッパリの邑 (40) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/16 8:46)
-
 チョッパリの邑 (41・最終回) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/17 7:27)
チョッパリの邑 (41・最終回) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/17 7:27)
-
編集者
 居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
 居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
11
戦況悪化する中の現地生活
寒い、寒いといいながらも、春の彼岸を過ぎる頃から氷も解け始め、日差しも和らいで、防寒着も要らなくなってきた。
この昭和十九年の春、私たちがこうして比較的安穏《あんのん》な生活を送っている頃、太平洋地域の戦争はますます激しさを増し、日本軍はマーシャル諸島《北西太平洋》、パラオ諸島《北西太平洋、ミクロネシアのカロリン諸島の西端》で相次いで敗北、連合艦隊司令部はフィリピン・ミンダナオ島に移動を余儀なくされ、当時絶対防衛圈の中でも特に重要視されていたサイパン、テニアンなどを含むマリアナ諸島《北西太平洋北部に位置する》すらアメリカ軍の射程距離に入るなど、戦況はますます不利な状況にあった。
一方、大陸では重慶《じゅうけい=中国四川省》の蒋介石《しょうかいせき》・国民政府軍、毛沢東《もうたくとう》・共産軍を相手にした戦いが続けられていた。そして、この年の一月には、アメリカ軍記の台湾空襲に使われたといわれる数箇所の飛行場の破壊、また鉄道を中心とする大陸横断路を追って満州から南方・シンガポールに至る長大な補給路確保を目的とした「大陸打通作戦」と称する前代未聞の大作戦が決行され、このため五〇万の大軍が華北から華南へ動かされたとのことである。
中国大陸では、こうして拡大した戦線の維持に難渋しながらも、苦戦が続く南方今太平洋地区に比べれば未だ総体的に統治能力は高いと信じられていたし、少なくとも鴨緑江《おうりょくこう》のこちら朝鮮には大陸の様子はあまり伝わらず、朝鮮国内にも不穏な動きはまったく見えなかった。
しかし、戦争が「不利」に傾くなか、ここ朝鮮でも物資不足は顕著《けんちょ》になり、食糧は米を除き自給自足が奨励されて、各家庭の空き地は野菜・穀物の栽培が盛んになっていった。
キムチを漬けてくれた朴さんが、「そろそろ野菜を植える準備にかかりましょう」と、鍬《くわ》やスコップを持ってきて、未だ下の方の固い裏庭の土を掘り起こして畑を作ってくれる。
勿論、私たちも手伝って2アールほどの畑ができた。
そこに、青菜、隠元豆、キャベツなどの春野菜を植え、少し時間をおいて茄子《なす》、胡瓜《きゅうり》、トマトに馬鈴薯《ばれいしょ》やサツマイモ、カボチャのほか、朝鮮特有のトウモロコシ、黍《きび》、ニンニク、唐辛子などを順次植えていった。
肥料は自家製、地味も豊かなのか、早いものは夏を持たず食べられたし、トマトや胡瓜はオヤツとして毎日のように、もいではそのままかぶりついたが新鮮で美味しかった。
こうした白家穀培で殆どの野菜類、またトウモロコシなどの穀物は、食料不足の助けになったが、朴さんが「これは少し難しいよ」といっていたマクワ瓜も、彼の指導で見事な出来ばえ、手に入り難い蜜柑《みかん》や挑に代わる「果物」として有難い産物であった。
春・夏野菜が終わると、白菜、葱《ねぎ》が畑の主役になるが、霜が降り始める頃にはキムチの材料になる見事な白菜が育った。
朝鮮にきて、初めはその臭いに閉口したニンニクも、特が経つにつれて「美味いもの」に変わり、特に冬場はそのまま焼いて味噌を付け、オヤツ代わりに一玉をペロリと平らげるようになった。今でいうバクダン、何とも乙なオヤツではあった。
二学期も終わりに近づいた頃、太平洋地域の戦闘は更に厳しくなり、サイパン《北西太平洋ミクロネシアのマリアナ諸島南部の島》は七月七日に陥落して東条内閣は総辞職(七月十八日)、四日後に小磯内閣が成立して、太平洋戦争勃発《ぼっぱつ=とつぜんにおこる》以来絶大な権威を誇った開戦内閣は終わりを迎えたのである。
そんな或る日、父の串木野時代の知り合いの梅原さんが軍服姿で突然訪ねてこられた。
「久しぶりだけど、どうしたの?」父が問いかけると、梅原さんは「今度、中支に派遣されることになり、今その途上ですが一日休暇を貰ってご挨拶に上がりました」
「わざわざ来てくれて嬉しいけど、大陸も大変らしいから、くれぐれも身体を大事にね」。
そして「これをお守りに特っていって」と、父が日ごろ大事にして、時には鞘《さや》を払ってタンポで白い粉をつけたりしていた幾つかの刀の中から、白鞘のI振りを差し出すと、梅原さんも「こんな立派なものを頂いて恐縮です。早速現地で軍刀に仕立てます」
しばらく現在の戦況や内地の様子などを話し込むと、梅原さんは、母の「食事でもしていって下さい」との誘いも断って
「では行って参ります。皆さんもお元気で」と、直立不動で敬礼して帰っていかれた。
軍服の様子から、梅原さんが低い地位でないことは判るが、もともと職業軍人ではなかった筈だし、何故そんな人が戦地に赴《おもむ》くのか、いよいよそんな時がきたのかと不安な気がしてならなかった。
事実、そんな出会いがあった少し前、日本内地ではアメリカ軍のB-29による初めての空爆(六月十六日)があり、北九州では大きな被害が出ていた。しかも、この空襲で使われたB-29は中国・成都から飛び立ったものと伝えられ、中国大陸にもアメリカ軍の力が及び始めていたのである。
その後も成都から出撃するB-29の内地爆撃は続き、秋口からはアメリカ軍の手に落ちたサイパン・テニアンなどマリアナ諸島からの空爆も頻繁《ひんぱん 》に行われるようになったことから、ここ朝鮮・南楊市《ナムヤンジュ》でも防空壕の設置が義務付けられたり、防空演習が行われるようになったし、学校でも体育授業の中で竹槍訓練や短棒投げなどをやらされるようになって、それまでは比較的遠くにあった戦争も身近に迫ってきたことを感じないわけにはいかなかった。
そうはいっても、食料や日用品の配給に制限が加えられたりする他は、空襲などの直接的な被害は何もなかったので、未だまだ日常生活は穏やかなもの。夏の或る日曜日など父に連れられて鴨緑江河口の多獅島まで築(ヤナ)遊びに出かけ、グチや蟹などたらふく食べることもできたし、或る時は、これも父が何処かから仕人れてきた「かすみ網」を持って雀やツグミを獲りに遠出することもあった。
勿論、放課後の遊びも今までどおり、チェギ、トッキ、モッパイ、竹馬など、畑でできたトウキビをかじりながら日が暮れるまで遊ぶ毎日。殊にモッパイは腕もあがって、標的の野ウサギ、野鳩、カササギを追いかけては野山を駆け巡っていた。


戦況悪化する中の現地生活
寒い、寒いといいながらも、春の彼岸を過ぎる頃から氷も解け始め、日差しも和らいで、防寒着も要らなくなってきた。
この昭和十九年の春、私たちがこうして比較的安穏《あんのん》な生活を送っている頃、太平洋地域の戦争はますます激しさを増し、日本軍はマーシャル諸島《北西太平洋》、パラオ諸島《北西太平洋、ミクロネシアのカロリン諸島の西端》で相次いで敗北、連合艦隊司令部はフィリピン・ミンダナオ島に移動を余儀なくされ、当時絶対防衛圈の中でも特に重要視されていたサイパン、テニアンなどを含むマリアナ諸島《北西太平洋北部に位置する》すらアメリカ軍の射程距離に入るなど、戦況はますます不利な状況にあった。
一方、大陸では重慶《じゅうけい=中国四川省》の蒋介石《しょうかいせき》・国民政府軍、毛沢東《もうたくとう》・共産軍を相手にした戦いが続けられていた。そして、この年の一月には、アメリカ軍記の台湾空襲に使われたといわれる数箇所の飛行場の破壊、また鉄道を中心とする大陸横断路を追って満州から南方・シンガポールに至る長大な補給路確保を目的とした「大陸打通作戦」と称する前代未聞の大作戦が決行され、このため五〇万の大軍が華北から華南へ動かされたとのことである。
中国大陸では、こうして拡大した戦線の維持に難渋しながらも、苦戦が続く南方今太平洋地区に比べれば未だ総体的に統治能力は高いと信じられていたし、少なくとも鴨緑江《おうりょくこう》のこちら朝鮮には大陸の様子はあまり伝わらず、朝鮮国内にも不穏な動きはまったく見えなかった。
しかし、戦争が「不利」に傾くなか、ここ朝鮮でも物資不足は顕著《けんちょ》になり、食糧は米を除き自給自足が奨励されて、各家庭の空き地は野菜・穀物の栽培が盛んになっていった。
キムチを漬けてくれた朴さんが、「そろそろ野菜を植える準備にかかりましょう」と、鍬《くわ》やスコップを持ってきて、未だ下の方の固い裏庭の土を掘り起こして畑を作ってくれる。
勿論、私たちも手伝って2アールほどの畑ができた。
そこに、青菜、隠元豆、キャベツなどの春野菜を植え、少し時間をおいて茄子《なす》、胡瓜《きゅうり》、トマトに馬鈴薯《ばれいしょ》やサツマイモ、カボチャのほか、朝鮮特有のトウモロコシ、黍《きび》、ニンニク、唐辛子などを順次植えていった。
肥料は自家製、地味も豊かなのか、早いものは夏を持たず食べられたし、トマトや胡瓜はオヤツとして毎日のように、もいではそのままかぶりついたが新鮮で美味しかった。
こうした白家穀培で殆どの野菜類、またトウモロコシなどの穀物は、食料不足の助けになったが、朴さんが「これは少し難しいよ」といっていたマクワ瓜も、彼の指導で見事な出来ばえ、手に入り難い蜜柑《みかん》や挑に代わる「果物」として有難い産物であった。
春・夏野菜が終わると、白菜、葱《ねぎ》が畑の主役になるが、霜が降り始める頃にはキムチの材料になる見事な白菜が育った。
朝鮮にきて、初めはその臭いに閉口したニンニクも、特が経つにつれて「美味いもの」に変わり、特に冬場はそのまま焼いて味噌を付け、オヤツ代わりに一玉をペロリと平らげるようになった。今でいうバクダン、何とも乙なオヤツではあった。
二学期も終わりに近づいた頃、太平洋地域の戦闘は更に厳しくなり、サイパン《北西太平洋ミクロネシアのマリアナ諸島南部の島》は七月七日に陥落して東条内閣は総辞職(七月十八日)、四日後に小磯内閣が成立して、太平洋戦争勃発《ぼっぱつ=とつぜんにおこる》以来絶大な権威を誇った開戦内閣は終わりを迎えたのである。
そんな或る日、父の串木野時代の知り合いの梅原さんが軍服姿で突然訪ねてこられた。
「久しぶりだけど、どうしたの?」父が問いかけると、梅原さんは「今度、中支に派遣されることになり、今その途上ですが一日休暇を貰ってご挨拶に上がりました」
「わざわざ来てくれて嬉しいけど、大陸も大変らしいから、くれぐれも身体を大事にね」。
そして「これをお守りに特っていって」と、父が日ごろ大事にして、時には鞘《さや》を払ってタンポで白い粉をつけたりしていた幾つかの刀の中から、白鞘のI振りを差し出すと、梅原さんも「こんな立派なものを頂いて恐縮です。早速現地で軍刀に仕立てます」
しばらく現在の戦況や内地の様子などを話し込むと、梅原さんは、母の「食事でもしていって下さい」との誘いも断って
「では行って参ります。皆さんもお元気で」と、直立不動で敬礼して帰っていかれた。
軍服の様子から、梅原さんが低い地位でないことは判るが、もともと職業軍人ではなかった筈だし、何故そんな人が戦地に赴《おもむ》くのか、いよいよそんな時がきたのかと不安な気がしてならなかった。
事実、そんな出会いがあった少し前、日本内地ではアメリカ軍のB-29による初めての空爆(六月十六日)があり、北九州では大きな被害が出ていた。しかも、この空襲で使われたB-29は中国・成都から飛び立ったものと伝えられ、中国大陸にもアメリカ軍の力が及び始めていたのである。
その後も成都から出撃するB-29の内地爆撃は続き、秋口からはアメリカ軍の手に落ちたサイパン・テニアンなどマリアナ諸島からの空爆も頻繁《ひんぱん 》に行われるようになったことから、ここ朝鮮・南楊市《ナムヤンジュ》でも防空壕の設置が義務付けられたり、防空演習が行われるようになったし、学校でも体育授業の中で竹槍訓練や短棒投げなどをやらされるようになって、それまでは比較的遠くにあった戦争も身近に迫ってきたことを感じないわけにはいかなかった。
そうはいっても、食料や日用品の配給に制限が加えられたりする他は、空襲などの直接的な被害は何もなかったので、未だまだ日常生活は穏やかなもの。夏の或る日曜日など父に連れられて鴨緑江河口の多獅島まで築(ヤナ)遊びに出かけ、グチや蟹などたらふく食べることもできたし、或る時は、これも父が何処かから仕人れてきた「かすみ網」を持って雀やツグミを獲りに遠出することもあった。
勿論、放課後の遊びも今までどおり、チェギ、トッキ、モッパイ、竹馬など、畑でできたトウキビをかじりながら日が暮れるまで遊ぶ毎日。殊にモッパイは腕もあがって、標的の野ウサギ、野鳩、カササギを追いかけては野山を駆け巡っていた。


--
編集者 (代理投稿)