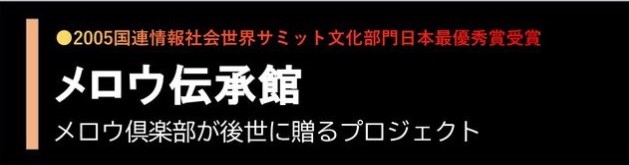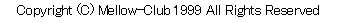チョッパリの邑 (17) 椎野 公雄
投稿ツリー
-
 チョッパリの邑 (1) 椎野 公雄 <一部英訳あり> (編集者, 2007/4/28 7:38)
チョッパリの邑 (1) 椎野 公雄 <一部英訳あり> (編集者, 2007/4/28 7:38)
-
 チョッパリの邑 (2) 椎野 公雄 (編集者, 2007/4/29 7:43)
チョッパリの邑 (2) 椎野 公雄 (編集者, 2007/4/29 7:43)
-
 チョッパリの邑 (3) 椎野 公雄 (編集者, 2007/4/30 6:49)
チョッパリの邑 (3) 椎野 公雄 (編集者, 2007/4/30 6:49)
-
 チョッパリの邑 (4) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/1 7:21)
チョッパリの邑 (4) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/1 7:21)
-
 チョッパリの邑 (5) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/2 8:31)
チョッパリの邑 (5) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/2 8:31)
-
 チョッパリの邑 (6) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/3 7:38)
チョッパリの邑 (6) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/3 7:38)
-
 チョッパリの邑 (7) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/4 8:37)
チョッパリの邑 (7) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/4 8:37)
-
 チョッパリの邑 (8) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/5 7:51)
チョッパリの邑 (8) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/5 7:51)
-
 チョッパリの邑 (9) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/6 8:12)
チョッパリの邑 (9) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/6 8:12)
-
 チョッパリの邑 (10) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/7 7:47)
チョッパリの邑 (10) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/7 7:47)
-
 チョッパリの邑 (11) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/8 7:46)
チョッパリの邑 (11) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/8 7:46)
-
 チョッパリの邑 (12) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/9 5:57)
チョッパリの邑 (12) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/9 5:57)
-
 チョッパリの邑 (13) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/20 10:17)
チョッパリの邑 (13) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/20 10:17)
-
 チョッパリの邑 (14) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/21 9:32)
チョッパリの邑 (14) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/21 9:32)
-
 チョッパリの邑 (15) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/22 8:44)
チョッパリの邑 (15) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/22 8:44)
-
 チョッパリの邑 (16) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/23 8:05)
チョッパリの邑 (16) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/23 8:05)
-
 チョッパリの邑 (17) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/24 7:23)
チョッパリの邑 (17) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/24 7:23)
-
 チョッパリの邑 (18) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/25 7:34)
チョッパリの邑 (18) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/25 7:34)
-
 チョッパリの邑 (19) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/26 6:51)
チョッパリの邑 (19) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/26 6:51)
-
 チョッパリの邑 (20) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/27 7:27)
チョッパリの邑 (20) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/27 7:27)
-
 チョッパリの邑 (21) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/28 7:07)
チョッパリの邑 (21) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/28 7:07)
-
 チョッパリの邑 (22) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/29 7:36)
チョッパリの邑 (22) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/29 7:36)
-
 チョッパリの邑 (23) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/30 7:39)
チョッパリの邑 (23) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/30 7:39)
-
 チョッパリの邑 (24) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/31 15:39)
チョッパリの邑 (24) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/31 15:39)
-
 チョッパリの邑 (25) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/1 7:56)
チョッパリの邑 (25) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/1 7:56)
-
 チョッパリの邑 (26) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/2 6:56)
チョッパリの邑 (26) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/2 6:56)
-
 チョッパリの邑 (27) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/3 7:22)
チョッパリの邑 (27) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/3 7:22)
-
 チョッパリの邑 (28) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/4 7:19)
チョッパリの邑 (28) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/4 7:19)
-
 チョッパリの邑 (29) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/5 8:04)
チョッパリの邑 (29) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/5 8:04)
-
 チョッパリの邑 (30) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/6 7:43)
チョッパリの邑 (30) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/6 7:43)
-
 チョッパリの邑 (31) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/7 7:39)
チョッパリの邑 (31) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/7 7:39)
-
 チョッパリの邑 (32) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/8 8:21)
チョッパリの邑 (32) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/8 8:21)
-
 チョッパリの邑 (33) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/9 7:20)
チョッパリの邑 (33) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/9 7:20)
-
 チョッパリの邑 (34) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/10 8:08)
チョッパリの邑 (34) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/10 8:08)
-
 チョッパリの邑 (35) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/11 7:53)
チョッパリの邑 (35) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/11 7:53)
-
 チョッパリの邑 (36) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/12 7:54)
チョッパリの邑 (36) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/12 7:54)
-
 チョッパリの邑 (37) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/13 7:15)
チョッパリの邑 (37) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/13 7:15)
-
 チョッパリの邑 (38) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/14 7:59)
チョッパリの邑 (38) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/14 7:59)
-
-
 チョッパリの邑 (39) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/15 7:52)
チョッパリの邑 (39) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/15 7:52)
-
 チョッパリの邑 (40) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/16 8:46)
チョッパリの邑 (40) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/16 8:46)
-
 チョッパリの邑 (41・最終回) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/17 7:27)
チョッパリの邑 (41・最終回) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/17 7:27)
-
編集者
 居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
 居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
ブタ小屋生活
小一時間かけて私たちが着いた所は、工場から西南にだいぶ離れた工員社宅の更に南のはずれ。その先はもう田畑しかなく、一キロほど向こうに低い山並みが見えるだけの淋しい田園地帯である。
そこに、荒れ果てた四軒長屋が縦に五棟、横に三列連なった住居群があり、ここが今日から私たちの住家となるという。以前は現地の工員が住んでいたらしいが、いったい彼らはどうしたのかがわからない。尋ねると、工場開設に際して採用した工員をその後減員したため、社宅として不要になったものとのことであった。
各戸とも同じ造りで四畳半が二間、そのうち一間はオンドルで、他に土間の台所がついているだけのみすぼらしい住居。勿論トイレは集合便所で外まで出なければならない。
入り口(玄関)は扉がとれて、筵《むしろ》が垂れ下がっているだけのものが多いし、暫く放置されていたせいかすべてが汚らしい。とにかく、これまでの社宅を「家」とすれば、こちらは「豚小屋」と言ってもいい。
既に抽選でもして決められていたのか、それぞれ割り当てられた家に荷物を持って入居することになった。
当時の家族同伴(平均三~四名)の世帯数は約五〇戸だったが、そこにちょうど五〇名ほどの単身者が一人ずつ割り振られて、同居人となった。
余った家一〇戸ほどには、しばらくして、満州からの引揚者ながら直接帰還できず、ここ南楊市まで漸くたどり着いた女子供だけの家族が、どういう理由か知れなかったけど入ってきた。
割り当てられた家は一列目の西端に近いところ、案の定玄関は扉の代わりに筵がかかっており、中は薄暗くて埃《ほこり》っぽい。
すぐ掃除《そうじ》にかかり、持ってきた荷物を納め込むころ一人の男性がやってきた。年のころは四〇才位か、おとなしい人である。
「栗原と申します。ご厄介になりますが、どうぞよろしくお願いいたします」申し訳なさそうに挨拶され、父母も丁重に答える。「心強いです。こちらこそ、よろしくお願いします」。
私達の家族は五人だから、この栗原さんを入れて六人。家の広さからすると狭苦しくなるが、この非常時に文句を言っている場合ではない。
幸いに?栗原さんの荷物は、身の回りの品と布団だけだったから、場所もとらず私たちのものの片隅にすんなりと納まった。
こうして私たちの新しく厳しい戦後の抑留《よくりゅう》生活が始まったが、とにもかくにも、今まで持っていた権力を失い、帰還も許されず、居住して働くことだけを認められた在朝・日本人としては、今ここにいる約二〇〇名が団結して何時訪れるかわからない帰国の日を耐えて待つよりほかなかった。
早速、父は集まりがあるといって社宅の東側にある小さな集会所へ出かけていった。
この時、これからの集団生活を取り仕切る日本人会が正式に結成され、色々な役どころが決まったと、帰ってきた父から知らされた。父は資材課長の経験から食糧や生活に必要な物資の調達を担当することになったという。また小学校高学年の子供達にも応分の役割が与えられ、私は当然ながら父の仕事を補佐する役目、つまり物資の配給係をさせられることになった。
小一時間かけて私たちが着いた所は、工場から西南にだいぶ離れた工員社宅の更に南のはずれ。その先はもう田畑しかなく、一キロほど向こうに低い山並みが見えるだけの淋しい田園地帯である。
そこに、荒れ果てた四軒長屋が縦に五棟、横に三列連なった住居群があり、ここが今日から私たちの住家となるという。以前は現地の工員が住んでいたらしいが、いったい彼らはどうしたのかがわからない。尋ねると、工場開設に際して採用した工員をその後減員したため、社宅として不要になったものとのことであった。
各戸とも同じ造りで四畳半が二間、そのうち一間はオンドルで、他に土間の台所がついているだけのみすぼらしい住居。勿論トイレは集合便所で外まで出なければならない。
入り口(玄関)は扉がとれて、筵《むしろ》が垂れ下がっているだけのものが多いし、暫く放置されていたせいかすべてが汚らしい。とにかく、これまでの社宅を「家」とすれば、こちらは「豚小屋」と言ってもいい。
既に抽選でもして決められていたのか、それぞれ割り当てられた家に荷物を持って入居することになった。
当時の家族同伴(平均三~四名)の世帯数は約五〇戸だったが、そこにちょうど五〇名ほどの単身者が一人ずつ割り振られて、同居人となった。
余った家一〇戸ほどには、しばらくして、満州からの引揚者ながら直接帰還できず、ここ南楊市まで漸くたどり着いた女子供だけの家族が、どういう理由か知れなかったけど入ってきた。
割り当てられた家は一列目の西端に近いところ、案の定玄関は扉の代わりに筵がかかっており、中は薄暗くて埃《ほこり》っぽい。
すぐ掃除《そうじ》にかかり、持ってきた荷物を納め込むころ一人の男性がやってきた。年のころは四〇才位か、おとなしい人である。
「栗原と申します。ご厄介になりますが、どうぞよろしくお願いいたします」申し訳なさそうに挨拶され、父母も丁重に答える。「心強いです。こちらこそ、よろしくお願いします」。
私達の家族は五人だから、この栗原さんを入れて六人。家の広さからすると狭苦しくなるが、この非常時に文句を言っている場合ではない。
幸いに?栗原さんの荷物は、身の回りの品と布団だけだったから、場所もとらず私たちのものの片隅にすんなりと納まった。
こうして私たちの新しく厳しい戦後の抑留《よくりゅう》生活が始まったが、とにもかくにも、今まで持っていた権力を失い、帰還も許されず、居住して働くことだけを認められた在朝・日本人としては、今ここにいる約二〇〇名が団結して何時訪れるかわからない帰国の日を耐えて待つよりほかなかった。
早速、父は集まりがあるといって社宅の東側にある小さな集会所へ出かけていった。
この時、これからの集団生活を取り仕切る日本人会が正式に結成され、色々な役どころが決まったと、帰ってきた父から知らされた。父は資材課長の経験から食糧や生活に必要な物資の調達を担当することになったという。また小学校高学年の子供達にも応分の役割が与えられ、私は当然ながら父の仕事を補佐する役目、つまり物資の配給係をさせられることになった。
--
編集者 (代理投稿)