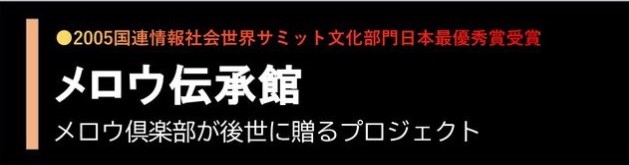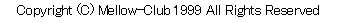гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (24) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„
жҠ•зЁҝгғ„гғӘгғј
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ пјңдёҖйғЁиӢұиЁігҒӮгӮҠпјһ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/4/28 7:38)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ пјңдёҖйғЁиӢұиЁігҒӮгӮҠпјһ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/4/28 7:38)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/4/29 7:43)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/4/29 7:43)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (3) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/4/30 6:49)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (3) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/4/30 6:49)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј”) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/1 7:21)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј”) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/1 7:21)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј•) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/2 8:31)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј•) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/2 8:31)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј–) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/3 7:38)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј–) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/3 7:38)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј—) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/4 8:37)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј—) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/4 8:37)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пјҳ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/5 7:51)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пјҳ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/5 7:51)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пјҷ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/6 8:12)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пјҷ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/6 8:12)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пјҗ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/7 7:47)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пјҗ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/7 7:47)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј‘) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/8 7:46)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј‘) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/8 7:46)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј’) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/9 5:57)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј’) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/9 5:57)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј“) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/20 10:17)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј“) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/20 10:17)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј”) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/21 9:32)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј”) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/21 9:32)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘5) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/22 8:44)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘5) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/22 8:44)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј–) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/23 8:05)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј–) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/23 8:05)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј—) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/24 7:23)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј—) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/24 7:23)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пјҳ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/25 7:34)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пјҳ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/25 7:34)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пјҷ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/26 6:51)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пјҷ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/26 6:51)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пјҗ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/27 7:27)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пјҗ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/27 7:27)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј‘) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/28 7:07)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј‘) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/28 7:07)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј’) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/29 7:36)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј’) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/29 7:36)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј“) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/30 7:39)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј“) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/30 7:39)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (24) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/31 15:39)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (24) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/31 15:39)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј•) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/1 7:56)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј•) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/1 7:56)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј–) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/2 6:56)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј–) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/2 6:56)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј—) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/3 7:22)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј—) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/3 7:22)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пјҳ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/4 7:19)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пјҳ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/4 7:19)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пјҷ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/5 8:04)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пјҷ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/5 8:04)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пјҗ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/6 7:43)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пјҗ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/6 7:43)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј‘) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/7 7:39)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј‘) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/7 7:39)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј’) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/8 8:21)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј’) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/8 8:21)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј“) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/9 7:20)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј“) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/9 7:20)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј”) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/10 8:08)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј”) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/10 8:08)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј•) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/11 7:53)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј•) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/11 7:53)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј–) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/12 7:54)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј–) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/12 7:54)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј—) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/13 7:15)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј—) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/13 7:15)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пјҳ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/14 7:59)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пјҳ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/14 7:59)
-
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пјҷ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/15 7:52)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пјҷ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/15 7:52)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј”пјҗ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/16 8:46)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј”пјҗ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/16 8:46)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј”пј‘гғ»жңҖзөӮеӣһ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/17 7:27)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј”пј‘гғ»жңҖзөӮеӣһ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/17 7:27)
-
гҒ“гҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜгҒ®жҠ•зЁҝдёҖиҰ§гҒё
- depth:
- 1
з·ЁйӣҶиҖ…
 еұ…дҪҸең°: гғЎгғӯгӮҰеҖ¶жҘҪйғЁ
жҠ•зЁҝж•°: 4298
еұ…дҪҸең°: гғЎгғӯгӮҰеҖ¶жҘҪйғЁ
жҠ•зЁҝж•°: 4298
 еұ…дҪҸең°: гғЎгғӯгӮҰеҖ¶жҘҪйғЁ
жҠ•зЁҝж•°: 4298
еұ…дҪҸең°: гғЎгғӯгӮҰеҖ¶жҘҪйғЁ
жҠ•зЁҝж•°: 4298
гҖҖдёҖзё·гҖҠгҒ„гҒЎгӮӢгҖӢгҒ®жңӣгҒҝгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰйҒҺгҒ”гҒҷж—ҘгҖ…
гҖҖеҢ—жңқй®®гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢзӨҫдјҡдё»зҫ©ж”ҝжЁ©еҢ–гҒ®еӢ•гҒҚгҒҜгҖҒйҮ‘ж—ҘжҲҗгҒҢдё»е°ҺгҒҷгӮӢе…ұз”Је…ҡгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒ“гҒ®й ғгҒӢгӮүжҘөгӮҒгҒҰзөұдёҖзҡ„гҒ«еҫ№еә•гҒ—гҒҰиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒжҲҰжҷӮдёӯж—Ҙжң¬гҒҢгҖҢзҡҮж°‘еҢ–гҖҚж”ҝзӯ–гӮ’еӯҰж Ўж•ҷиӮІгҒ«жҢҒгҒЎиҫјгӮ“гҒ гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒж•ҷе®ӨгҒ§гҒҜзӨҫдјҡдё»зҫ©жҖқжғігҒҢе”ҜдёҖгҒ®ж•ҷжқЎгҖҠе…¬иӘҚгҒ—гҒҹеҚ”иӯ°гӮ’з®ҮжқЎгҒЁгҒ—гҒҰиЎЁзҸҫгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҖӢгҒЁгҒ—гҒҰж•ҷгҒҲгӮүгӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒеӯҗдҫӣйҒ”гҒҢйҒҠгҒігҒӘгҒҢгӮүжңқй®®иӘһгҒ§жӯҢгҒҶгҖҢгӮӨгғігӮҝгғјгҖҚгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгӮӮзӘәгҖҠгҒҶгҒӢгҒҢгҖӢгҒ„зҹҘгӮҢгҒҹгҖӮ
гҖҖз§ҒгҒҹгҒЎгҒ«гҒҜеј·еҲ¶гҒ“гҒқгҒ•гӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒеҪјгӮүгҒ®жӯҢгӮ’иҒһгҒҚгҒӘгҒҢгӮүиҮӘ然гҒ«иҰҡгҒҲгҒҰжӯҢгҒҶгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒгҒқгҒҶгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҪјгӮүгҒ«иҰӘиҝ‘ж„ҹгӮ’жҢҒгҒҹгҒӣгӮӢгҒ®гҒӢд»ҘеүҚгҒ»гҒ©ж•өж„ҫеҝғгҖҠгҒҰгҒҚгҒҢгҒ„гҒ—гӮ“гҖӢгӮ’йЎ•гҖҠгҒӮгӮүгӮҸгҖӢгҒ«гҒ—гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒЎгӮүгӮӮеҫ—гҒҹгӮҠгҒЁгҒ°гҒӢгӮҠгҒ«еҸЈгҒҡгҒ•гҒҝгҒӘгҒҢгӮүйҒҠгӮ“гҒ гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—иҰӘйҒ”гҒ«гҒ—гҒҰгҒҝгӮҢгҒ°гҖҒгҖҢз”ҹгҒҚ延гҒігӮӢгҒ“гҒЁгҖҚгҖҒгҖҢеё°гӮӢгҒ“гҒЁгҖҚгҒ«еҝғгӮ’з •гҒ„гҒҰгҒ„гҒҹзӯҲгҒ§гҖҒз„ЎйӮӘж°—гҖҠгӮҖгҒҳгӮғгҒҚгҖӢгҒЁгҒҜжҖқгҒЈгҒҰгӮӮжұәгҒ—гҒҰеҝғең°гӮҲгҒҸгҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгӮҚгҒҶгҒ—гҖҒгҖҢгҒқгӮ“гҒӘжӯҢгҒҜжӯўгӮҒгҒӘгҒ•гҒ„гҖҚгҒЁдёҚжәҖйЎ”гҒ«гҒ„гӮҸгӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгӮӮжҖқгҒ„еҮәгҒҷгҖӮ
гҖҖжӣІгҒҜеё°еӣҪеҫҢжҡ«гҒҸгҒ—гҒҰгҖҒзӨҫдјҡдё»зҫ©гғ»е…ұз”Јдё»зҫ©гҒ«гҒӢгҒ¶гӮҢгҒҹйҖЈдёӯгҒҢжӯҢгҒҶгҒ®гӮ’й–ӢгҒ„гҒҰгҖҢгҒӮгҒӮгҖҒгҒӮгҒ®жӯҢгҒӢгҖҚгҒЁдёҚжҖқиӯ°гҒӘж„ҹиҰҡгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒжңқй®®иӘһгҒ®жӯҢи©һгҒҜгӮӮгҒҶеҝҳгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
гҖҖгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹзҠ¶жіҒгҒ®дёӯгҒ§гҖҒеҚ—жҘҠеёӮгғ»дёүдә•и»ҪйҮ‘еұһж—Ҙжң¬дәәдјҡгҒҜгҒЁгҒ«гӮӮгҒӢгҒҸгҒ«гӮӮгҖҢеј•гҒҚжҸҡгҒ’гҖҚе®ҹзҸҫгҒ«еҗ‘гҒ‘гҒҰз©ҚжҘөзҡ„гҒӘйҒӢеӢ•гӮ’еұ•й–ӢгҒ—гҒҹгҒ«гӮӮжӢҳгӮҸгӮүгҒҡгҖҒдҪ•еҮҰгҒӢгӮүгӮӮдёҖеҗ‘гҒ«жүҝиӘҚгҒҢеҮәгҒӘгҒ„гҒҫгҒҫгҖҒз§ҒйҒ”гҒҜй…·еҜ’гҒ®ең°гҒ§еҜ’гҒ•гҒ«йңҮгҒҲгҒӘгҒҢгӮүгҖҒеҫ’гҖҠгҒ„гҒҹгҒҡгӮүгҖӢгҒ«жҷӮгҒҜжөҒгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖгҒ“гҒ®й ғгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁйЈҹж–ҷдәӢжғ…гҒҜжӣҙгҒ«жӮӘеҢ–гҒ—гҖҒзұігҒҜеӢҝи«–гҒ®гҒ“гҒЁгҖҒгғҲгӮҰгғўгғӯгӮігӮ·гҖҒзІҹгҖҠгҒӮгӮҸгҖӢгҖҒзЁ—гҖҠгҒІгҒҲгҖӢгҒ§гҒҷгӮүй…ҚзөҰйҮҸгҒҜжёӣгҒЈгҒҰгҖҒгҖҢи…№жёӣгҒЈгҒҹгҒӘпјҒгҖҚгҖҒгҖҢдҪ•гҒӢзҫҺе‘ігҒ„гӮӮгҒ®гҒҢйЈҹгҒ№гҒҹгҒ„гҒӘпјҒгҖҚгҒЁеҸЈгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеў—гҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒқгҒ—гҒҰеҪ“然гҒӘгҒҢгӮүйЈҹж–ҷдёҚи¶ігӮ’иЈңгҒҶгҖҢд»•дәӢгҖҚгҒ«зІҫгӮ’еҮәгҒ•гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖдёүеҜ’еӣӣжё©гҒ®жҳҘгҒҢгҒҫгҒҹгҒҫгҒҹгӮ„гҒЈгҒҰгҒҚгҒҰд»–гҒ®ж°·гҒҢжә¶гҒ‘е§ӢгӮҒгӮӢгҒЁгҖҒиӣӢзҷҪиіӘиЈңзөҰгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®йӯҡзҚІгӮҠдҪңжҘӯгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮж°ҙгҒҢеҶ·гҒҹгҒ„жҷӮгҒҜйӯҡгӮӮеӢ•гҒҚгҒҢйҲҚгҒҸгҖҒйҜүгҖҠгҒ“гҒ„гҖӢгӮ„й®’гҖҠгҒөгҒӘгҖӢгҒӘгҒ©еӨ§еһӢгҒ®гӮӮгҒ®гҒҢгӮ¶гғ«гҒӘгҒ©гҒ§е®№жҳ“гҒҸжҺ¬гҒ„еҸ–гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮгҒҫгҒҹеҲқгӮҒгҒ®гҒҶгҒЎгҒІгҒ©гҒӢгҒЈгҒҹжңқй®®дәәгҒ®иӢӣгҖҠгҒ„гҒҳгҖӢгӮҒгӮӮжёӣгҒЈгҒҰгҒҚгҒҰгҒ„гҒҹгҒӢгӮүгҖҒиЎҢеӢ•зҜ„еӣІгӮӮе°‘гҒ—гҒҜеәғгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹзҲ¶гҒ«й јгӮҖгҒЁдҪ•еҮҰгҒӢгҒ§йҮЈгӮҠзіёгӮ„йҮқгӮӮд»•е…ҘгӮҢгҒҰгҒҚгҒҰгҒҸгӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹйҒ“е…·гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰе°‘гҒ—йҒ гҒҸгҒҫгҒ§йӯҡйҮЈгӮҠгҒ«еҮәгҒӢгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
гҖҖйҮЈгӮҠгҒҜй®’гҒ«е§ӢгҒҫгӮҠй®’гҒ«зөӮгӮҸгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ»гҒ©гҒ§гҖҒйҮЈгӮҠгӮ’и¶Је‘ігҒЁгҒҷгӮӢдәәгҒ«гҒҜйқўзҷҪгҒҸгҒҰйӣЈгҒ—гҒ„йҮЈгӮҠгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒ®е ҙеҗҲгҒҜйЈҹгҒ№гӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гҖҢд»•дәӢгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮж•°еӨҡгҒҸгҒӮгӮӢжұ гҒ«гҒҜй®’гҒҢгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“гҒ„гҒҰгҖҒжңқй®®гҒ®еӨӘе…¬жңӣгҖҠгҒҹгҒ„гҒ“гҒҶгҒјгҒҶ=йҮЈгӮҠдәәгҒ®з•°з§°гҖӢгҒҢжңқгҒӢгӮүзіёгӮ’еһӮгӮҢгӮӢе§ҝгӮ’иҰӢгҒӢгҒ‘гҖҒеҪјгӮүгӮӮз§ҒгҒҹгҒЎгӮ’е·®гҒ»гҒ©жҜӣе«ҢгҒ„гҒ—гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒӢгӮүгҖҒеҒҙгҒ«еҜ„гҒЈгҒҰиЎҢгҒЈгҒҰгҒҜйҮЈгӮӢж§ҳеӯҗгӮ’иҰӢгҒҹгӮҠгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
гҖҖзўәгҒӢгҒ«гҖҢйӣЈгҒ—гҒ„гҖҚйҮЈгӮҠгҒ§гҖҒгҒ“гҒЎгӮүгҒ«гҒҜе®№жҳ“гҒ«гҒҜжҺӣгҒӢгҒЈгҒҰгҒҸгӮҢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒеҪјгӮүгҒҜж¬ЎгҒӢгӮүж¬ЎгҒёгҒЁгӮӮгҒ®гҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮдёҚжҖқиӯ°гҒ«жҖқгҒЈгҒҰйӨҢгӮ’иҰӢгӮӢгҒЁгҖҒгҒ“гҒЎгӮүгҒ®ж–№гҒҢйЈҹгҒ№гҒҹгҒ„гҖҢгҒ”йЈҜзІ’гҖҚгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гҒ„гҒ„гҒ®гҒӢгҒЁе°‘гҒ—еҲҶгҒ‘гҒҰиІ°гҒ„йҮқгҒ«д»ҳгҒ‘гҒҰж”ҫгӮҠиҫјгӮҖгҒЁгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒ®гғҹгғҹгӮәгӮ„гғҲгӮҰгғўгғӯгӮігӮ·гҒ®еӣЈеӯҗгҒ§гҒҜгғ”гӮҜгғӘгҒЁгӮӮгҒ—гҒӘгҒ„жө®гҒҚгҒҢжІҲгӮҖгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ
гҖҖгҖҢгҒ“гҒ“гҒ®й®’гӮӮгӮ„гҒҜгӮҠгҒ”йЈҜгҒҢйЈҹгҒ№гҒҹгҒ„гҒ®гҒӢгҖҚгҒЁеӨүгҒӘеҗҢжғ…гӮ’гҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒгҒқгҒ®ж—ҘгҒҜж•°е°ҫгӮ’гҒӮгҒ’гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«жҲҗеҠҹгҖҒеӨңгҒ®еӨ§еӨүгҒӘгҒ”йҰіиө°гҖҠгҒ”гҒЎгҒқгҒҶгҖӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҸгӮҢгҒҹгҖӮ
гҖҖгҒқгӮҢгҒӢгӮүгҒҜжҜҺж—ҘгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒ家гҒ«гҒӮгӮӢгҒӘгҒ‘гҒӘгҒ—гҒ®зұізІ’гӮ’гӮӮгҒЈгҒҰй®’йҮЈгӮҠгҒ«зІҫгӮ’еҮәгҒҷж—ҘгҒҢз¶ҡгҒ„гҒҹгҖӮ
гҖҖжҳҘгӮӮгҒҹгҒ‘гҒӘгӮҸгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰж°ҙгҒҢгҒ¬гӮӢгӮҖгҒЁгҖҒд»ҠеәҰгҒҜгӮҰгғҠгӮ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖжұ гҒ«гҒҜеҘҙгӮүгҒҢй®’гӮҲгӮҠгӮӮгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“гҒ„гҒҰгҖҒйқўзҷҪгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гӮҲгҒҸзҚІгӮҢгҒҹгҖӮгҒҹгҒ“зіёгҒ«еӨ§гҒҚзӣ®гҒ®йҮқгӮ’гҒӨгҒ‘з”°гӮ“гҒјгҒ®з•ҰгҖҠгҒӮгҒң=з”°гӮ“гҒјгҒ®еўғз•ҢгӮ’дҪңгӮӢеҢәеҲҮгӮҠгҖӢгҒ§жҚ•гҒЈгҒҹгғүгӮёгғ§гӮҰгӮ’йӨҢгҒ«д»ҳгҒ‘гҒҰгҖҒеӨ•ж–№дҪ•жң¬гҒӢж”ҫгӮҠиҫјгӮ“гҒ§гҒҠгҒҸгҖӮеӢҝи«–з«ҜгҖҠгҒҜгҒ—гҖӢгҒЈгҒ“гҒҜдә”гҖҮгӮ»гғігғҒгҒ»гҒ©гҒ®жЈ’гҒҸгҒ„гҒ§гҒ—гҒЈгҒӢгӮҠеІёгҒ«з№ӢгҒҺгҒЁгӮҒгҖҒзҝҢжңқж—©гҒҸгҒ“гӮҢгӮ’еј•гҒҚдёҠгҒ’гӮӢгҒ®гҒ гҖӮжҺӣгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁзіёгҒҢгғ”гғігҒЁдјёгҒігҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҗгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮгҖҖгҖҢгҒ—гӮҒгҒҹгҖҚгҒЁиҶқгҖҠгҒІгҒ–гҖӢдёҠгҒҫгҒ§ж°ҙгҒ«е…ҘгӮҠгҒ“гӮҢгӮ’еј•гҒҚдёҠгҒ’гӮӢгҒЁгҖҒеӨ§гҒҚгҒ„гҒ®гҒҜпј©гғЎгғјгғҲгғ«иҝ‘гҒҸгҖҒе°ҸгҒ•гҒҸгҒЁгӮӮдә”гҖҮгӮ»гғігғҒгҒ®гӮҰгғҠгӮ®гҒҢжүӢгҒ”гҒҹгҒҲиұҠгҒӢгҒ«дёҠгҒҢгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮдёҖгҖҮжң¬д»•жҺӣгҒ‘гӮӢгҒЁдёүпҪһеӣӣжң¬гҒ«гҒҜжҺӣгҒӢгҒЈгҒҹгҒӢгӮүзўәзҺҮгҒҜеӣӣеүІгҒ«иҝ‘гҒҸгҖҒгҒЁгҒ«гҒӢгҒҸйқўзҷҪгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«зҚІгӮҢгҒҰгҖҒеҲқгӮҒгҒҜжҜҺж—ҘгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«д»•дәӢгҒ«еҠұгӮҖж—ҘгҖ…гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖжҢҒгҒЎеё°гҒЈгҒҹзҚІзү©гҒҜиҮӘеҲҶгҒ§жҚҢгҖҠгҒ•гҒ°гҖӢгҒҸгҖӮжҷ®йҖҡгҒ®иҸңгҒҚгӮҠеҢ…дёҒгҒ§гҒҜгҒҶгҒҫгҒҸгҒ„гҒӢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒйҒ“е…·гҒҜгҖҢиӮҘеҫҢгҒ®е®ҲгҖҠгҒІгҒ”гҒ®гҒӢгҒҝ=е°ҸеҲҖгҒ®дёҖзЁ®гҖҒжҠҳгӮҠиҫјгҒҝејҸгҒ§жҹ„гӮӮйү„иЈҪгҖӢгҖҚгҖӮгҒҫгҒӘжқҝгҒ«й ӯгӮ’йҢҗгҖҠгҒҚгӮҠгҖӢгҒ§жү“гҒЎгҒӨгҒ‘иғҢй–ӢгҒҚгҒ«гҒ—гҒҹгҒӮгҒЁй ӯгӮ’еҲҮгӮҠиҗҪгҒ—гҖҒеӨ§зү©гҒҜдёүгҒӨгҒӢгӮүеӣӣгҒӨгҖҒе°Ҹзү©гҒҜдәҢгҒӨгҒ«гҒ—гҒҰи’Із„јгҖҠгҒӢгҒ°гӮ„гҒҚгҖӢгҒ®дёӢгҒ”гҒ—гӮүгҒҲгҒҜеҮәжқҘдёҠгҒҢгӮӢгҖӮгҒӮгҒЁгҒҜжҜҚгҒҢгҖҒиІҙйҮҚгҒӘйҶӨжІ№гҒЁеҪ“жҷӮз Ӯзі–гҒҜжүӢгҒ«е…ҘгӮүгҒҡгҖҒгӮөгғғгӮ«гғӘгғігӮ„гӮәгғ«гғҒгғігҒӘгҒ©гҒ®дәәе·Ҙз”ҳе‘іж–ҷгӮӮгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒӢгӮүгҖҒгғҲгӮҰгӮӯгғ“гҒӢгӮүзөһгӮҠеҮәгҒ—гҒҹжұҒгӮ’з”ҳе‘ігҒ«гҒ—гҒҰдҪңгҒЈгҒҹгӮҝгғ¬гӮ’д»ҳгҒ‘гҒҰи’Із„јгҒ®еҮәжқҘдёҠгҒҢгӮҠгҖӮе°‘гҒ—иҫӣгӮҒгҒ гҒҢзҫҺе‘ігҒҸгҒҰгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒҹиІҙйҮҚгҒ§ж»…еӨҡгҒ«еҸЈгҒ«гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„зұігҒ®йЈҜгӮ’е°‘гҒ—гҒ°гҒӢгӮҠзӮҠгҒ„гҒҰгҖҒгҒқгҒ®дёҠгҒ«д№—гҒӣгӮӢгҒЁжҘөдёҠгҒ®гӮҰгғҠдёјгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒҹгҒ гҖҒзұігҒ®гҒ”йЈҜгҒҜгӮ„гҒҹгӮүгҒ«йЈҹгҒ№гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒзІҹгӮ„й»ҚгҖҠгҒҚгҒігҖӢгҒ®гҒ”йЈҜгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮи’Із„јгҒҜи’Із„јгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒд№…гҒ—гҒ¶гӮҠгҒ«гҖҢзҫҺе‘ігҒ„гӮӮгҒ®гҒ«гҒӮгӮҠгҒӨгҒ‘гҒҹгҖҚгҒЁзҡҶгҒҢжәҖи¶ігҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒҹжҷӮгҒҜгҖҒз§ҒгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮд»•дәӢгҒ®гҒ—з”Іж–җгҖҠгҒ—гҒҢгҒ„гҖӢгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒЁжң¬еҪ“гҒ«е¬үгҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒжҲ–гӮӢж—ҘгҒқгҒ®зҫҺе‘ігҒқгҒҶгҒӘиҮӯгҒ„гӮ’е—…гҒҺгҒӨгҒ‘гҒҹиҝ‘жүҖгҒ®жңқй®®дәәгҒҢгҖҒгҖҢиҙ…жІўгҒӘгӮӮгҒ®гӮ’йЈҹгҒ№гҒҰгҒ„гӮӢгҖҚгҖҒгҖҢгҒ‘гҒ—гҒҢгӮүгӮ“еҘҙгҒҜиӘ°гҒ гҖҚгҒЁж—Ҙжң¬дәәдјҡгҒ«жҖ’йіҙгӮҠиҫјгӮ“гҒ§гҒҚгҒҹгҖҒгҒЁеҝ е‘ҠгҒ•гӮҢ唖然гҖҠгҒӮгҒңгӮ“гҖӢгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ
гҖҖгҖҢиҮӘеҲҶгҒ§зҚІгҒЈгҒҰгҒҚгҒҰеӢқжүӢгҒ«дҪңгҒЈгҒҰйЈҹгҒ№гҒҰдҪ•гҒӢжӮӘгҒ„гҖҚгҖҒгҖҢдёҖз·’гҒ«зҚІгӮҠгҒ«иЎҢгҒЈгҒҹеҸӢйҒ”гӮӮеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒ«йЈҹгҒ№гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ«гҖҒдҪ•ж•…еғ•гҒ гҒ‘гҖҚгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒж—Ҙжң¬дәәдјҡгҒ«иҝ·жғ‘гҒҢгҒӢгҒӢгҒЈгҒҰгӮӮгҒЁгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒҜе°‘гҒ—йҒ ж…®гҒ—гҒӘгҒҢгӮүгӮӮжјҒгҒҜз¶ҡгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
гҖҖгҒ“гҒҶгҒ—гҒҰиӣӢзҷҪиіӘгҖҠгҒҹгӮ“гҒұгҒҸгҒ—гҒӨгҖӢгҒҜйӯҡгҒ§ж‘ӮгӮҢгҖҒгғ“гӮҝгғҹгғіпјЈгӮӮе‘ЁгӮҠгҒ®йҮҺеұұгҒ§гғЁгғўгӮ®гӮ„йҮҺи’ңгӮ’еҸ–гҒЈгҒҰгҒҚгҒҰеӨҡе°‘гҒЁгӮӮж‘ӮеҸ–гҒ§гҒҚгҒҹгҒҢгҖҒдё»йЈҹгҒ®з©Җзү©гҒҜгҒ©гҒҶгҒ«гӮӮгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮд»•ж–№гҒҢгҒӘгҒ„гҒӢгӮүгҖҒжңқй®®дәәиҫІе®¶гҒ«иЎҢгҒЈгҒҰгҒҜгҖҢз”°жӨҚгҒҲгҖҒиҚүгӮҖгҒ—гӮҠгӮ’гӮ„гӮүгҒӣгҒҰж¬ІгҒ—гҒ„гҖӮжүӢй–“иіғгҒҜдҪ•гҒ§гӮӮгҒ„гҒ„гҒӢгӮүз©Җзү©гӮ’еҲҶгҒ‘гҒҰиІ°гҒ„гҒҹгҒ„гҖҚгҒЁгҖҢиҫІдҪңжҘӯгҒ®еЈІгӮҠиҫјгҒҝгҖҚгӮ’гҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҖӮжңҖеҲқгҒҜдҪ•еҮҰгҒёиЎҢгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгҒ«гҒ№гӮӮз„ЎгҒҸж–ӯгӮүгӮҢгӮӢгҒҢгҖҒзІҳгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁеӯҗдҫӣгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«еҗҢжғ…гҒҷгӮӢгҒ®гҒӢгҖҒе°‘гҒ—гҒҡгҒӨд»•дәӢгӮ’гҒҸгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҖҒзөӮгӮҸгӮӢгҒЁе°ҸгҒ•гҒӘиўӢгҒ«зЁ—гҖҠгҒІгҒҲгҖӢгғ»зІҹгӮ’гҖҒгҒҫгҒҹжҷӮгҒ«гҒҜзұігӮ’еҲҶгҒ‘гҒҰгҒҸгӮҢгҒҹгҖӮ
гҖҖдҪ•гӮ„гӮүд№һйЈҹгҒ®гӮҲгҒҶгҒ§гҖҒгҒЁиЁҖгҒҶгӮҲгӮҠе®ҹйҡӣгҒ«д№һйЈҹгҒӘгҒ®гҒ гҒҢгҖҒиҮӘеҲҶгҒ§гҒҜгҖҢеҠҙеғҚгӮ’еёҢжңӣгҒ—гҖҒеҜҫдҫЎгӮ’жұӮгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢгҖҚгҒӢгӮүгҖҢд№һйЈҹгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁиҮӘгӮүиЁҖгҒ„иҒһгҒӢгҒӣгҒҰеҠҙеғҚгҒ«еҠұгӮ“гҒ гҖӮгҒқгӮҢгҒ§гӮӮеҲқгӮҒгҒҜжҒҘгҒҡгҒӢгҒ—гҒҸгҒҰиЁҖи‘үгӮӮгғўгӮҫгғўгӮҪгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—йЈҹгҒ№гӮӢгҒҹгӮҒгҒӘгӮүгӮ„гӮҖгӮ’еҫ—гҒӘгҒ„гҖӮзҫһжҒҘгҖҠгҒЎгҒҳгӮҮгҒҸгҖӢеҝғгӮ’жҚЁгҒҰгӮӢгҒЁгҖҒеҫҢгҒҜгҒ”гҒҸиҮӘ然гҒ«гҖҢгҒҠйЎҳгҒ„гҒ—гҒҫгҒҷгҖҚгҒЁе…ғж°—иүҜгҒҸеЈ°гҒҢеҮәгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰеҸҺз©«гӮӮе°‘гҒ—гҒҡгҒӨеў—гҒҲгҖҒйЈҹз”ҹжҙ»гҒ®жүӢеҠ©гҒ‘гҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢиҮӘж…ўгҒ§гҒҷгӮүгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖеҢ—жңқй®®гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢзӨҫдјҡдё»зҫ©ж”ҝжЁ©еҢ–гҒ®еӢ•гҒҚгҒҜгҖҒйҮ‘ж—ҘжҲҗгҒҢдё»е°ҺгҒҷгӮӢе…ұз”Је…ҡгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒ“гҒ®й ғгҒӢгӮүжҘөгӮҒгҒҰзөұдёҖзҡ„гҒ«еҫ№еә•гҒ—гҒҰиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒжҲҰжҷӮдёӯж—Ҙжң¬гҒҢгҖҢзҡҮж°‘еҢ–гҖҚж”ҝзӯ–гӮ’еӯҰж Ўж•ҷиӮІгҒ«жҢҒгҒЎиҫјгӮ“гҒ гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒж•ҷе®ӨгҒ§гҒҜзӨҫдјҡдё»зҫ©жҖқжғігҒҢе”ҜдёҖгҒ®ж•ҷжқЎгҖҠе…¬иӘҚгҒ—гҒҹеҚ”иӯ°гӮ’з®ҮжқЎгҒЁгҒ—гҒҰиЎЁзҸҫгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҖӢгҒЁгҒ—гҒҰж•ҷгҒҲгӮүгӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒеӯҗдҫӣйҒ”гҒҢйҒҠгҒігҒӘгҒҢгӮүжңқй®®иӘһгҒ§жӯҢгҒҶгҖҢгӮӨгғігӮҝгғјгҖҚгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгӮӮзӘәгҖҠгҒҶгҒӢгҒҢгҖӢгҒ„зҹҘгӮҢгҒҹгҖӮ
гҖҖз§ҒгҒҹгҒЎгҒ«гҒҜеј·еҲ¶гҒ“гҒқгҒ•гӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒеҪјгӮүгҒ®жӯҢгӮ’иҒһгҒҚгҒӘгҒҢгӮүиҮӘ然гҒ«иҰҡгҒҲгҒҰжӯҢгҒҶгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒгҒқгҒҶгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҪјгӮүгҒ«иҰӘиҝ‘ж„ҹгӮ’жҢҒгҒҹгҒӣгӮӢгҒ®гҒӢд»ҘеүҚгҒ»гҒ©ж•өж„ҫеҝғгҖҠгҒҰгҒҚгҒҢгҒ„гҒ—гӮ“гҖӢгӮ’йЎ•гҖҠгҒӮгӮүгӮҸгҖӢгҒ«гҒ—гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒЎгӮүгӮӮеҫ—гҒҹгӮҠгҒЁгҒ°гҒӢгӮҠгҒ«еҸЈгҒҡгҒ•гҒҝгҒӘгҒҢгӮүйҒҠгӮ“гҒ гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—иҰӘйҒ”гҒ«гҒ—гҒҰгҒҝгӮҢгҒ°гҖҒгҖҢз”ҹгҒҚ延гҒігӮӢгҒ“гҒЁгҖҚгҖҒгҖҢеё°гӮӢгҒ“гҒЁгҖҚгҒ«еҝғгӮ’з •гҒ„гҒҰгҒ„гҒҹзӯҲгҒ§гҖҒз„ЎйӮӘж°—гҖҠгӮҖгҒҳгӮғгҒҚгҖӢгҒЁгҒҜжҖқгҒЈгҒҰгӮӮжұәгҒ—гҒҰеҝғең°гӮҲгҒҸгҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгӮҚгҒҶгҒ—гҖҒгҖҢгҒқгӮ“гҒӘжӯҢгҒҜжӯўгӮҒгҒӘгҒ•гҒ„гҖҚгҒЁдёҚжәҖйЎ”гҒ«гҒ„гӮҸгӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгӮӮжҖқгҒ„еҮәгҒҷгҖӮ
гҖҖжӣІгҒҜеё°еӣҪеҫҢжҡ«гҒҸгҒ—гҒҰгҖҒзӨҫдјҡдё»зҫ©гғ»е…ұз”Јдё»зҫ©гҒ«гҒӢгҒ¶гӮҢгҒҹйҖЈдёӯгҒҢжӯҢгҒҶгҒ®гӮ’й–ӢгҒ„гҒҰгҖҢгҒӮгҒӮгҖҒгҒӮгҒ®жӯҢгҒӢгҖҚгҒЁдёҚжҖқиӯ°гҒӘж„ҹиҰҡгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒжңқй®®иӘһгҒ®жӯҢи©һгҒҜгӮӮгҒҶеҝҳгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
гҖҖгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹзҠ¶жіҒгҒ®дёӯгҒ§гҖҒеҚ—жҘҠеёӮгғ»дёүдә•и»ҪйҮ‘еұһж—Ҙжң¬дәәдјҡгҒҜгҒЁгҒ«гӮӮгҒӢгҒҸгҒ«гӮӮгҖҢеј•гҒҚжҸҡгҒ’гҖҚе®ҹзҸҫгҒ«еҗ‘гҒ‘гҒҰз©ҚжҘөзҡ„гҒӘйҒӢеӢ•гӮ’еұ•й–ӢгҒ—гҒҹгҒ«гӮӮжӢҳгӮҸгӮүгҒҡгҖҒдҪ•еҮҰгҒӢгӮүгӮӮдёҖеҗ‘гҒ«жүҝиӘҚгҒҢеҮәгҒӘгҒ„гҒҫгҒҫгҖҒз§ҒйҒ”гҒҜй…·еҜ’гҒ®ең°гҒ§еҜ’гҒ•гҒ«йңҮгҒҲгҒӘгҒҢгӮүгҖҒеҫ’гҖҠгҒ„гҒҹгҒҡгӮүгҖӢгҒ«жҷӮгҒҜжөҒгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖгҒ“гҒ®й ғгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁйЈҹж–ҷдәӢжғ…гҒҜжӣҙгҒ«жӮӘеҢ–гҒ—гҖҒзұігҒҜеӢҝи«–гҒ®гҒ“гҒЁгҖҒгғҲгӮҰгғўгғӯгӮігӮ·гҖҒзІҹгҖҠгҒӮгӮҸгҖӢгҖҒзЁ—гҖҠгҒІгҒҲгҖӢгҒ§гҒҷгӮүй…ҚзөҰйҮҸгҒҜжёӣгҒЈгҒҰгҖҒгҖҢи…№жёӣгҒЈгҒҹгҒӘпјҒгҖҚгҖҒгҖҢдҪ•гҒӢзҫҺе‘ігҒ„гӮӮгҒ®гҒҢйЈҹгҒ№гҒҹгҒ„гҒӘпјҒгҖҚгҒЁеҸЈгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеў—гҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒқгҒ—гҒҰеҪ“然гҒӘгҒҢгӮүйЈҹж–ҷдёҚи¶ігӮ’иЈңгҒҶгҖҢд»•дәӢгҖҚгҒ«зІҫгӮ’еҮәгҒ•гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖдёүеҜ’еӣӣжё©гҒ®жҳҘгҒҢгҒҫгҒҹгҒҫгҒҹгӮ„гҒЈгҒҰгҒҚгҒҰд»–гҒ®ж°·гҒҢжә¶гҒ‘е§ӢгӮҒгӮӢгҒЁгҖҒиӣӢзҷҪиіӘиЈңзөҰгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®йӯҡзҚІгӮҠдҪңжҘӯгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮж°ҙгҒҢеҶ·гҒҹгҒ„жҷӮгҒҜйӯҡгӮӮеӢ•гҒҚгҒҢйҲҚгҒҸгҖҒйҜүгҖҠгҒ“гҒ„гҖӢгӮ„й®’гҖҠгҒөгҒӘгҖӢгҒӘгҒ©еӨ§еһӢгҒ®гӮӮгҒ®гҒҢгӮ¶гғ«гҒӘгҒ©гҒ§е®№жҳ“гҒҸжҺ¬гҒ„еҸ–гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮгҒҫгҒҹеҲқгӮҒгҒ®гҒҶгҒЎгҒІгҒ©гҒӢгҒЈгҒҹжңқй®®дәәгҒ®иӢӣгҖҠгҒ„гҒҳгҖӢгӮҒгӮӮжёӣгҒЈгҒҰгҒҚгҒҰгҒ„гҒҹгҒӢгӮүгҖҒиЎҢеӢ•зҜ„еӣІгӮӮе°‘гҒ—гҒҜеәғгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹзҲ¶гҒ«й јгӮҖгҒЁдҪ•еҮҰгҒӢгҒ§йҮЈгӮҠзіёгӮ„йҮқгӮӮд»•е…ҘгӮҢгҒҰгҒҚгҒҰгҒҸгӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹйҒ“е…·гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰе°‘гҒ—йҒ гҒҸгҒҫгҒ§йӯҡйҮЈгӮҠгҒ«еҮәгҒӢгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
гҖҖйҮЈгӮҠгҒҜй®’гҒ«е§ӢгҒҫгӮҠй®’гҒ«зөӮгӮҸгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ»гҒ©гҒ§гҖҒйҮЈгӮҠгӮ’и¶Је‘ігҒЁгҒҷгӮӢдәәгҒ«гҒҜйқўзҷҪгҒҸгҒҰйӣЈгҒ—гҒ„йҮЈгӮҠгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒ®е ҙеҗҲгҒҜйЈҹгҒ№гӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гҖҢд»•дәӢгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮж•°еӨҡгҒҸгҒӮгӮӢжұ гҒ«гҒҜй®’гҒҢгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“гҒ„гҒҰгҖҒжңқй®®гҒ®еӨӘе…¬жңӣгҖҠгҒҹгҒ„гҒ“гҒҶгҒјгҒҶ=йҮЈгӮҠдәәгҒ®з•°з§°гҖӢгҒҢжңқгҒӢгӮүзіёгӮ’еһӮгӮҢгӮӢе§ҝгӮ’иҰӢгҒӢгҒ‘гҖҒеҪјгӮүгӮӮз§ҒгҒҹгҒЎгӮ’е·®гҒ»гҒ©жҜӣе«ҢгҒ„гҒ—гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒӢгӮүгҖҒеҒҙгҒ«еҜ„гҒЈгҒҰиЎҢгҒЈгҒҰгҒҜйҮЈгӮӢж§ҳеӯҗгӮ’иҰӢгҒҹгӮҠгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
гҖҖзўәгҒӢгҒ«гҖҢйӣЈгҒ—гҒ„гҖҚйҮЈгӮҠгҒ§гҖҒгҒ“гҒЎгӮүгҒ«гҒҜе®№жҳ“гҒ«гҒҜжҺӣгҒӢгҒЈгҒҰгҒҸгӮҢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒеҪјгӮүгҒҜж¬ЎгҒӢгӮүж¬ЎгҒёгҒЁгӮӮгҒ®гҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮдёҚжҖқиӯ°гҒ«жҖқгҒЈгҒҰйӨҢгӮ’иҰӢгӮӢгҒЁгҖҒгҒ“гҒЎгӮүгҒ®ж–№гҒҢйЈҹгҒ№гҒҹгҒ„гҖҢгҒ”йЈҜзІ’гҖҚгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гҒ„гҒ„гҒ®гҒӢгҒЁе°‘гҒ—еҲҶгҒ‘гҒҰиІ°гҒ„йҮқгҒ«д»ҳгҒ‘гҒҰж”ҫгӮҠиҫјгӮҖгҒЁгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒ®гғҹгғҹгӮәгӮ„гғҲгӮҰгғўгғӯгӮігӮ·гҒ®еӣЈеӯҗгҒ§гҒҜгғ”гӮҜгғӘгҒЁгӮӮгҒ—гҒӘгҒ„жө®гҒҚгҒҢжІҲгӮҖгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ
гҖҖгҖҢгҒ“гҒ“гҒ®й®’гӮӮгӮ„гҒҜгӮҠгҒ”йЈҜгҒҢйЈҹгҒ№гҒҹгҒ„гҒ®гҒӢгҖҚгҒЁеӨүгҒӘеҗҢжғ…гӮ’гҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒгҒқгҒ®ж—ҘгҒҜж•°е°ҫгӮ’гҒӮгҒ’гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«жҲҗеҠҹгҖҒеӨңгҒ®еӨ§еӨүгҒӘгҒ”йҰіиө°гҖҠгҒ”гҒЎгҒқгҒҶгҖӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҸгӮҢгҒҹгҖӮ
гҖҖгҒқгӮҢгҒӢгӮүгҒҜжҜҺж—ҘгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒ家гҒ«гҒӮгӮӢгҒӘгҒ‘гҒӘгҒ—гҒ®зұізІ’гӮ’гӮӮгҒЈгҒҰй®’йҮЈгӮҠгҒ«зІҫгӮ’еҮәгҒҷж—ҘгҒҢз¶ҡгҒ„гҒҹгҖӮ
гҖҖжҳҘгӮӮгҒҹгҒ‘гҒӘгӮҸгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰж°ҙгҒҢгҒ¬гӮӢгӮҖгҒЁгҖҒд»ҠеәҰгҒҜгӮҰгғҠгӮ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖжұ гҒ«гҒҜеҘҙгӮүгҒҢй®’гӮҲгӮҠгӮӮгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“гҒ„гҒҰгҖҒйқўзҷҪгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гӮҲгҒҸзҚІгӮҢгҒҹгҖӮгҒҹгҒ“зіёгҒ«еӨ§гҒҚзӣ®гҒ®йҮқгӮ’гҒӨгҒ‘з”°гӮ“гҒјгҒ®з•ҰгҖҠгҒӮгҒң=з”°гӮ“гҒјгҒ®еўғз•ҢгӮ’дҪңгӮӢеҢәеҲҮгӮҠгҖӢгҒ§жҚ•гҒЈгҒҹгғүгӮёгғ§гӮҰгӮ’йӨҢгҒ«д»ҳгҒ‘гҒҰгҖҒеӨ•ж–№дҪ•жң¬гҒӢж”ҫгӮҠиҫјгӮ“гҒ§гҒҠгҒҸгҖӮеӢҝи«–з«ҜгҖҠгҒҜгҒ—гҖӢгҒЈгҒ“гҒҜдә”гҖҮгӮ»гғігғҒгҒ»гҒ©гҒ®жЈ’гҒҸгҒ„гҒ§гҒ—гҒЈгҒӢгӮҠеІёгҒ«з№ӢгҒҺгҒЁгӮҒгҖҒзҝҢжңқж—©гҒҸгҒ“гӮҢгӮ’еј•гҒҚдёҠгҒ’гӮӢгҒ®гҒ гҖӮжҺӣгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁзіёгҒҢгғ”гғігҒЁдјёгҒігҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҗгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮгҖҖгҖҢгҒ—гӮҒгҒҹгҖҚгҒЁиҶқгҖҠгҒІгҒ–гҖӢдёҠгҒҫгҒ§ж°ҙгҒ«е…ҘгӮҠгҒ“гӮҢгӮ’еј•гҒҚдёҠгҒ’гӮӢгҒЁгҖҒеӨ§гҒҚгҒ„гҒ®гҒҜпј©гғЎгғјгғҲгғ«иҝ‘гҒҸгҖҒе°ҸгҒ•гҒҸгҒЁгӮӮдә”гҖҮгӮ»гғігғҒгҒ®гӮҰгғҠгӮ®гҒҢжүӢгҒ”гҒҹгҒҲиұҠгҒӢгҒ«дёҠгҒҢгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮдёҖгҖҮжң¬д»•жҺӣгҒ‘гӮӢгҒЁдёүпҪһеӣӣжң¬гҒ«гҒҜжҺӣгҒӢгҒЈгҒҹгҒӢгӮүзўәзҺҮгҒҜеӣӣеүІгҒ«иҝ‘гҒҸгҖҒгҒЁгҒ«гҒӢгҒҸйқўзҷҪгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«зҚІгӮҢгҒҰгҖҒеҲқгӮҒгҒҜжҜҺж—ҘгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«д»•дәӢгҒ«еҠұгӮҖж—ҘгҖ…гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖжҢҒгҒЎеё°гҒЈгҒҹзҚІзү©гҒҜиҮӘеҲҶгҒ§жҚҢгҖҠгҒ•гҒ°гҖӢгҒҸгҖӮжҷ®йҖҡгҒ®иҸңгҒҚгӮҠеҢ…дёҒгҒ§гҒҜгҒҶгҒҫгҒҸгҒ„гҒӢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒйҒ“е…·гҒҜгҖҢиӮҘеҫҢгҒ®е®ҲгҖҠгҒІгҒ”гҒ®гҒӢгҒҝ=е°ҸеҲҖгҒ®дёҖзЁ®гҖҒжҠҳгӮҠиҫјгҒҝејҸгҒ§жҹ„гӮӮйү„иЈҪгҖӢгҖҚгҖӮгҒҫгҒӘжқҝгҒ«й ӯгӮ’йҢҗгҖҠгҒҚгӮҠгҖӢгҒ§жү“гҒЎгҒӨгҒ‘иғҢй–ӢгҒҚгҒ«гҒ—гҒҹгҒӮгҒЁй ӯгӮ’еҲҮгӮҠиҗҪгҒ—гҖҒеӨ§зү©гҒҜдёүгҒӨгҒӢгӮүеӣӣгҒӨгҖҒе°Ҹзү©гҒҜдәҢгҒӨгҒ«гҒ—гҒҰи’Із„јгҖҠгҒӢгҒ°гӮ„гҒҚгҖӢгҒ®дёӢгҒ”гҒ—гӮүгҒҲгҒҜеҮәжқҘдёҠгҒҢгӮӢгҖӮгҒӮгҒЁгҒҜжҜҚгҒҢгҖҒиІҙйҮҚгҒӘйҶӨжІ№гҒЁеҪ“жҷӮз Ӯзі–гҒҜжүӢгҒ«е…ҘгӮүгҒҡгҖҒгӮөгғғгӮ«гғӘгғігӮ„гӮәгғ«гғҒгғігҒӘгҒ©гҒ®дәәе·Ҙз”ҳе‘іж–ҷгӮӮгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒӢгӮүгҖҒгғҲгӮҰгӮӯгғ“гҒӢгӮүзөһгӮҠеҮәгҒ—гҒҹжұҒгӮ’з”ҳе‘ігҒ«гҒ—гҒҰдҪңгҒЈгҒҹгӮҝгғ¬гӮ’д»ҳгҒ‘гҒҰи’Із„јгҒ®еҮәжқҘдёҠгҒҢгӮҠгҖӮе°‘гҒ—иҫӣгӮҒгҒ гҒҢзҫҺе‘ігҒҸгҒҰгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒҹиІҙйҮҚгҒ§ж»…еӨҡгҒ«еҸЈгҒ«гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„зұігҒ®йЈҜгӮ’е°‘гҒ—гҒ°гҒӢгӮҠзӮҠгҒ„гҒҰгҖҒгҒқгҒ®дёҠгҒ«д№—гҒӣгӮӢгҒЁжҘөдёҠгҒ®гӮҰгғҠдёјгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒҹгҒ гҖҒзұігҒ®гҒ”йЈҜгҒҜгӮ„гҒҹгӮүгҒ«йЈҹгҒ№гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒзІҹгӮ„й»ҚгҖҠгҒҚгҒігҖӢгҒ®гҒ”йЈҜгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮи’Із„јгҒҜи’Із„јгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒд№…гҒ—гҒ¶гӮҠгҒ«гҖҢзҫҺе‘ігҒ„гӮӮгҒ®гҒ«гҒӮгӮҠгҒӨгҒ‘гҒҹгҖҚгҒЁзҡҶгҒҢжәҖи¶ігҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒҹжҷӮгҒҜгҖҒз§ҒгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮд»•дәӢгҒ®гҒ—з”Іж–җгҖҠгҒ—гҒҢгҒ„гҖӢгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒЁжң¬еҪ“гҒ«е¬үгҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒжҲ–гӮӢж—ҘгҒқгҒ®зҫҺе‘ігҒқгҒҶгҒӘиҮӯгҒ„гӮ’е—…гҒҺгҒӨгҒ‘гҒҹиҝ‘жүҖгҒ®жңқй®®дәәгҒҢгҖҒгҖҢиҙ…жІўгҒӘгӮӮгҒ®гӮ’йЈҹгҒ№гҒҰгҒ„гӮӢгҖҚгҖҒгҖҢгҒ‘гҒ—гҒҢгӮүгӮ“еҘҙгҒҜиӘ°гҒ гҖҚгҒЁж—Ҙжң¬дәәдјҡгҒ«жҖ’йіҙгӮҠиҫјгӮ“гҒ§гҒҚгҒҹгҖҒгҒЁеҝ е‘ҠгҒ•гӮҢ唖然гҖҠгҒӮгҒңгӮ“гҖӢгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ
гҖҖгҖҢиҮӘеҲҶгҒ§зҚІгҒЈгҒҰгҒҚгҒҰеӢқжүӢгҒ«дҪңгҒЈгҒҰйЈҹгҒ№гҒҰдҪ•гҒӢжӮӘгҒ„гҖҚгҖҒгҖҢдёҖз·’гҒ«зҚІгӮҠгҒ«иЎҢгҒЈгҒҹеҸӢйҒ”гӮӮеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒ«йЈҹгҒ№гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ«гҖҒдҪ•ж•…еғ•гҒ гҒ‘гҖҚгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒж—Ҙжң¬дәәдјҡгҒ«иҝ·жғ‘гҒҢгҒӢгҒӢгҒЈгҒҰгӮӮгҒЁгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒҜе°‘гҒ—йҒ ж…®гҒ—гҒӘгҒҢгӮүгӮӮжјҒгҒҜз¶ҡгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
гҖҖгҒ“гҒҶгҒ—гҒҰиӣӢзҷҪиіӘгҖҠгҒҹгӮ“гҒұгҒҸгҒ—гҒӨгҖӢгҒҜйӯҡгҒ§ж‘ӮгӮҢгҖҒгғ“гӮҝгғҹгғіпјЈгӮӮе‘ЁгӮҠгҒ®йҮҺеұұгҒ§гғЁгғўгӮ®гӮ„йҮҺи’ңгӮ’еҸ–гҒЈгҒҰгҒҚгҒҰеӨҡе°‘гҒЁгӮӮж‘ӮеҸ–гҒ§гҒҚгҒҹгҒҢгҖҒдё»йЈҹгҒ®з©Җзү©гҒҜгҒ©гҒҶгҒ«гӮӮгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮд»•ж–№гҒҢгҒӘгҒ„гҒӢгӮүгҖҒжңқй®®дәәиҫІе®¶гҒ«иЎҢгҒЈгҒҰгҒҜгҖҢз”°жӨҚгҒҲгҖҒиҚүгӮҖгҒ—гӮҠгӮ’гӮ„гӮүгҒӣгҒҰж¬ІгҒ—гҒ„гҖӮжүӢй–“иіғгҒҜдҪ•гҒ§гӮӮгҒ„гҒ„гҒӢгӮүз©Җзү©гӮ’еҲҶгҒ‘гҒҰиІ°гҒ„гҒҹгҒ„гҖҚгҒЁгҖҢиҫІдҪңжҘӯгҒ®еЈІгӮҠиҫјгҒҝгҖҚгӮ’гҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҖӮжңҖеҲқгҒҜдҪ•еҮҰгҒёиЎҢгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгҒ«гҒ№гӮӮз„ЎгҒҸж–ӯгӮүгӮҢгӮӢгҒҢгҖҒзІҳгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁеӯҗдҫӣгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«еҗҢжғ…гҒҷгӮӢгҒ®гҒӢгҖҒе°‘гҒ—гҒҡгҒӨд»•дәӢгӮ’гҒҸгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҖҒзөӮгӮҸгӮӢгҒЁе°ҸгҒ•гҒӘиўӢгҒ«зЁ—гҖҠгҒІгҒҲгҖӢгғ»зІҹгӮ’гҖҒгҒҫгҒҹжҷӮгҒ«гҒҜзұігӮ’еҲҶгҒ‘гҒҰгҒҸгӮҢгҒҹгҖӮ
гҖҖдҪ•гӮ„гӮүд№һйЈҹгҒ®гӮҲгҒҶгҒ§гҖҒгҒЁиЁҖгҒҶгӮҲгӮҠе®ҹйҡӣгҒ«д№һйЈҹгҒӘгҒ®гҒ гҒҢгҖҒиҮӘеҲҶгҒ§гҒҜгҖҢеҠҙеғҚгӮ’еёҢжңӣгҒ—гҖҒеҜҫдҫЎгӮ’жұӮгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢгҖҚгҒӢгӮүгҖҢд№һйЈҹгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁиҮӘгӮүиЁҖгҒ„иҒһгҒӢгҒӣгҒҰеҠҙеғҚгҒ«еҠұгӮ“гҒ гҖӮгҒқгӮҢгҒ§гӮӮеҲқгӮҒгҒҜжҒҘгҒҡгҒӢгҒ—гҒҸгҒҰиЁҖи‘үгӮӮгғўгӮҫгғўгӮҪгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—йЈҹгҒ№гӮӢгҒҹгӮҒгҒӘгӮүгӮ„гӮҖгӮ’еҫ—гҒӘгҒ„гҖӮзҫһжҒҘгҖҠгҒЎгҒҳгӮҮгҒҸгҖӢеҝғгӮ’жҚЁгҒҰгӮӢгҒЁгҖҒеҫҢгҒҜгҒ”гҒҸиҮӘ然гҒ«гҖҢгҒҠйЎҳгҒ„гҒ—гҒҫгҒҷгҖҚгҒЁе…ғж°—иүҜгҒҸеЈ°гҒҢеҮәгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰеҸҺз©«гӮӮе°‘гҒ—гҒҡгҒӨеў—гҒҲгҖҒйЈҹз”ҹжҙ»гҒ®жүӢеҠ©гҒ‘гҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢиҮӘж…ўгҒ§гҒҷгӮүгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
--
з·ЁйӣҶиҖ… пјҲд»ЈзҗҶжҠ•зЁҝпјү