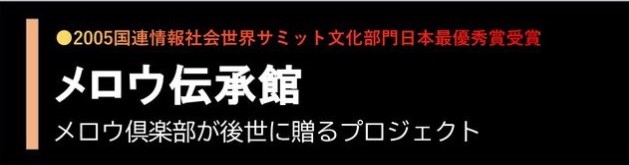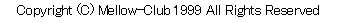гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј–) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„
жҠ•зЁҝгғ„гғӘгғј
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ пјңдёҖйғЁиӢұиЁігҒӮгӮҠпјһ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/4/28 7:38)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ пјңдёҖйғЁиӢұиЁігҒӮгӮҠпјһ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/4/28 7:38)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/4/29 7:43)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/4/29 7:43)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (3) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/4/30 6:49)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (3) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/4/30 6:49)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј”) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/1 7:21)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј”) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/1 7:21)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј•) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/2 8:31)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј•) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/2 8:31)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј–) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/3 7:38)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј–) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/3 7:38)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј—) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/4 8:37)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј—) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/4 8:37)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пјҳ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/5 7:51)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пјҳ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/5 7:51)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пјҷ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/6 8:12)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пјҷ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/6 8:12)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пјҗ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/7 7:47)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пјҗ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/7 7:47)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј‘) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/8 7:46)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј‘) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/8 7:46)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј’) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/9 5:57)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј’) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/9 5:57)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј“) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/20 10:17)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј“) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/20 10:17)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј”) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/21 9:32)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј”) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/21 9:32)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘5) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/22 8:44)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘5) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/22 8:44)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј–) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/23 8:05)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј–) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/23 8:05)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј—) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/24 7:23)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј—) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/24 7:23)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пјҳ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/25 7:34)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пјҳ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/25 7:34)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пјҷ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/26 6:51)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пјҷ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/26 6:51)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пјҗ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/27 7:27)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пјҗ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/27 7:27)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј‘) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/28 7:07)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј‘) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/28 7:07)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј’) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/29 7:36)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј’) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/29 7:36)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј“) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/30 7:39)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј“) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/30 7:39)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (24) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/31 15:39)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (24) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/31 15:39)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј•) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/1 7:56)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј•) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/1 7:56)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј–) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/2 6:56)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј–) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/2 6:56)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј—) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/3 7:22)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј—) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/3 7:22)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пјҳ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/4 7:19)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пјҳ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/4 7:19)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пјҷ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/5 8:04)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пјҷ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/5 8:04)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пјҗ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/6 7:43)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пјҗ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/6 7:43)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј‘) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/7 7:39)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј‘) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/7 7:39)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј’) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/8 8:21)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј’) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/8 8:21)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј“) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/9 7:20)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј“) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/9 7:20)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј”) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/10 8:08)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј”) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/10 8:08)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј•) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/11 7:53)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј•) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/11 7:53)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј–) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/12 7:54)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј–) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/12 7:54)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј—) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/13 7:15)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј—) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/13 7:15)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пјҳ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/14 7:59)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пјҳ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/14 7:59)
-
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пјҷ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/15 7:52)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пјҷ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/15 7:52)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј”пјҗ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/16 8:46)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј”пјҗ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/16 8:46)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј”пј‘гғ»жңҖзөӮеӣһ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/17 7:27)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј”пј‘гғ»жңҖзөӮеӣһ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/17 7:27)
-
гҒ“гҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜгҒ®жҠ•зЁҝдёҖиҰ§гҒё
- depth:
- 1
з·ЁйӣҶиҖ…
 еұ…дҪҸең°: гғЎгғӯгӮҰеҖ¶жҘҪйғЁ
жҠ•зЁҝж•°: 4298
еұ…дҪҸең°: гғЎгғӯгӮҰеҖ¶жҘҪйғЁ
жҠ•зЁҝж•°: 4298
 еұ…дҪҸең°: гғЎгғӯгӮҰеҖ¶жҘҪйғЁ
жҠ•зЁҝж•°: 4298
еұ…дҪҸең°: гғЎгғӯгӮҰеҖ¶жҘҪйғЁ
жҠ•зЁҝж•°: 4298
гҖҖгҒ„гӮҲгҒ„гӮҲжӯЈејҸгҒӘеј•жҸҡиҖ…гҒЁгҒ—гҒҰеё°йӮ„гҒ®йҖ”гҒ«
гҖҖдёүйҖұй–“гӮ’йҒҺгҒ”гҒ—гҒҹиӯ°ж”ҝеәңгҖҠгӮҰгӮӨгӮёгғ§гғігғ—гҖӢгӮӮеҗҚж®ӢжғңгҒ—гҒ„гҒҢгҖҒеҝғгҒҜгӮӮгҒҶдҪҗдё–дҝқгҒ«йЈӣгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮжқҘгҒҹгҒЁгҒҚгҒЁеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒ«гғҲгғ©гғғгӮҜгҒ«д№—гҒӣгӮүгӮҢгӮӢгҒЁеҶҚгҒід»Ғе·қгҖҠгӮӨгғігғҒгғ§гғігҖӢгҒёгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—д»ҠеәҰгҒҜе…ҲзқҖгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹд»–гҒ®еӣЈдҪ“гӮӮдёҖз·’гҒ гҒӢгӮүи»ҠгҒ®ж•°гӮӮеӨҡгҒ„гҖӮз§ҒйҒ”гӮҲгӮҠеҫҢгҒ«е…ҘжүҖгҒ—гҒҹдәәйҒ”гӮ’ж®ӢгҒ—гҖҒзҙ„дәҢгҖҮгҖҮгҖҮдәәгҒҢдёҖж–үгҒ«д»Ғе·қгҒ«еҗ‘гҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖд»Ғе·қжёҜгҒ«гҒҜеҚ—жңқй®®гҒ®иҲ№гҒ«ж··гҒҳгҒЈгҒҰгҖҒгӮўгғЎгғӘгӮ«гҒ®еӣҪж——гӮ’гҒҜгҒҹгӮҒгҒӢгҒӣгҒҹи»ҚиүҰгӮ„иІЁзү©иҲ№гҒ®гҒ»гҒӢгҒ«гҖҒж—ҘгҒ®дёёгӮ’жҺІгҒ’гӮӢж—Ҙжң¬гҒ®иІЁзү©иҲ№гҒҢдәҢйҡ»иҰӢгҒҲгӮӢгҖӮиҲ№и…№гҒ®ж–Үеӯ—гҒӢгӮүдёҖйҡ»гҒҜгҖҢеӨ§д№…дёёгҖҚгҖҒгӮӮгҒҶдёҖйҡ»гҒҜгҖҢдҝЎжҙӢдёёгҖҚгҒЁиӘӯгӮҒгҒҹгҖӮгҒЁгӮӮгҒ«дә”гҖҮгҖҮгҖҮгғҲгғігҒ»гҒ©гҒ®гҒӮгҒҫгӮҠеӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгҒ„иІЁзү©иҲ№гҒ гҖӮ
гҖҖгҒҠжҳјгӮ’йҒҺгҒҺгӮӢй ғгҖҒз§ҒйҒ”гҒҜгҒ“гҒ®дәҢйҡ»гҒ®гҒҶгҒЎгҒ®еӨ§д№…дёёгҒ«д№—иҲ№гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒй Ҷз•ӘгҒ«д№—гӮҠиҫјгӮ“гҒ гҖӮ
гҖҖиҲ№гҒҜгӮ·гғігӮ°гғ«гғҮгғғгӮӯгғ»гғҖгғ–гғ«гғҸгғғгғҒгҒ®дёӯеһӢиІЁзү©иҲ№гҒ§гҖҒжҲ‘гҖ…гҒҢд№—гӮҠиҫјгӮ“гҒ жҷӮгҒ«гҒҜеҫҢйғЁгғҸгғғгғҒгҒ«д»ҠгҒҫгҒ§иҰӢгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӘгҒ„дәәйҒ”гҒҢж—ўгҒ«д№—иҲ№гҒ—гҒҰгҖҒгӮӮгҒҶеҜӣгҖҠгҒҸгҒӨгӮҚгҖӢгҒ„гҒ§гҒ„гҒҹгҖӮиҝ‘иҫәгҒ®еҸҺе®№жүҖгҒҜиӯ°ж”ҝеәңгҖҠгӮҰгӮӨгӮёгғ§гғігғ—гҖӢгҒ®д»–гҒ«гӮӮдҪ•з®ҮжүҖгҒӢгҒӮгҒЈгҒҹгҒӢгӮүгҖҒгҒқгҒЎгӮүгҒӢгӮүжқҘгҒҰе…ҲгҒ«д№—гӮҠиҫјгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮ
гҖҖдҪҗдё–дҝқеј•жҸҡжҸҙиӯ·еұҖгҖҠпјқеӣҪеӨ–гҒӢгӮүгҒ®еј•жҸҡиҖ…гӮ’еҠ©гҒ‘гӮӢеҪ№жүҖгҖӢгҒ®иЁҳйҢІгҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒеӨ§д№…дёёгҒҜдёүеӣӣд№қгҖҮдәәгӮ’д№—гҒӣгҒҰеҚҒжңҲеҚҒдә”ж—ҘгҒ«е…ҘжёҜгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҖҒжҲ‘гҖ…гҒ®еҸҺе®№жүҖд»ҘеӨ–гҒ®дәәйҒ”гҒҢпј‘пјҗпјҗпјҗдәәд»ҘдёҠд№—гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ
гҖҖеӨ§д№…дёёгҒҜжҲ‘гҖ…гӮ’йҒӢгӮ“гҒ гҒӮгҒЁгҖҒеӨ§йҖЈгҖҒгӮ·гғігӮ¬гғқгғјгғ«гҖҒдёӯеӣҪгғ»иғЎиҠҰеі¶гҒӘгҒ©гҒ«ж•°еӣһжҙҫйҒЈгҒ•гӮҢгҖҒеҗ„дәҢдәҢгҖҮгҖҮпҪһдёүдёғгҖҮгҖҮдәәгӮ’д№—гҒӣгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҖҒгҒ“гҒ®иҲ№гҒ®гӮӯгғЈгғ‘гӮ·гғҶгӮЈгғјгҖҠпјқеҸ—е®№еҠӣгҖӢгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҒ»гҒјжәҖиҲ№зҠ¶ж…ӢгҒ®д№—е“Ўж•°гҖҒгҒқгҒ—гҒҰз§ҒйҒ”家ж—ҸгҒҜгҒ“гҒ®дёүеӣӣд№қгҖҮдәәгҒ®дёӯгҒ®дә”дәәгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҖӮ
гҖҖеӣ гҒҝгҒ«гҒ“гҒ®е№ҙгҖҒд»Ғе·қгҒӢгӮүдҪҗдё–дҝқгҒёгҒ®еј•гҒҚжҸҡгҒ’гҒҜгҒ“гҒ®еӨ§д№…дёёгҒҢеҲқгӮҒгҒҰгҒ§гҖҒдёүж—ҘеҫҢгҒ®еҚҒжңҲеҚҒе…«ж—ҘгҒ«гҒҜд»Ғе·қгҒ§е§ҝгӮ’иҰӢгҒҹдҝЎжҙӢдёёгҒҢдәҢдёҖдә”дёғдәәгӮ’д№—гҒӣгҒҰе…ҘжёҜгҖҒзҝҢеҚҒд№қж—ҘгҒ«ж°ёйҢІдёёгҒҢдёҖд№қд№қдәҢдәәгҖҒй«ҳж „дёёгғ»дёүдә”еӣӣгҖҮдәәгҖҒдәҢеҚҒдәҢж—ҘгҒ«зҶҠйҮҺдёёгғ»дёүдә”дёүдә”дәәгҖҒдәҢеҚҒдёғж—ҘгҒ«зұіеұұдёёгғ»дәҢе…ӯе…ӯе…ӯдәәгҖҒдёүеҚҒдёҖж—Ҙгғ»пјұпјҷпј•гғ»дёҖдәҢгҖҮдәҢдәәгҖҒеҚҒдёҖжңҲдәҢж—Ҙгғ»иҫ°ж—Ҙдёёгғ»дёүд№қдёғе…ӯдәәгҒӘгҒ©гҖҒд»Ғе·қпјҚдҪҗдё–дҝқй–“гҒ®еј•жҸҡиҖ…ијёйҖҒгҒҜгҒ“гҒ®гғӢгӮұжңҲй–“гҒ«йӣҶдёӯгҒ—гҒҰиЎҢгӮҸгӮҢгҖҒеҗҲиЁҲзҙ„дәҢдәҢдә”гҖҮгҖҮдәәгҒҢйҒӢгҒ°гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖгҒӘгҒҠжңқй®®й–ўдҝӮгҒҜйҮңеұұгҖҠгғ—гӮөгғігҖӢгҒӢгӮүгӮӮе…ҘжёҜгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒдёҖйҡ»еҪ“гҒҹгӮҠгҒ®дәәж•°гҒҜжҘөгӮҒгҒҰе°‘гҒӘгҒҸгҖҒеӨ§еҚҠгҒҜй–ўй–ҖгҖҒеҚҡеӨҡгҒёгҒ®е…ҘжёҜгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒҫгҒҹжңқй®®жқұеІёгҒӢгӮүгҒҜиҲһй¶ҙгҖҠгҒҫгҒ„гҒҡгӮӢгҖӢгҒҢеӨҡгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒӢгӮҚгҒҶгҒӢгҖӮ
гҖҖгҖҢе…·еҗҲгҒ®жӮӘгҒ„ж–№гҒҜж•‘иӯ·е®ӨгӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҰгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒӢгӮүгҖҒз”ігҒ—еҮәгҒҰдёӢгҒ•гҒ„гҖҚгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҖҒж•°дәәгҒҜгҒқгҒЎгӮүгҒёе…ҘгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒжҲ‘гҖ…гҒҜиІЁзү©гҒЁеҗҢгҒҳжүұгҒ„гҒ§еүҚж–№гҒ®гғҸгғғгғҒгҒ«иӘҳе°ҺгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ
гҖҖж·ұгҒ„иҲ№иүҷгҖҠгҒӣгӮ“гҒқгҒҶгҖӢгҒ®еҫҢйғЁгҒ«е·ҰиҲ·гҒӢгӮүеҸіиҲ·гҖҠгҒҶгҒ’гӮ“пјқеҸіеҒҙгҒ®иҲ№гҒ№гӮҠгҖӢгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰд»®иЁӯгҒ•гӮҢгҒҹжўҜеӯҗгҖҠгҒҜгҒ—гҒ”гҖӢйҡҺж®өгӮ’дјқгҒЈгҒҰйҷҚгӮҠгӮӢгҒЁгҖҒгҒқгҒ“гҒҜи–„жҡ—гҒҸгҒҰгҖҒгҒҫгӮӢгҒ§еӨ§гҒҚгҒӘжҙһз©ҙгҒ«е…ҘгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒӘж°—еҲҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжҲ‘гҖ…гҒ®дёҖеӣЈгҒҜгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘зәҸгҖҠгҒҫгҒЁгҖӢгҒҫгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰгҖҒз§ҒйҒ”家ж—ҸгҒҜзңҹдёӯгҒӮгҒҹгӮҠгҒ«еұ…е ҙжүҖгӮ’зўәдҝқгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒдҪ•гҒӣеӨ§еӢўгҒ гҒӢгӮүе…Ёе“ЎгҒҢжЁӘгҒ«гҒӘгӮӢгҒ гҒ‘гҒ®гӮ№гғҡгғјгӮ№гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгҒҫгҒӮдёҖж—ҘгҒ гҒ‘гҒ®гҒ“гҒЁгҒ гҒ—гҖҒгҖҖгҖҢжҳҺж—ҘгҒҜгҒ„гӮҲгҒ„гӮҲж—Ҙжң¬гҒЁгҒӘгӮҢгҒ°е°‘гҖ…зӘ®еұҲгҖҠгҒҚгӮ…гҒҶгҒҸгҒӨгҖӢгҒ§гӮӮжҲ‘ж…ўгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҚгҒЁеә§гӮҠиҫјгӮ“гҒ гҖӮ
гҖҖеӨҡзҚ…еі¶гӮ’еҮәгҒҹгҒЁгҒҚгҒҜи„ұиө°иҖ…гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒеҗҢгҒҳиҲ№ж—…гҒ§гӮӮд»ҠеәҰгҒҜеёҢжңӣгҒҢзӣҙгҒҗгҒқгҒ“гҒ«гҒӮгӮӢжӯЈејҸгҒӘеё°йӮ„иҖ…гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮзӘ®еұҲгҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒж–Үеӯ—йҖҡгӮҠгҖҢеӨ§иҲ№гҒ«д№—гҒЈгҒҰгҖҚгҒ®жңҖеҫҢгҒ®ж—…гҒҢгҒ„гҒҫе§ӢгҒҫгӮҚгҒҶгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҖӮгҒҝгҒӘдёҖж§ҳгҒ«иҲҲеҘ®гҖҠгҒ“гҒҶгҒөгӮ“гҖӢгҒ—гҒҹйқўжҢҒгҒЎгҒ§гҖҒд»ҠжңқгҒӢгӮүгҒ®з§»еӢ•гҒ®з–ІгӮҢгӮӮеҝҳгӮҢгҒҰйҡЈиҝ‘жүҖгҒ®дәәйҒ”гҒЁи©ұгҒ—еҗҲгҒ„гҖҒгҒҫгҒҹгӮёгғғгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒЁз«ӢгҒЈгҒҹгӮҠеә§гҒЈгҒҹгӮҠгҒ§гҖҒйЁ’гҖ…гҖҠгҒқгҒҶгҒһгҒҶгҖӢгҒ—гҒ„гҒ“гҒЁеӨҘгҖҠгҒҜгҒӘгҒҜгҒ гҖӢгҒ—гҒ„гҖӮ
гҖҖжҡ«гҒҸгҒҜиі‘гҖҠгҒ«гҒҺгҖӢгӮ„гҒӢгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒе…ЁгҒҰгҒ®дәәйҒ”гҒҢд№—иҲ№гҒ—зөӮгҒҲгӮӢй ғгҒ«гҒҜиҲ№еҶ…гӮӮйқҷгҒӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ
гҖҖеӨ–гҒ®ж§ҳеӯҗгӮӮиүҜгҒҸгҒҜгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒиҲ№е“ЎгҒ®еӢ•гҒҚгӮ„еЈ°гҒӢгӮүгҒҷгӮӢгҒЁеҮәиҲӘжә–еӮҷгҒҢе§ӢгҒҫгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖгӮҝгғ©гғғгғ—гҒҢеӨ–гҒ•гӮҢгҖҒиҲ«гҖҠгҒ»гҒҶгҖӢгҒҢи§ЈгҒӢгӮҢгӮӢйҹігҒҢиҒһгҒ“гҒҲгҖҒгӮЁгғігӮёгғігҒ®йҹҝгҒҚгӮӮе°‘гҒ—еӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮ
гҖҖгҖҢгҒ„гӮҲгҒ„гӮҲжҳҺж—ҘгҒҜгҖҺеҶ…ең°гҖҸгҒ гҒӘгҖҚгҒ—гҒҝгҒҳгҒҝгҒЁгҒ—гҒҹзҲ¶гҒ®иЁҖи‘үгҒ«гҒҜгҖҒгҖҢиҫӣгҒӢгҒЈгҒҹгҒ‘гҒ©гӮҲгҒҶгӮ„гҒҸгҒ“гҒ“гҒҫгҒ§иҫҝгҖҠгҒҹгҒ©гҖӢгӮҠзқҖгҒ‘гҒҹгҖӮдёҖжҷӮгҒҜзө¶жңӣгҒ—гҒҹе№ёйҒӢгӮ’иҮӘеҲҶйҒ”гҒҜгҒ„гҒҫжҺҙгҖҠгҒӨгҒӢгҖӢгӮӮгҒҶгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҝғгҒӢгӮүгҒ®е–ңгҒігҒЁгҖҒгҖҢжҲҰдәүгҒ®зңҹгҒЈгҒҹгҒ дёӯгҖҒеӨ–ең°гҒ«йҖЈгӮҢеҮәгҒ—гҒҹ家ж—ҸгӮ’дёҖдәәгӮӮеӨұгҒҸгҒҷгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸгҖҒдҪ•гҒЁгҒӢгҒ“гҒҶгҒ—гҒҰйҖЈгӮҢгҒҰеё°гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶ家長гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®е®үе өж„ҹгҒҢгҒӮгҒөгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
гҖҖгҖҢгҒ“гҒҶгҒ—гҒҰзҡҶгҒҢе…ғж°—гҒ§дёҖз·’гҒ«её°гӮҢгӮӢгҒЁгҒҜгҒӯгҖӮеӨўиҰӢгҒҹгҒ„гҖҚгӮ„гҒӨгӮҢгҒҹжҜҚгҒ®йЎ”гҒ«гӮӮгҖҒз©ҸгӮ„гҒӢгҒӘ笑гҒҝгҒҢжө®гҒӢгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖжҖқгҒ„иө·гҒ“гҒҷгҒЁгҖҒж—Ҙжң¬еҶ…ең°гӮ’йӣўгӮҢгҒҹгҒ®гҒҢгҒЎгӮҮгҒҶгҒ©дёүе№ҙеүҚгҒ®жҳӯе’ҢеҚҒе…«е№ҙд№қжңҲгҖҒгҒӮгҒ®жҷӮгҒҜй–ўйҮңгҖҠгҒӢгӮ“гҒ·гҖӢйҖЈзөЎиҲ№гғ»иҲҲе®үдёёгҖҠгҒ“гҒҶгҒӮгӮ“гҒҫгӮӢгҖӢгҒ®дәҢзӯүиҲ№е®ӨгҖҒеӨӘе№іжҙӢжҲҰдәүгӮӮзңҹгҒЈгҒҹгҒ дёӯгҒ§гҖҒдёҚе®үж··гҒҳгӮҠгҒЁгҒҜгҒ„гҒҲе„Әйӣ…гҒӘиҲ№ж—…гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒ«еј•гҒҚгҒӢгҒҲгҖҒд»ҠгҒҜиІЁзү©иҲ№гҒ®иҲ№еә•гҒ«зқҖгҒ®иә«зқҖгҒ®гҒҫгҒҫгҒ®и–„жұҡгӮҢгҒҹе§ҝгҒ§иҶқгҖҠгҒІгҒ–гҖӢгӮ’жҠұгҒҲгҒҰеә§гӮҠиҫјгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮеӨ§гҒҚгҒӘйҒ•гҒ„гҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒиЁҖи‘үгҒ«гҒ„гҒ„е°ҪгҒҸгҒӣгҒ¬гҖҢеӨ–ең°гҖҚгҒ§гҒ®иӢҰйӣЈгҒӢгӮүгӮҲгҒҶгӮ„гҒҸи§Јж”ҫгҒ•гӮҢгҖҒжҳҺж—ҘгҒӢгӮүгҒҜж•…еӣҪгғ»ж—Ҙжң¬гҒ§гҒ®ж–°гҒ—гҒ„з”ҹжҙ»гҒҢеҫ…гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеҶ…ең°гӮӮгҒІгҒ©гҒ„зҠ¶ж…ӢгҒЁгҒҜиҒһгҒ„гҒҰгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒгҒ“гҒ®дёҖе№ҙгҒ®иҫӣй…ёгҖҠгҒ—гӮ“гҒ•гӮ“пјқиӢҰгҒ„зөҢйЁ“гҖӢгӮ’иҖғгҒҲгӮҢгҒ°дҪ•гҒ®гҒ“гҒЁгӮӮгҒӘгҒӢгӮҚгҒҶгҖӮгҒЁгҒ«гӮӮгҒӢгҒҸгҒ«гӮӮгҖҒгҖҢдёҖеҲ»гӮӮж—©гҒҸж•…йғ·гҒ®еңҹгӮ’иёҸгҒҝгҒҹгҒ„гҖҒгҒқгҒ—гҒҰжҳҺж—ҘгҒҜгҒқгҒ®еңҹгҒ®гҒӮгӮӢдҪҗдё–дҝқгҒӘгҒ®гҒ гҖҚгҖҒжҳӮгҖҠгҒҹгҒӢгҖӢгҒ¶гӮӢж°—жҢҒгҒЎгӮ’жҠ‘гҒҲгҒҰеҷӮгҖҠгҒ—гӮ„гҒ№гҖӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҶгҒЎгҒ«иҲ№гҒҜжұҪз¬ӣгӮ’йіҙгӮүгҒ—гҒҰеӢ•гҒҚе§ӢгӮҒгҒҹгҖӮ
гҖҖдёүйҖұй–“гӮ’йҒҺгҒ”гҒ—гҒҹиӯ°ж”ҝеәңгҖҠгӮҰгӮӨгӮёгғ§гғігғ—гҖӢгӮӮеҗҚж®ӢжғңгҒ—гҒ„гҒҢгҖҒеҝғгҒҜгӮӮгҒҶдҪҗдё–дҝқгҒ«йЈӣгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮжқҘгҒҹгҒЁгҒҚгҒЁеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒ«гғҲгғ©гғғгӮҜгҒ«д№—гҒӣгӮүгӮҢгӮӢгҒЁеҶҚгҒід»Ғе·қгҖҠгӮӨгғігғҒгғ§гғігҖӢгҒёгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—д»ҠеәҰгҒҜе…ҲзқҖгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹд»–гҒ®еӣЈдҪ“гӮӮдёҖз·’гҒ гҒӢгӮүи»ҠгҒ®ж•°гӮӮеӨҡгҒ„гҖӮз§ҒйҒ”гӮҲгӮҠеҫҢгҒ«е…ҘжүҖгҒ—гҒҹдәәйҒ”гӮ’ж®ӢгҒ—гҖҒзҙ„дәҢгҖҮгҖҮгҖҮдәәгҒҢдёҖж–үгҒ«д»Ғе·қгҒ«еҗ‘гҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖд»Ғе·қжёҜгҒ«гҒҜеҚ—жңқй®®гҒ®иҲ№гҒ«ж··гҒҳгҒЈгҒҰгҖҒгӮўгғЎгғӘгӮ«гҒ®еӣҪж——гӮ’гҒҜгҒҹгӮҒгҒӢгҒӣгҒҹи»ҚиүҰгӮ„иІЁзү©иҲ№гҒ®гҒ»гҒӢгҒ«гҖҒж—ҘгҒ®дёёгӮ’жҺІгҒ’гӮӢж—Ҙжң¬гҒ®иІЁзү©иҲ№гҒҢдәҢйҡ»иҰӢгҒҲгӮӢгҖӮиҲ№и…№гҒ®ж–Үеӯ—гҒӢгӮүдёҖйҡ»гҒҜгҖҢеӨ§д№…дёёгҖҚгҖҒгӮӮгҒҶдёҖйҡ»гҒҜгҖҢдҝЎжҙӢдёёгҖҚгҒЁиӘӯгӮҒгҒҹгҖӮгҒЁгӮӮгҒ«дә”гҖҮгҖҮгҖҮгғҲгғігҒ»гҒ©гҒ®гҒӮгҒҫгӮҠеӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгҒ„иІЁзү©иҲ№гҒ гҖӮ
гҖҖгҒҠжҳјгӮ’йҒҺгҒҺгӮӢй ғгҖҒз§ҒйҒ”гҒҜгҒ“гҒ®дәҢйҡ»гҒ®гҒҶгҒЎгҒ®еӨ§д№…дёёгҒ«д№—иҲ№гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒй Ҷз•ӘгҒ«д№—гӮҠиҫјгӮ“гҒ гҖӮ
гҖҖиҲ№гҒҜгӮ·гғігӮ°гғ«гғҮгғғгӮӯгғ»гғҖгғ–гғ«гғҸгғғгғҒгҒ®дёӯеһӢиІЁзү©иҲ№гҒ§гҖҒжҲ‘гҖ…гҒҢд№—гӮҠиҫјгӮ“гҒ жҷӮгҒ«гҒҜеҫҢйғЁгғҸгғғгғҒгҒ«д»ҠгҒҫгҒ§иҰӢгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӘгҒ„дәәйҒ”гҒҢж—ўгҒ«д№—иҲ№гҒ—гҒҰгҖҒгӮӮгҒҶеҜӣгҖҠгҒҸгҒӨгӮҚгҖӢгҒ„гҒ§гҒ„гҒҹгҖӮиҝ‘иҫәгҒ®еҸҺе®№жүҖгҒҜиӯ°ж”ҝеәңгҖҠгӮҰгӮӨгӮёгғ§гғігғ—гҖӢгҒ®д»–гҒ«гӮӮдҪ•з®ҮжүҖгҒӢгҒӮгҒЈгҒҹгҒӢгӮүгҖҒгҒқгҒЎгӮүгҒӢгӮүжқҘгҒҰе…ҲгҒ«д№—гӮҠиҫјгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮ
гҖҖдҪҗдё–дҝқеј•жҸҡжҸҙиӯ·еұҖгҖҠпјқеӣҪеӨ–гҒӢгӮүгҒ®еј•жҸҡиҖ…гӮ’еҠ©гҒ‘гӮӢеҪ№жүҖгҖӢгҒ®иЁҳйҢІгҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒеӨ§д№…дёёгҒҜдёүеӣӣд№қгҖҮдәәгӮ’д№—гҒӣгҒҰеҚҒжңҲеҚҒдә”ж—ҘгҒ«е…ҘжёҜгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҖҒжҲ‘гҖ…гҒ®еҸҺе®№жүҖд»ҘеӨ–гҒ®дәәйҒ”гҒҢпј‘пјҗпјҗпјҗдәәд»ҘдёҠд№—гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ
гҖҖеӨ§д№…дёёгҒҜжҲ‘гҖ…гӮ’йҒӢгӮ“гҒ гҒӮгҒЁгҖҒеӨ§йҖЈгҖҒгӮ·гғігӮ¬гғқгғјгғ«гҖҒдёӯеӣҪгғ»иғЎиҠҰеі¶гҒӘгҒ©гҒ«ж•°еӣһжҙҫйҒЈгҒ•гӮҢгҖҒеҗ„дәҢдәҢгҖҮгҖҮпҪһдёүдёғгҖҮгҖҮдәәгӮ’д№—гҒӣгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҖҒгҒ“гҒ®иҲ№гҒ®гӮӯгғЈгғ‘гӮ·гғҶгӮЈгғјгҖҠпјқеҸ—е®№еҠӣгҖӢгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҒ»гҒјжәҖиҲ№зҠ¶ж…ӢгҒ®д№—е“Ўж•°гҖҒгҒқгҒ—гҒҰз§ҒйҒ”家ж—ҸгҒҜгҒ“гҒ®дёүеӣӣд№қгҖҮдәәгҒ®дёӯгҒ®дә”дәәгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҖӮ
гҖҖеӣ гҒҝгҒ«гҒ“гҒ®е№ҙгҖҒд»Ғе·қгҒӢгӮүдҪҗдё–дҝқгҒёгҒ®еј•гҒҚжҸҡгҒ’гҒҜгҒ“гҒ®еӨ§д№…дёёгҒҢеҲқгӮҒгҒҰгҒ§гҖҒдёүж—ҘеҫҢгҒ®еҚҒжңҲеҚҒе…«ж—ҘгҒ«гҒҜд»Ғе·қгҒ§е§ҝгӮ’иҰӢгҒҹдҝЎжҙӢдёёгҒҢдәҢдёҖдә”дёғдәәгӮ’д№—гҒӣгҒҰе…ҘжёҜгҖҒзҝҢеҚҒд№қж—ҘгҒ«ж°ёйҢІдёёгҒҢдёҖд№қд№қдәҢдәәгҖҒй«ҳж „дёёгғ»дёүдә”еӣӣгҖҮдәәгҖҒдәҢеҚҒдәҢж—ҘгҒ«зҶҠйҮҺдёёгғ»дёүдә”дёүдә”дәәгҖҒдәҢеҚҒдёғж—ҘгҒ«зұіеұұдёёгғ»дәҢе…ӯе…ӯе…ӯдәәгҖҒдёүеҚҒдёҖж—Ҙгғ»пјұпјҷпј•гғ»дёҖдәҢгҖҮдәҢдәәгҖҒеҚҒдёҖжңҲдәҢж—Ҙгғ»иҫ°ж—Ҙдёёгғ»дёүд№қдёғе…ӯдәәгҒӘгҒ©гҖҒд»Ғе·қпјҚдҪҗдё–дҝқй–“гҒ®еј•жҸҡиҖ…ијёйҖҒгҒҜгҒ“гҒ®гғӢгӮұжңҲй–“гҒ«йӣҶдёӯгҒ—гҒҰиЎҢгӮҸгӮҢгҖҒеҗҲиЁҲзҙ„дәҢдәҢдә”гҖҮгҖҮдәәгҒҢйҒӢгҒ°гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖгҒӘгҒҠжңқй®®й–ўдҝӮгҒҜйҮңеұұгҖҠгғ—гӮөгғігҖӢгҒӢгӮүгӮӮе…ҘжёҜгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒдёҖйҡ»еҪ“гҒҹгӮҠгҒ®дәәж•°гҒҜжҘөгӮҒгҒҰе°‘гҒӘгҒҸгҖҒеӨ§еҚҠгҒҜй–ўй–ҖгҖҒеҚҡеӨҡгҒёгҒ®е…ҘжёҜгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒҫгҒҹжңқй®®жқұеІёгҒӢгӮүгҒҜиҲһй¶ҙгҖҠгҒҫгҒ„гҒҡгӮӢгҖӢгҒҢеӨҡгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒӢгӮҚгҒҶгҒӢгҖӮ
гҖҖгҖҢе…·еҗҲгҒ®жӮӘгҒ„ж–№гҒҜж•‘иӯ·е®ӨгӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҰгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒӢгӮүгҖҒз”ігҒ—еҮәгҒҰдёӢгҒ•гҒ„гҖҚгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҖҒж•°дәәгҒҜгҒқгҒЎгӮүгҒёе…ҘгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒжҲ‘гҖ…гҒҜиІЁзү©гҒЁеҗҢгҒҳжүұгҒ„гҒ§еүҚж–№гҒ®гғҸгғғгғҒгҒ«иӘҳе°ҺгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ
гҖҖж·ұгҒ„иҲ№иүҷгҖҠгҒӣгӮ“гҒқгҒҶгҖӢгҒ®еҫҢйғЁгҒ«е·ҰиҲ·гҒӢгӮүеҸіиҲ·гҖҠгҒҶгҒ’гӮ“пјқеҸіеҒҙгҒ®иҲ№гҒ№гӮҠгҖӢгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰд»®иЁӯгҒ•гӮҢгҒҹжўҜеӯҗгҖҠгҒҜгҒ—гҒ”гҖӢйҡҺж®өгӮ’дјқгҒЈгҒҰйҷҚгӮҠгӮӢгҒЁгҖҒгҒқгҒ“гҒҜи–„жҡ—гҒҸгҒҰгҖҒгҒҫгӮӢгҒ§еӨ§гҒҚгҒӘжҙһз©ҙгҒ«е…ҘгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒӘж°—еҲҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжҲ‘гҖ…гҒ®дёҖеӣЈгҒҜгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘зәҸгҖҠгҒҫгҒЁгҖӢгҒҫгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰгҖҒз§ҒйҒ”家ж—ҸгҒҜзңҹдёӯгҒӮгҒҹгӮҠгҒ«еұ…е ҙжүҖгӮ’зўәдҝқгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒдҪ•гҒӣеӨ§еӢўгҒ гҒӢгӮүе…Ёе“ЎгҒҢжЁӘгҒ«гҒӘгӮӢгҒ гҒ‘гҒ®гӮ№гғҡгғјгӮ№гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгҒҫгҒӮдёҖж—ҘгҒ гҒ‘гҒ®гҒ“гҒЁгҒ гҒ—гҖҒгҖҖгҖҢжҳҺж—ҘгҒҜгҒ„гӮҲгҒ„гӮҲж—Ҙжң¬гҒЁгҒӘгӮҢгҒ°е°‘гҖ…зӘ®еұҲгҖҠгҒҚгӮ…гҒҶгҒҸгҒӨгҖӢгҒ§гӮӮжҲ‘ж…ўгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҚгҒЁеә§гӮҠиҫјгӮ“гҒ гҖӮ
гҖҖеӨҡзҚ…еі¶гӮ’еҮәгҒҹгҒЁгҒҚгҒҜи„ұиө°иҖ…гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒеҗҢгҒҳиҲ№ж—…гҒ§гӮӮд»ҠеәҰгҒҜеёҢжңӣгҒҢзӣҙгҒҗгҒқгҒ“гҒ«гҒӮгӮӢжӯЈејҸгҒӘеё°йӮ„иҖ…гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮзӘ®еұҲгҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒж–Үеӯ—йҖҡгӮҠгҖҢеӨ§иҲ№гҒ«д№—гҒЈгҒҰгҖҚгҒ®жңҖеҫҢгҒ®ж—…гҒҢгҒ„гҒҫе§ӢгҒҫгӮҚгҒҶгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҖӮгҒҝгҒӘдёҖж§ҳгҒ«иҲҲеҘ®гҖҠгҒ“гҒҶгҒөгӮ“гҖӢгҒ—гҒҹйқўжҢҒгҒЎгҒ§гҖҒд»ҠжңқгҒӢгӮүгҒ®з§»еӢ•гҒ®з–ІгӮҢгӮӮеҝҳгӮҢгҒҰйҡЈиҝ‘жүҖгҒ®дәәйҒ”гҒЁи©ұгҒ—еҗҲгҒ„гҖҒгҒҫгҒҹгӮёгғғгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒЁз«ӢгҒЈгҒҹгӮҠеә§гҒЈгҒҹгӮҠгҒ§гҖҒйЁ’гҖ…гҖҠгҒқгҒҶгҒһгҒҶгҖӢгҒ—гҒ„гҒ“гҒЁеӨҘгҖҠгҒҜгҒӘгҒҜгҒ гҖӢгҒ—гҒ„гҖӮ
гҖҖжҡ«гҒҸгҒҜиі‘гҖҠгҒ«гҒҺгҖӢгӮ„гҒӢгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒе…ЁгҒҰгҒ®дәәйҒ”гҒҢд№—иҲ№гҒ—зөӮгҒҲгӮӢй ғгҒ«гҒҜиҲ№еҶ…гӮӮйқҷгҒӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ
гҖҖеӨ–гҒ®ж§ҳеӯҗгӮӮиүҜгҒҸгҒҜгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒиҲ№е“ЎгҒ®еӢ•гҒҚгӮ„еЈ°гҒӢгӮүгҒҷгӮӢгҒЁеҮәиҲӘжә–еӮҷгҒҢе§ӢгҒҫгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖгӮҝгғ©гғғгғ—гҒҢеӨ–гҒ•гӮҢгҖҒиҲ«гҖҠгҒ»гҒҶгҖӢгҒҢи§ЈгҒӢгӮҢгӮӢйҹігҒҢиҒһгҒ“гҒҲгҖҒгӮЁгғігӮёгғігҒ®йҹҝгҒҚгӮӮе°‘гҒ—еӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮ
гҖҖгҖҢгҒ„гӮҲгҒ„гӮҲжҳҺж—ҘгҒҜгҖҺеҶ…ең°гҖҸгҒ гҒӘгҖҚгҒ—гҒҝгҒҳгҒҝгҒЁгҒ—гҒҹзҲ¶гҒ®иЁҖи‘үгҒ«гҒҜгҖҒгҖҢиҫӣгҒӢгҒЈгҒҹгҒ‘гҒ©гӮҲгҒҶгӮ„гҒҸгҒ“гҒ“гҒҫгҒ§иҫҝгҖҠгҒҹгҒ©гҖӢгӮҠзқҖгҒ‘гҒҹгҖӮдёҖжҷӮгҒҜзө¶жңӣгҒ—гҒҹе№ёйҒӢгӮ’иҮӘеҲҶйҒ”гҒҜгҒ„гҒҫжҺҙгҖҠгҒӨгҒӢгҖӢгӮӮгҒҶгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҝғгҒӢгӮүгҒ®е–ңгҒігҒЁгҖҒгҖҢжҲҰдәүгҒ®зңҹгҒЈгҒҹгҒ дёӯгҖҒеӨ–ең°гҒ«йҖЈгӮҢеҮәгҒ—гҒҹ家ж—ҸгӮ’дёҖдәәгӮӮеӨұгҒҸгҒҷгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸгҖҒдҪ•гҒЁгҒӢгҒ“гҒҶгҒ—гҒҰйҖЈгӮҢгҒҰеё°гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶ家長гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®е®үе өж„ҹгҒҢгҒӮгҒөгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
гҖҖгҖҢгҒ“гҒҶгҒ—гҒҰзҡҶгҒҢе…ғж°—гҒ§дёҖз·’гҒ«её°гӮҢгӮӢгҒЁгҒҜгҒӯгҖӮеӨўиҰӢгҒҹгҒ„гҖҚгӮ„гҒӨгӮҢгҒҹжҜҚгҒ®йЎ”гҒ«гӮӮгҖҒз©ҸгӮ„гҒӢгҒӘ笑гҒҝгҒҢжө®гҒӢгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖжҖқгҒ„иө·гҒ“гҒҷгҒЁгҖҒж—Ҙжң¬еҶ…ең°гӮ’йӣўгӮҢгҒҹгҒ®гҒҢгҒЎгӮҮгҒҶгҒ©дёүе№ҙеүҚгҒ®жҳӯе’ҢеҚҒе…«е№ҙд№қжңҲгҖҒгҒӮгҒ®жҷӮгҒҜй–ўйҮңгҖҠгҒӢгӮ“гҒ·гҖӢйҖЈзөЎиҲ№гғ»иҲҲе®үдёёгҖҠгҒ“гҒҶгҒӮгӮ“гҒҫгӮӢгҖӢгҒ®дәҢзӯүиҲ№е®ӨгҖҒеӨӘе№іжҙӢжҲҰдәүгӮӮзңҹгҒЈгҒҹгҒ дёӯгҒ§гҖҒдёҚе®үж··гҒҳгӮҠгҒЁгҒҜгҒ„гҒҲе„Әйӣ…гҒӘиҲ№ж—…гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒ«еј•гҒҚгҒӢгҒҲгҖҒд»ҠгҒҜиІЁзү©иҲ№гҒ®иҲ№еә•гҒ«зқҖгҒ®иә«зқҖгҒ®гҒҫгҒҫгҒ®и–„жұҡгӮҢгҒҹе§ҝгҒ§иҶқгҖҠгҒІгҒ–гҖӢгӮ’жҠұгҒҲгҒҰеә§гӮҠиҫјгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮеӨ§гҒҚгҒӘйҒ•гҒ„гҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒиЁҖи‘үгҒ«гҒ„гҒ„е°ҪгҒҸгҒӣгҒ¬гҖҢеӨ–ең°гҖҚгҒ§гҒ®иӢҰйӣЈгҒӢгӮүгӮҲгҒҶгӮ„гҒҸи§Јж”ҫгҒ•гӮҢгҖҒжҳҺж—ҘгҒӢгӮүгҒҜж•…еӣҪгғ»ж—Ҙжң¬гҒ§гҒ®ж–°гҒ—гҒ„з”ҹжҙ»гҒҢеҫ…гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеҶ…ең°гӮӮгҒІгҒ©гҒ„зҠ¶ж…ӢгҒЁгҒҜиҒһгҒ„гҒҰгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒгҒ“гҒ®дёҖе№ҙгҒ®иҫӣй…ёгҖҠгҒ—гӮ“гҒ•гӮ“пјқиӢҰгҒ„зөҢйЁ“гҖӢгӮ’иҖғгҒҲгӮҢгҒ°дҪ•гҒ®гҒ“гҒЁгӮӮгҒӘгҒӢгӮҚгҒҶгҖӮгҒЁгҒ«гӮӮгҒӢгҒҸгҒ«гӮӮгҖҒгҖҢдёҖеҲ»гӮӮж—©гҒҸж•…йғ·гҒ®еңҹгӮ’иёҸгҒҝгҒҹгҒ„гҖҒгҒқгҒ—гҒҰжҳҺж—ҘгҒҜгҒқгҒ®еңҹгҒ®гҒӮгӮӢдҪҗдё–дҝқгҒӘгҒ®гҒ гҖҚгҖҒжҳӮгҖҠгҒҹгҒӢгҖӢгҒ¶гӮӢж°—жҢҒгҒЎгӮ’жҠ‘гҒҲгҒҰеҷӮгҖҠгҒ—гӮ„гҒ№гҖӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҶгҒЎгҒ«иҲ№гҒҜжұҪз¬ӣгӮ’йіҙгӮүгҒ—гҒҰеӢ•гҒҚе§ӢгӮҒгҒҹгҖӮ
--
з·ЁйӣҶиҖ… пјҲд»ЈзҗҶжҠ•зЁҝпјү