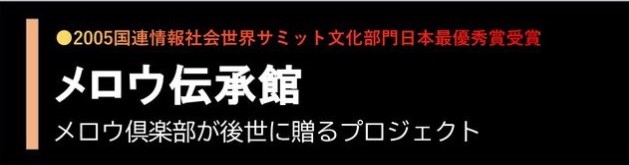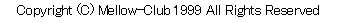チョッパリの邑 (37) 椎野 公雄
投稿ツリー
-
 チョッパリの邑 (1) 椎野 公雄 <一部英訳あり> (編集者, 2007/4/28 7:38)
チョッパリの邑 (1) 椎野 公雄 <一部英訳あり> (編集者, 2007/4/28 7:38)
-
 チョッパリの邑 (2) 椎野 公雄 (編集者, 2007/4/29 7:43)
チョッパリの邑 (2) 椎野 公雄 (編集者, 2007/4/29 7:43)
-
 チョッパリの邑 (3) 椎野 公雄 (編集者, 2007/4/30 6:49)
チョッパリの邑 (3) 椎野 公雄 (編集者, 2007/4/30 6:49)
-
 チョッパリの邑 (4) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/1 7:21)
チョッパリの邑 (4) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/1 7:21)
-
 チョッパリの邑 (5) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/2 8:31)
チョッパリの邑 (5) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/2 8:31)
-
 チョッパリの邑 (6) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/3 7:38)
チョッパリの邑 (6) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/3 7:38)
-
 チョッパリの邑 (7) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/4 8:37)
チョッパリの邑 (7) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/4 8:37)
-
 チョッパリの邑 (8) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/5 7:51)
チョッパリの邑 (8) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/5 7:51)
-
 チョッパリの邑 (9) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/6 8:12)
チョッパリの邑 (9) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/6 8:12)
-
 チョッパリの邑 (10) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/7 7:47)
チョッパリの邑 (10) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/7 7:47)
-
 チョッパリの邑 (11) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/8 7:46)
チョッパリの邑 (11) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/8 7:46)
-
 チョッパリの邑 (12) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/9 5:57)
チョッパリの邑 (12) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/9 5:57)
-
 チョッパリの邑 (13) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/20 10:17)
チョッパリの邑 (13) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/20 10:17)
-
 チョッパリの邑 (14) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/21 9:32)
チョッパリの邑 (14) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/21 9:32)
-
 チョッパリの邑 (15) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/22 8:44)
チョッパリの邑 (15) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/22 8:44)
-
 チョッパリの邑 (16) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/23 8:05)
チョッパリの邑 (16) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/23 8:05)
-
 チョッパリの邑 (17) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/24 7:23)
チョッパリの邑 (17) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/24 7:23)
-
 チョッパリの邑 (18) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/25 7:34)
チョッパリの邑 (18) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/25 7:34)
-
 チョッパリの邑 (19) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/26 6:51)
チョッパリの邑 (19) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/26 6:51)
-
 チョッパリの邑 (20) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/27 7:27)
チョッパリの邑 (20) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/27 7:27)
-
 チョッパリの邑 (21) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/28 7:07)
チョッパリの邑 (21) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/28 7:07)
-
 チョッパリの邑 (22) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/29 7:36)
チョッパリの邑 (22) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/29 7:36)
-
 チョッパリの邑 (23) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/30 7:39)
チョッパリの邑 (23) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/30 7:39)
-
 チョッパリの邑 (24) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/31 15:39)
チョッパリの邑 (24) 椎野 公雄 (編集者, 2007/5/31 15:39)
-
 チョッパリの邑 (25) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/1 7:56)
チョッパリの邑 (25) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/1 7:56)
-
 チョッパリの邑 (26) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/2 6:56)
チョッパリの邑 (26) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/2 6:56)
-
 チョッパリの邑 (27) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/3 7:22)
チョッパリの邑 (27) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/3 7:22)
-
 チョッパリの邑 (28) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/4 7:19)
チョッパリの邑 (28) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/4 7:19)
-
 チョッパリの邑 (29) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/5 8:04)
チョッパリの邑 (29) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/5 8:04)
-
 チョッパリの邑 (30) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/6 7:43)
チョッパリの邑 (30) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/6 7:43)
-
 チョッパリの邑 (31) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/7 7:39)
チョッパリの邑 (31) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/7 7:39)
-
 チョッパリの邑 (32) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/8 8:21)
チョッパリの邑 (32) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/8 8:21)
-
 チョッパリの邑 (33) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/9 7:20)
チョッパリの邑 (33) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/9 7:20)
-
 チョッパリの邑 (34) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/10 8:08)
チョッパリの邑 (34) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/10 8:08)
-
 チョッパリの邑 (35) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/11 7:53)
チョッパリの邑 (35) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/11 7:53)
-
 チョッパリの邑 (36) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/12 7:54)
チョッパリの邑 (36) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/12 7:54)
-
 チョッパリの邑 (37) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/13 7:15)
チョッパリの邑 (37) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/13 7:15)
-
 チョッパリの邑 (38) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/14 7:59)
チョッパリの邑 (38) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/14 7:59)
-
-
 チョッパリの邑 (39) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/15 7:52)
チョッパリの邑 (39) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/15 7:52)
-
 チョッパリの邑 (40) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/16 8:46)
チョッパリの邑 (40) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/16 8:46)
-
 チョッパリの邑 (41・最終回) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/17 7:27)
チョッパリの邑 (41・最終回) 椎野 公雄 (編集者, 2007/6/17 7:27)
-
編集者
 居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
 居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
懐かしき故郷・日本、そして佐世保
三四九〇人の引揚者を乗せた大久丸は夜を徹して順調に走り、翌早朝には五島列島《=長崎市の北西海上にある列島》にさしかかっていた。
父に起こされて甲板に上がると、五島の鮮やかな松の緑が朝日に輝いて目に染《し》みるようだ。三年ぶりに見る内地の景色である。
「公雄、良く見ておけ。『国敗れて山河あり』というけど、やはり日本の景色はいいな」父も如何にも感慨深げである。
海も蒼《あお》ければ、その向こうに映《は》える緑も濃く、朝鮮で見て来た樹々の色合いとは全く異なる深みがある。船の動きとともに姿を変える穏やかな島の佇《たたず》まいには「戦争」、「敗戦」の面影が全く感じられないのが不思議なくらいだ。その後何十年も方々の緑を見てきたが、あの時の感動は今も忘れることができない。
静かな海を滑《すべ》るように船は進み、夢にまで見た母国・佐世保港に着岸したのは昼を過ぎた頃であったろうか。日本の領海に入り、五島の緑に感激し、本土・西彼杵《にしそのぎ》の陸地を右に見ながら目的地・佐世保を目指している時は未だ興奮気味であった船内も、「もうじき佐世保入港です」と船内放送かある頃には、みな安心したのか気が抜けたように静まり返っていた。
しっかりと岸壁に着いた船の上から、改めて港を見渡してみる。九州生まれの私にも佐世保は初めての土地であって勿論見覚えはないが、何だか懐かしいところに帰ってきたような気がする。
「ここが佐世保か。とうとう帰って来たんだな」
未だ空襲の痕《あと》も残っているところもあって痛々しいが、「それでもここは、まぎれもなく日本なのだ」と思うと感慨も一入《ひとしお》、身体の中から嬉《うれ》しさが滲《し》み出てくる思いであった。
暫くすると船内放送でこれからの予定が伝えられる。
「皆様ようこそお帰りなさいませ。私は当援護局のOOです。皆様には早速土陸していただきたいところですが検疫が必要です。明朝、船上にて実施されますので、恐縮《きょうしゅく》ですが終わるまで船内に留まっていただきます」
記録によると、この年の五月、満州からの引揚者の中からコレラ患者が発生、蔓延《まんえん=ひろがる》したことがあり、既に十月には収まっていたものの、受け入れ側としては神経質になっていたからやむを得ない状況ではあった。すぐ上陸できると思っていた私達には残念だったが指示に従うよりなかった。
翌朝、白衣を着た検疫《=伝染病の有無を調べる》官が大勢乗り込んできて検疫が始まった。私達は甲板上に一列に並ばされ、下着を膝下まで下ろしお尻を突き出すとガラスの棒を押し込まれる。あられもない恰好だが、当時はこれが一般的な方法だったようで、当然な措置《そち=処置》と思って検査を受けたのである。
三~四時間かけて約三五〇〇人全員の検査が終わると、結果は宿舎で待つこととして順次下船が始まった。
当時は引揚者の帰還が最も多い時期だったから、受け入れも大変だったと思われる。特に十月には八五隻・十二万四八八七人が受け入れられたと記録に残っており、一日に約三隻が入港し平均四〇〇〇人が上陸したことになる。事実十月十五日には我々の大久丸のほか、中国・胡芦島から二隻(合計四四〇〇人)が入港していたから、佐世保は引揚者でごった返していたと言ってもよかった。
なお戦後の海外日本人引揚者受け入れ及び外国人送還事業は、昭和二十年十月から、この佐世保、舞鶴など日本各地一〇数箇所に開設された引揚援護局によって行われたが、佐世保援護局の記録では二十五年五月に閉局するまでに、引揚者は軍人・六三万三〇〇〇人、一般人・七五万九〇〇〇人、合計一三九万二〇〇〇人(全国六五〇万ともいわれる総数の二〇%強)を受け人れたとされる。方面別では満州が最も多く五一万七〇〇〇人(殆どが一般人)、次いで華北《=中国北部》・四二万九〇〇〇人(ほぼ半数が一般人)、華中・二一万九〇〇〇人(殆どが軍人)、そして朝鮮・一二万一〇〇〇人(うち一般人四万六〇〇〇人)、残り10万人が他地区となっている。また送還者は一九万四〇〇〇人で、うち一一万人が朝鮮人であった。
とにかく膨大《ぼうだい》な数の引揚者、送還者を扱った佐世保であって、援護局としても大事業だったと思われる。
三四九〇人の引揚者を乗せた大久丸は夜を徹して順調に走り、翌早朝には五島列島《=長崎市の北西海上にある列島》にさしかかっていた。
父に起こされて甲板に上がると、五島の鮮やかな松の緑が朝日に輝いて目に染《し》みるようだ。三年ぶりに見る内地の景色である。
「公雄、良く見ておけ。『国敗れて山河あり』というけど、やはり日本の景色はいいな」父も如何にも感慨深げである。
海も蒼《あお》ければ、その向こうに映《は》える緑も濃く、朝鮮で見て来た樹々の色合いとは全く異なる深みがある。船の動きとともに姿を変える穏やかな島の佇《たたず》まいには「戦争」、「敗戦」の面影が全く感じられないのが不思議なくらいだ。その後何十年も方々の緑を見てきたが、あの時の感動は今も忘れることができない。
静かな海を滑《すべ》るように船は進み、夢にまで見た母国・佐世保港に着岸したのは昼を過ぎた頃であったろうか。日本の領海に入り、五島の緑に感激し、本土・西彼杵《にしそのぎ》の陸地を右に見ながら目的地・佐世保を目指している時は未だ興奮気味であった船内も、「もうじき佐世保入港です」と船内放送かある頃には、みな安心したのか気が抜けたように静まり返っていた。
しっかりと岸壁に着いた船の上から、改めて港を見渡してみる。九州生まれの私にも佐世保は初めての土地であって勿論見覚えはないが、何だか懐かしいところに帰ってきたような気がする。
「ここが佐世保か。とうとう帰って来たんだな」
未だ空襲の痕《あと》も残っているところもあって痛々しいが、「それでもここは、まぎれもなく日本なのだ」と思うと感慨も一入《ひとしお》、身体の中から嬉《うれ》しさが滲《し》み出てくる思いであった。
暫くすると船内放送でこれからの予定が伝えられる。
「皆様ようこそお帰りなさいませ。私は当援護局のOOです。皆様には早速土陸していただきたいところですが検疫が必要です。明朝、船上にて実施されますので、恐縮《きょうしゅく》ですが終わるまで船内に留まっていただきます」
記録によると、この年の五月、満州からの引揚者の中からコレラ患者が発生、蔓延《まんえん=ひろがる》したことがあり、既に十月には収まっていたものの、受け入れ側としては神経質になっていたからやむを得ない状況ではあった。すぐ上陸できると思っていた私達には残念だったが指示に従うよりなかった。
翌朝、白衣を着た検疫《=伝染病の有無を調べる》官が大勢乗り込んできて検疫が始まった。私達は甲板上に一列に並ばされ、下着を膝下まで下ろしお尻を突き出すとガラスの棒を押し込まれる。あられもない恰好だが、当時はこれが一般的な方法だったようで、当然な措置《そち=処置》と思って検査を受けたのである。
三~四時間かけて約三五〇〇人全員の検査が終わると、結果は宿舎で待つこととして順次下船が始まった。
当時は引揚者の帰還が最も多い時期だったから、受け入れも大変だったと思われる。特に十月には八五隻・十二万四八八七人が受け入れられたと記録に残っており、一日に約三隻が入港し平均四〇〇〇人が上陸したことになる。事実十月十五日には我々の大久丸のほか、中国・胡芦島から二隻(合計四四〇〇人)が入港していたから、佐世保は引揚者でごった返していたと言ってもよかった。
なお戦後の海外日本人引揚者受け入れ及び外国人送還事業は、昭和二十年十月から、この佐世保、舞鶴など日本各地一〇数箇所に開設された引揚援護局によって行われたが、佐世保援護局の記録では二十五年五月に閉局するまでに、引揚者は軍人・六三万三〇〇〇人、一般人・七五万九〇〇〇人、合計一三九万二〇〇〇人(全国六五〇万ともいわれる総数の二〇%強)を受け人れたとされる。方面別では満州が最も多く五一万七〇〇〇人(殆どが一般人)、次いで華北《=中国北部》・四二万九〇〇〇人(ほぼ半数が一般人)、華中・二一万九〇〇〇人(殆どが軍人)、そして朝鮮・一二万一〇〇〇人(うち一般人四万六〇〇〇人)、残り10万人が他地区となっている。また送還者は一九万四〇〇〇人で、うち一一万人が朝鮮人であった。
とにかく膨大《ぼうだい》な数の引揚者、送還者を扱った佐世保であって、援護局としても大事業だったと思われる。
--
編集者 (代理投稿)