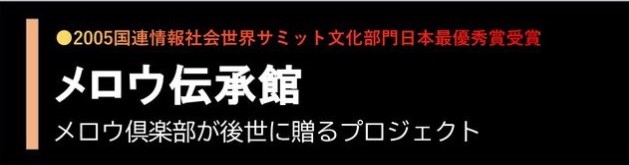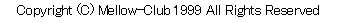гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј—) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„
жҠ•зЁҝгғ„гғӘгғј
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ пјңдёҖйғЁиӢұиЁігҒӮгӮҠпјһ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/4/28 7:38)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ пјңдёҖйғЁиӢұиЁігҒӮгӮҠпјһ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/4/28 7:38)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/4/29 7:43)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/4/29 7:43)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (3) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/4/30 6:49)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (3) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/4/30 6:49)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј”) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/1 7:21)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј”) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/1 7:21)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј•) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/2 8:31)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј•) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/2 8:31)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј–) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/3 7:38)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј–) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/3 7:38)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј—) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/4 8:37)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј—) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/4 8:37)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пјҳ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/5 7:51)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пјҳ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/5 7:51)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пјҷ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/6 8:12)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пјҷ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/6 8:12)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пјҗ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/7 7:47)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пјҗ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/7 7:47)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј‘) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/8 7:46)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј‘) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/8 7:46)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј’) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/9 5:57)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј’) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/9 5:57)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј“) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/20 10:17)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј“) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/20 10:17)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј”) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/21 9:32)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј”) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/21 9:32)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘5) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/22 8:44)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘5) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/22 8:44)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј–) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/23 8:05)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј–) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/23 8:05)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј—) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/24 7:23)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пј—) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/24 7:23)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пјҳ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/25 7:34)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пјҳ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/25 7:34)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пјҷ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/26 6:51)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј‘пјҷ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/26 6:51)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пјҗ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/27 7:27)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пјҗ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/27 7:27)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј‘) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/28 7:07)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј‘) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/28 7:07)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј’) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/29 7:36)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј’) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/29 7:36)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј“) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/30 7:39)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј“) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/30 7:39)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (24) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/31 15:39)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (24) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/5/31 15:39)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј•) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/1 7:56)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј•) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/1 7:56)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј–) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/2 6:56)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј–) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/2 6:56)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј—) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/3 7:22)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пј—) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/3 7:22)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пјҳ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/4 7:19)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пјҳ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/4 7:19)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пјҷ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/5 8:04)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј’пјҷ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/5 8:04)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пјҗ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/6 7:43)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пјҗ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/6 7:43)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј‘) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/7 7:39)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј‘) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/7 7:39)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј’) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/8 8:21)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј’) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/8 8:21)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј“) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/9 7:20)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј“) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/9 7:20)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј”) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/10 8:08)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј”) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/10 8:08)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј•) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/11 7:53)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј•) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/11 7:53)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј–) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/12 7:54)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј–) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/12 7:54)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј—) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/13 7:15)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пј—) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/13 7:15)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пјҳ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/14 7:59)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пјҳ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/14 7:59)
-
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пјҷ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/15 7:52)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј“пјҷ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/15 7:52)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј”пјҗ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/16 8:46)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј”пјҗ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/16 8:46)
-
 гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј”пј‘гғ»жңҖзөӮеӣһ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/17 7:27)
гғҒгғ§гғғгғ‘гғӘгҒ®йӮ‘ (пј”пј‘гғ»жңҖзөӮеӣһ) жӨҺйҮҺ е…¬йӣ„ (з·ЁйӣҶиҖ…, 2007/6/17 7:27)
-
гҒ“гҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜгҒ®жҠ•зЁҝдёҖиҰ§гҒё
- depth:
- 1
з·ЁйӣҶиҖ…
 еұ…дҪҸең°: гғЎгғӯгӮҰеҖ¶жҘҪйғЁ
жҠ•зЁҝж•°: 4298
еұ…дҪҸең°: гғЎгғӯгӮҰеҖ¶жҘҪйғЁ
жҠ•зЁҝж•°: 4298
 еұ…дҪҸең°: гғЎгғӯгӮҰеҖ¶жҘҪйғЁ
жҠ•зЁҝж•°: 4298
еұ…дҪҸең°: гғЎгғӯгӮҰеҖ¶жҘҪйғЁ
жҠ•зЁҝж•°: 4298
гҖҖгҒ„гӮҲгҒ„гӮҲе§ӢгҒҫгӮӢй…·еҜ’гҒ®ең°гҒ®з”ҹжҙ»
гҖҖеҢ—дёӯй§…гҒ«зқҖгҒҸгҒЁгҖҒеҗҢиЎҢгҒ®еҺҹеҸЈгҒ•гӮ“гҒ®жЎҲеҶ…гҒ§ж—©йҖҹзӨҫе®…гҒ«еҗ‘гҒӢгҒҶгҖӮ
гҖҖжҘҠеёӮе·Ҙе ҙгҒ§гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬дәәгҒҜе·Ҙе ҙгҒӢгӮүзҷҫгҒёе°‘гҒ—йӣўгӮҢгҒҹиҒ·е“ЎзӨҫе®…гҒ«гҖҒзҸҫең°жңқй®®дәәгҒҜе·Ҙе ҙгҒ®еҸҚеҜҫеҒҙгҒ«гҒӮгӮӢе·Ҙе“ЎзӨҫе®…гҒ«еұ…дҪҸгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒиіҮжқҗиӘІй•·гҒЁгҒ—гҒҰзқҖд»»гҒ—гҒҹзҲ¶гҒ®зӨҫе®…гҒҜгҖҒиҒ·е“ЎзӨҫе®…гҒ®еҢәз”»гҒ®е…ҘгӮҠеҸЈгҒ«иҝ‘гҒ„еҢ—жқұгҒ®й«ҳеҸ°гҒ«гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒдҪ•еҮҰгҒ«иЎҢгҒҸгҒ«гӮӮдҫҝеҲ©гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖ家гҒҜжңЁйҖ гғўгғ«гӮҝгғ«йҖ гӮҠгҒ§еӨ–иҰӢгҒҜжҙӢйўЁгҒ®дёҖжҲёе»әгҒҰгҖҒ家гҒ®дёӯгҒҜдәҢгҒӨгҒ®е’Ңе®ӨпјҲе…«з•ігҖҒе…ӯз•іпјүгҒЁгӮӘгғігғүгғ«йғЁеұӢпјҲе…ӯз•іпјүгҒ«гҖҒеҸ°жүҖгҖҒгғҲгӮӨгғ¬гҒӘгҒ©гҒҢд»ҳгҒҸз«ӢжҙҫгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖгӮӘгғігғүгғ«гҒЁгҒҜеҶ¬гҒ®еҜ’гҒ•еҜҫзӯ–гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеәҠгҒҜгӮігғігӮҜгғӘгғјгғҲгҒ«гғӘгғҺгғӘгӮҰгғ ејөгӮҠгҖҒеҸ°жүҖеҒҙгҒӢгӮүи–ӘгҖҒгҒҫгҒҹгҒҜз·ҙзӮӯгӮ’з„ҡгҖҠгҒҹгҖӢгҒ„гҒҰгҖҒз…ҷгӮ’еәҠдёӢгҒ«йҖҷгӮҸгҒӣгӮӢж§ӢйҖ гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹйғЁеұӢгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖеҪ“然гҖҒз…ҷгҒҜз…ҷзӘҒгҒӢгӮүеҮәгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒеҶ¬е ҙгҒҜеҗ„家гҒ®з…ҷзӘҒгҒӢгӮүдёҖж—Ҙдёӯз…ҷгҒҢеҮәгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
гҖҖжңқй®®гҒ§гӮӮжңҖеҢ—з«ҜгҒ«дҪҚзҪ®гҒҷгӮӢгҒ“гҒ®ең°гҒ®еҶ¬гҒҜгҖҒеҚҒжңҲгҒӢгӮүзҝҢе№ҙгҒ®еӣӣжңҲй ғгҒҫгҒ§гҖҒжңҖгӮӮеҜ’гҒ„гҒЁгҒҚгҒҜж°—жё©гӮӮйӣ¶дёӢдёүгҖҮеәҰгҒҫгҒ§дёӢгҒҢгӮӢй…·еҜ’гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжҳҘгҒЁз§ӢгҒҜзҹӯгҒҸгҖҒеӨҸгҒҢзөӮгӮҸгӮӢгҒЁеҶ¬ж”ҜеәҰгҖҒеҶ¬гҒҢжҳҺгҒ‘гӮҢгҒ°еӨҸж”ҜеәҰгҒЁгҒҫгҒ“гҒЁгҒ«ж…ҢгҖҠгҒӮгӮҸгҒҹгҒ гҖӢгҒ—гҒ„гҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ§гӮӮзҹӯгҒҸгҒЁгӮӮйҒҺгҒ”гҒ—гӮ„гҒҷгҒ„еӯЈзҜҖгҒҜгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒиҫІдҪңзү©гҒҜзұігҖҒйәҰгҖҒгғҲгӮҰгғўгғӯгӮігӮ·гҖҒиҠӢгҒ®йЎһгҖҒжҲ–гҒ„гҒҜйҮҺиҸңгӮӮгҒЎгӮ„гӮ“гҒЁиӮІгҒЈгҒҰиұҠеҜҢгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖз§ҒйҒ”гҒҢзҸҫең°е…ҘгӮҠгҒ—гҒҹд№қжңҲгҒҜгҖҒз§ӢгӮӮж·ұгҒҫгӮҚгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶжҷӮгҒ§жңқжҷ©гҒҜиӮҢеҜ’гҒҸгҖҒгҒқгӮҚгҒқгӮҚеҶ¬гҒ®ж°—й…ҚгҒҢж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгӮӢй ғгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ§гӮӮжңӘгҒ гӮігғјгғҲгӮ’зқҖиҫјгӮҖгҒ»гҒ©гҒ§гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖзҲ¶гҒҜгҖҢдјҡзӨҫгҒ«еҲ°зқҖгҒ®е ұе‘ҠгӮ’гҒ—гҒҰгҒҸгӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгҖҒгҒҷгҒҗеҮәгҒӢгҒ‘гҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖеҶ…ең°гҒӢгӮүе…ҲгҒ«йҖҒгӮҠеҮәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹ家財йҒ“е…·дёҖејҸгҒҜжңӘгҒ еҲ°зқҖгҒ—гҒҰгҒҠгӮүгҒҡгҖҒеҸ–гӮҠгҒӮгҒҲгҒҡз”ҹжҙ»гҒҷгӮӢгҒ«жңҖдҪҺйҷҗеҝ…иҰҒгҒӘйҒ“е…·гҒЁгҒ—гҒҰдјҡзӨҫгҒӢгӮүеҖҹгӮҠгҒҰгҒӮгҒЈгҒҹеҜқе…·гӮ„зӮҠдәӢйҒ“е…·гҒӘгҒ©гҒҢзҪ®гҒ„гҒҰгҒӮгӮӢгҖҒгҒҢгӮүгӮ“гҒЁгҒ—гҒҹйғЁеұӢгҒ«гҖҒжҜҚгғ»е§үгғ»з§ҒгҒЁејҹгҒ®з§ҒгҒҹгҒЎеӣӣдәәгҒҜгҖҢгҒӮпјҚгҒӮгҖҒз–ІгӮҢгҒҹгҖҚгҒЁжүӢи¶ігӮ’дјёгҒ°гҒ—гҒҰжЁӘгҒҹгӮҸгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖдёүж—ҘгҒ«еҮәзҷәгҒ—гҒҰгҖҒйҖ”дёӯгҖҒж—…йӨЁгғ»иҲ№гғ»жұҪи»Ҡгғ»ж—…йӨЁгҒЁеӣӣжіҠгҒ®й•·ж—…гӮ’зөӮгҒҲгҒҰд»Ҡж—ҘгҒҜгӮӮгҒҶдёғж—ҘгҖҒжң¬еҪ“гҒ«гҖҒдёүеҚғйҮҢгӮ’и¶ҠгҒҲгҒҰйҒҘгҖ…гҖҠгҒҜгӮӢгҒ°гӮӢгҖӢжқҘгҒҹгӮӮгҒ®гҒЁгҒ®е®ҹж„ҹгҒҢжІёгҒ„гҒҰгҒҸгӮӢгҖӮ
гҖҖгҒ“гҒҶгҒ—гҒҰз§ҒгҒҹгҒЎгҒ®еӨ–ең°гғ»жңқй®®гҒ§гҒ®з”ҹжҙ»гҒҜе§ӢгҒҫгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒӮгҒЁгҒӮгҒЁгҖҢжҢҒгҒЈгҒҰжқҘгӮӢгӮ“гҒҳгӮ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖҚгҒЁеҳҶгҒҸгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢиІЁи»ҠдёҖжқҜгҒ®е®¶иІЎгӮӮгҖҒдёҖйҖұй–“гӮӮгҒ—гҒӘгҒ„гҒҶгҒЎгҒ«еҲ°зқҖгҒ—гҒҰгҖҒгӮҲгҒҶгӮ„гҒҸиҗҪгҒЎзқҖгҒ„гҒҹз”ҹжҙ»гҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖеӯҰж ЎгҒҜгҖҒе·Ҙе ҙй–ўдҝӮиҖ…еӯҗејҹгҒқгҒ®д»–ж—Ҙжң¬дәәгҒ®гҒҝгӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгӮӢе°ҸеӯҰж ЎпјҲеӣҪж°‘еӯҰж ЎпјүгҒҢзӨҫе®…гҒ®еӮҚгҒ«дҪңгӮүгӮҢгҖҒдёҖеӯҰе№ҙдәҢгҖҮпҪһдёүгҖҮдәәгҖҒе…Ёж ЎгҒ§гӮӮдёҖдә”гҖҮдәәгҒ»гҒ©гҒ®е°ҸгҒ•гҒӘиҰҸжЁЎгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒе…Ҳз”ҹгҒҜеҶ…ең°гҒӢгӮүгҒ®жҙҫйҒЈгҖҒгҒҫгҒҹгҒҜзҸҫең°жҺЎз”ЁиҖ…гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖгҒҫгҒҹдёӯеӯҰж ЎгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҖҒеҶ…ең°ж®Ӣз•ҷгҖҠпјқж—Ҙжң¬гҒ«ж®ӢгҒЈгҒҰгҖӢгҒ®гӮұгғјгӮ№гӮӮгҒӮгҒЈгҒҰз”ҹеҫ’ж•°гҒҢе°‘гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒӢгӮүгҖҒж–°зҫ©е·һгҒҫгҒ§жұҪи»ҠйҖҡеӯҰгӮ’дҪҷе„ҖгҒӘгҒҸгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ
гҖҖеӣҪж°‘еӯҰж ЎгҒҜж—ўгҒ«дәҢеӯҰжңҹгҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒж—©йҖҹжүӢз¶ҡгҒҚгӮ’жёҲгҒҫгҒӣгҒҰйҖҡгҒҶгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ
ж ЎиҲҺгҒҜж–°гҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгҒҢе…ҘеӯҰиҖ…ж•°гҒҢдәҲжғігӮ’дёҠеӣһгҒЈгҒҰжүӢзӢӯгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒеў—зҜүгҒ®гҒҹгӮҒдёҖжҷӮжңҹйҙЁз·‘гҖҠгғӨгғјгғ«гғјгҖӢжұҹжІіеҸЈгҒ®еӨҡзҚ…еі¶гҒЁгҒ®й–“гҒ«гҒӮгӮӢйҫҚеІ©жөҰгҖҠгғЁгғ гӮўгғ гғқгҖӢгҒ®еӯҰж ЎгҒЁе…ұеҗҢжҺҲжҘӯгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҖҒжұҪи»ҠгҒ§йҖҡеӯҰгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—е·ҘдәӢгӮӮдәҢгӮұжңҲгҒ°гҒӢгӮҠгҒ§зөӮгӮҸгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒҫгҒҹгҒҷгҒҗе…ғгҒ®ж ЎеҗҲгҒ«жҲ»гҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ
гҖҖгҒ‘гӮҢгҒ©гӮӮгҖҒжҳӯе’ҢдәҢеҚҒе№ҙе…«жңҲгҒҫгҒ§гҒ»гҒјдәҢе№ҙгҒӮгҒЈгҒҹеӯҰж Ўз”ҹжҙ»гҖҒзү№гҒ«жҺҲжҘӯгҒ®еҶ…е®№гӮ’гҒӮгҒҫгӮҠиЁҳжҶ¶гҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒҜдҪ•ж•…гҒӘгҒ®гҒӢгҖҒеҲҘгҒ«еӯҰж ЎгҒҢе«ҢгҒ„гҒ гҒЈгҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гӮӮгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ—гҖҒд»ҠгӮӮгҒЈгҒҰдёҚжҖқиӯ°гҒӘж°—гҒҢгҒ—гҒҰгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮ
гҖҖгҒҹгҒ дҝ®иә«гҒ®жҷӮй–“гҒҢгӮ„гҒҹгӮүгҒ«еҺігҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҖҒеҶ…ең°гҒЁйҒ•гҒЈгҒҰгҖҢеҘүе®үж®ҝгҖҠгҒ»гҒҶгҒӮгӮ“гҒ§гӮ“гҖӢгҖҚгҒҢз„ЎгҒӢгҒЈгҒҹгҒӢгӮүгҖҒжҜҺжңқгҖҒжқұеҚ—гҒ®ж–№еҗ‘гӮ’еҗ‘гҒҚгҖҢе®®еҹҺгҖҚйҒҘжӢқгҖҠгӮҲгҒҶгҒҜгҒ„пјқйҒ гҒҸгҒӢгӮүжӢқгӮҖгҖӢгӮ’гҒ•гҒӣгӮүгӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҖҒе§ӢжҘӯејҸгӮ„ж——ж—ҘгҒ«гҒҜгҖҒж Ўй•·е…Ҳз”ҹгҒҢжҒӯгҒ—гҒҸжҚ§гҖҠгҒ•гҒ•гҒ’гҖӢгҒ’гӮӮгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹжјҶеЎ—гҖҠгҒҶгӮӢгҒ—гҒ¬гӮҠгҖӢгӮҠгҒ®й»’гҒ„з®ұгҒӢгӮүгҖҒгҖҢе·»зү©гҖҚгҒ®ж•ҷиӮІеӢ…иӘһгӮ’еҸ–гӮҠеҮәгҒ—гҒҰиӘӯгӮҖгҒ®гӮ’гҖҒй ӯгӮ’дёӢгҒ’гҒҰиҒһгҒӢгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒҫгҒҹеӢ…иӘһгҖҠгҒЎгӮҮгҒҸгҒ”пјқеӨ©зҡҮгҒ®иЁҖи‘үгҖӢгҒҜиҒһгҒҸгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸжҜҺж—ҘгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жҡ—иӘҰгҖҠгҒӮгӮ“гҒ—гӮҮгҒҶгҖӢгҒ•гҒӣгӮүгӮҢгҒҹгҖӮ
гҖҖгҖҢгғҒгғігӮӘгғўгӮҰгғӢгғ»гғҜгӮ¬гӮігӮҰгӮҪгӮігӮҰгӮҪгӮҰгғ»гӮҜгғӢгғІгғҸгӮёгғ гғ«гӮігғҲгғ»гӮігӮҰгӮЁгғігғӢгғ»гғҲгӮҜгғІгӮҝгғ„гғ«гӮігғҲгӮ·гғігӮігӮҰгғҠгғӘгғ»гғҜгӮ¬гӮ·гғігғҹгғігғ»гғЁгӮҜгғҒгғҘгӮҰгғӢгғ»гғЁгӮҜгӮігӮҰгғӢгғ»гӮӘгӮҜгғҒгғ§гӮҰгӮігӮігғӯгғІгӮӨгғ„гғӢгӮ·гғҶгғ»гғЁгғЁгӮҪгғҺгғ“гғІгғҠгӮ»гғ«гғҸгғ»гӮігғ¬гғҜгӮ¬гӮігӮҜгӮҝгӮӨгғҺгӮ»гӮӨгӮ«гғҶвҖҰгғҠгғігӮёгӮ·гғігғҹгғігғ»гғ•гғңгғӢгӮігӮҰгғӢгғ»гӮұгӮӨгғҶгӮӨгғӢгғҘгӮҰгғӢгғ»гғ•гӮҰгғ•гӮўгӮӨгғ•гӮ·гғ»гғӣгӮҰгғҘгӮҰгӮўгӮӨгӮ·гғігӮёвҖҰгӮӨгғғгӮҝгғігӮ«гғігӮӯгғҘгӮҰгӮўгғ¬гғҗгғ»гӮ®гғҘгӮҰгӮігӮҰгғӢгғӣгӮҰгӮёвҖҰгӮұгғігӮұгғігғ•гӮҜгғ§гӮҰгӮ·гғҶгғ»гғҹгғҠгӮҪгғҺгғҲгӮҜгғІгӮӨгғ„гғӢгӮ»гғігӮігғҲгғІгғ»гӮігӮӨгғҚгӮ¬гӮҰпјҡгӮ®гғ§гғЎгӮӨгӮ®гғ§гӮёгҖҚгҖҒеҪ“жҷӮж„Ҹе‘ігҒҜжӯЈзўәгҒ«гҒҜи§ЈгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢд»ҠгҒ§гӮӮгҒҷгӮүгҒҷгӮүеҮәгҒҰгҒҸгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®жҹ”гӮүгҒӢгҒ„й ӯгҒ«еҫ№еә•зҡ„гҒ«еҸ©гҒҚиҫјгҒҫгӮҢгҒҹгҒҠйҷ°гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮ
гҖҖдҪҸгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹеҢ—дёӯйқўе…ғеі°жҙһеҚ—жҘҠеёӮгҒҜгҖҒе·Ҙе ҙгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒҫгҒ§гҒҜйқҷгҒӢгҒӘз”°ең’ең°еёҜгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒЁжҖқгӮҸгӮҢгҖҒжқұеҚ—гҒ«дҪҺгҒ„еұұдёҰгҒҝгҒҢгҒӮгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҖҒгҒ»гҒӢгҒҜгҒ©гҒЎгӮүгӮ’иҰӢгҒҰгӮӮеӨ§гҒҚгҒҸй–ӢгҒ‘гҖҒзү№гҒ«йҙЁз·‘жұҹгҒ®гҒӢгҒӘгҒҹгҖҒиҘҝгҒ®еӨ§ең°гҒ«еӨ•ж—ҘгҒҢиөӨгҒҸжІҲгӮҖйўЁжҷҜгҒҜгҒ“гӮҢгҒҢеӨ§йҷёгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹйўЁжғ…гҒ§гҖҒе°‘гҒӘгҒҸгҒЁгӮӮж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜеҲ°еә•гҒҠзӣ®гҒ«гҒӢгҒӢгҒӢгӮҢгҒ¬еЈ®еӨ§гҒ•гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖжңҖеҲқгҒ®й ғгҒҜгҖҒиЎ—гҒ«иІ·гҒ„зү©гҒ«еҮәгӮӢгҒ®гӮӮеҝғй…ҚгҒ§гҖҒж—ҘеёёдҪ•гҒӢгҒЁйқўеҖ’гӮ’гҒҝгҒҰгҒҸгӮҢгӮӢжңҙгҒ•гӮ“гҒ«жЎҲеҶ…гӮ’й јгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҒҢгҖҒ次第гҒ«иЁҖи‘үгӮ„з’°еўғгҒ«гӮӮж…ЈгӮҢгҒҰгҒҸгӮӢгҒЁгҖҒеҸӢйҒ”гӮ„дёЎиҰӘгҒЁеҮәгҒӢгҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮеӢҝи«–з”ҹжҙ»гҒ«еҝ…иҰҒгҒӘзү©е“ҒгҒҜж®ҶгҒ©зӨҫе®…гҒ®дёӯгҒ«гҒӮгӮӢеЈІеә—гҒ§иІ·гҒҲгӮӢгҒҢгҖҒзү©зҸҚгҒ—гҒ•гӮӮжүӢдјқгҒЈгҒҰжһңзү©гҒӘгҒ©гҒҜиЎ—гҒ§иІ·гҒЈгҒҰгҒҚгҒҰйЈҹгҒ№гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖзү№гҒ«гғһгӮҜгғҜз“ңгӮ„иҘҝз“ңгҒӘгҒ©гҒ®жһңзү©гҖҒзӢ¬зү№гҒ®е‘ігҒҢгҒҷгӮӢйЈҙгӮ„йӨ…гҒӘгҒ©гӮ’иІ·гҒ„йЈҹгҒ„гҒҷгӮӢгҒ®гҒҢжҘҪгҒ—гҒҝгҒ§гҖҒеҪ“然гҒӘгҒҢгӮүгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж©ҹдјҡгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰиЁҖи‘үгӮӮжҶ¶гҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒЁгҒҜгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒж–Үжі•гҒҢи§ЈгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гӮӮгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§иҒһгҒҚиҰҡгҒҲгҒҹеҚҳиӘһгӮ’дёҰгҒ№гӮӢгҒ гҒ‘гҖӮеҗ‘гҒ“гҒҶгӮӮгӮҲгҒ»гҒ©гҒ®иҖҒдәәгҒ§гҒӘгҒ„йҷҗгӮҠж—Ҙжң¬иӘһгҒҢи§ЈгӮӢгҒӢгӮүзөҗеұҖгғҒгғЈгғігғқгғігҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҖҒгҖҢгӮўгғігғӢгғ§гғігғ»гғҸгӮ»гғ§гҖҚгҖҒгҖҢгӮігғһгӮ№гғҹгғҖгҖҚгҒӘгҒ©гҒ®жҢЁжӢ¶гҒҜгҒ„гҒ„гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҖҢгғһгғғгӮ«гғ»гғҒгғ§гӮ»гғ§гҖҒгҒ„гҒҸгӮүпјҹгҖҚгҖҒгҖҢй«ҳгҒ„гӮҲгҖҒгғҠгғғгғ—гғігӮҲгҖҚгҖҒгҖҢйЈҙгҖҒгғҸгғҠгғ»гғҒгғ§гӮ»гғ§гҖҚгҒӘгҒ©гҒЁгҖҒгҒҫгҒ“гҒЁгҒ«дёҚеҸҜжҖқиӯ°гҒӘдјҡиӘһгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
гҖҖгҒ„гҒҡгӮҢгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҰиЎ—гҒ«еҮәгҒҹгӮҠгҒ—гҒӘгҒ„йҷҗгӮҠгҖҒзӨҫе®…гҒЁеӯҰж ЎгҒЁгҒ„гҒҶж—Ҙжң¬дәәзӨҫдјҡгҒ®дёӯгҒ§йҡ”йӣўгҒ•гӮҢгҒҰз”ҹжҙ»гҒҷгӮӢжҷӮй–“гҒ®ж–№гҒҢиүҜгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒзөҗеұҖжңҖеҫҢгҒҫгҒ§жӯЈгҒ—гҒ„жңқй®®иӘһгӮ’е„„гҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒд»ҠгҒ«гҒ—гҒҰжҖқгҒҲгҒ°иӘ гҒ«ж®ӢеҝөгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҖҖ
гҖҖжҳӯе’Ңпј‘пјҷе№ҙгҒ®жҳҘпјҹгҖҖиҮӘе®…зҺ„й–ўгҒ«гҒҰ
гҖҖзҲ¶гҒҢж’®еҪұгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒҹеҶҷзңҹгҖӮеҫҢеҲ—е·Ұз«Ҝгғ»йҳІеҜ’еёҪгҒҢз§ҒгҖӮ
гҖҖеҢ—дёӯй§…гҒ«зқҖгҒҸгҒЁгҖҒеҗҢиЎҢгҒ®еҺҹеҸЈгҒ•гӮ“гҒ®жЎҲеҶ…гҒ§ж—©йҖҹзӨҫе®…гҒ«еҗ‘гҒӢгҒҶгҖӮ
гҖҖжҘҠеёӮе·Ҙе ҙгҒ§гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬дәәгҒҜе·Ҙе ҙгҒӢгӮүзҷҫгҒёе°‘гҒ—йӣўгӮҢгҒҹиҒ·е“ЎзӨҫе®…гҒ«гҖҒзҸҫең°жңқй®®дәәгҒҜе·Ҙе ҙгҒ®еҸҚеҜҫеҒҙгҒ«гҒӮгӮӢе·Ҙе“ЎзӨҫе®…гҒ«еұ…дҪҸгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒиіҮжқҗиӘІй•·гҒЁгҒ—гҒҰзқҖд»»гҒ—гҒҹзҲ¶гҒ®зӨҫе®…гҒҜгҖҒиҒ·е“ЎзӨҫе®…гҒ®еҢәз”»гҒ®е…ҘгӮҠеҸЈгҒ«иҝ‘гҒ„еҢ—жқұгҒ®й«ҳеҸ°гҒ«гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒдҪ•еҮҰгҒ«иЎҢгҒҸгҒ«гӮӮдҫҝеҲ©гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖ家гҒҜжңЁйҖ гғўгғ«гӮҝгғ«йҖ гӮҠгҒ§еӨ–иҰӢгҒҜжҙӢйўЁгҒ®дёҖжҲёе»әгҒҰгҖҒ家гҒ®дёӯгҒҜдәҢгҒӨгҒ®е’Ңе®ӨпјҲе…«з•ігҖҒе…ӯз•іпјүгҒЁгӮӘгғігғүгғ«йғЁеұӢпјҲе…ӯз•іпјүгҒ«гҖҒеҸ°жүҖгҖҒгғҲгӮӨгғ¬гҒӘгҒ©гҒҢд»ҳгҒҸз«ӢжҙҫгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖгӮӘгғігғүгғ«гҒЁгҒҜеҶ¬гҒ®еҜ’гҒ•еҜҫзӯ–гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеәҠгҒҜгӮігғігӮҜгғӘгғјгғҲгҒ«гғӘгғҺгғӘгӮҰгғ ејөгӮҠгҖҒеҸ°жүҖеҒҙгҒӢгӮүи–ӘгҖҒгҒҫгҒҹгҒҜз·ҙзӮӯгӮ’з„ҡгҖҠгҒҹгҖӢгҒ„гҒҰгҖҒз…ҷгӮ’еәҠдёӢгҒ«йҖҷгӮҸгҒӣгӮӢж§ӢйҖ гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹйғЁеұӢгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖеҪ“然гҖҒз…ҷгҒҜз…ҷзӘҒгҒӢгӮүеҮәгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒеҶ¬е ҙгҒҜеҗ„家гҒ®з…ҷзӘҒгҒӢгӮүдёҖж—Ҙдёӯз…ҷгҒҢеҮәгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
гҖҖжңқй®®гҒ§гӮӮжңҖеҢ—з«ҜгҒ«дҪҚзҪ®гҒҷгӮӢгҒ“гҒ®ең°гҒ®еҶ¬гҒҜгҖҒеҚҒжңҲгҒӢгӮүзҝҢе№ҙгҒ®еӣӣжңҲй ғгҒҫгҒ§гҖҒжңҖгӮӮеҜ’гҒ„гҒЁгҒҚгҒҜж°—жё©гӮӮйӣ¶дёӢдёүгҖҮеәҰгҒҫгҒ§дёӢгҒҢгӮӢй…·еҜ’гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжҳҘгҒЁз§ӢгҒҜзҹӯгҒҸгҖҒеӨҸгҒҢзөӮгӮҸгӮӢгҒЁеҶ¬ж”ҜеәҰгҖҒеҶ¬гҒҢжҳҺгҒ‘гӮҢгҒ°еӨҸж”ҜеәҰгҒЁгҒҫгҒ“гҒЁгҒ«ж…ҢгҖҠгҒӮгӮҸгҒҹгҒ гҖӢгҒ—гҒ„гҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ§гӮӮзҹӯгҒҸгҒЁгӮӮйҒҺгҒ”гҒ—гӮ„гҒҷгҒ„еӯЈзҜҖгҒҜгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒиҫІдҪңзү©гҒҜзұігҖҒйәҰгҖҒгғҲгӮҰгғўгғӯгӮігӮ·гҖҒиҠӢгҒ®йЎһгҖҒжҲ–гҒ„гҒҜйҮҺиҸңгӮӮгҒЎгӮ„гӮ“гҒЁиӮІгҒЈгҒҰиұҠеҜҢгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖз§ҒйҒ”гҒҢзҸҫең°е…ҘгӮҠгҒ—гҒҹд№қжңҲгҒҜгҖҒз§ӢгӮӮж·ұгҒҫгӮҚгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶжҷӮгҒ§жңқжҷ©гҒҜиӮҢеҜ’гҒҸгҖҒгҒқгӮҚгҒқгӮҚеҶ¬гҒ®ж°—й…ҚгҒҢж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгӮӢй ғгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ§гӮӮжңӘгҒ гӮігғјгғҲгӮ’зқҖиҫјгӮҖгҒ»гҒ©гҒ§гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖзҲ¶гҒҜгҖҢдјҡзӨҫгҒ«еҲ°зқҖгҒ®е ұе‘ҠгӮ’гҒ—гҒҰгҒҸгӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгҖҒгҒҷгҒҗеҮәгҒӢгҒ‘гҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖеҶ…ең°гҒӢгӮүе…ҲгҒ«йҖҒгӮҠеҮәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹ家財йҒ“е…·дёҖејҸгҒҜжңӘгҒ еҲ°зқҖгҒ—гҒҰгҒҠгӮүгҒҡгҖҒеҸ–гӮҠгҒӮгҒҲгҒҡз”ҹжҙ»гҒҷгӮӢгҒ«жңҖдҪҺйҷҗеҝ…иҰҒгҒӘйҒ“е…·гҒЁгҒ—гҒҰдјҡзӨҫгҒӢгӮүеҖҹгӮҠгҒҰгҒӮгҒЈгҒҹеҜқе…·гӮ„зӮҠдәӢйҒ“е…·гҒӘгҒ©гҒҢзҪ®гҒ„гҒҰгҒӮгӮӢгҖҒгҒҢгӮүгӮ“гҒЁгҒ—гҒҹйғЁеұӢгҒ«гҖҒжҜҚгғ»е§үгғ»з§ҒгҒЁејҹгҒ®з§ҒгҒҹгҒЎеӣӣдәәгҒҜгҖҢгҒӮпјҚгҒӮгҖҒз–ІгӮҢгҒҹгҖҚгҒЁжүӢи¶ігӮ’дјёгҒ°гҒ—гҒҰжЁӘгҒҹгӮҸгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖдёүж—ҘгҒ«еҮәзҷәгҒ—гҒҰгҖҒйҖ”дёӯгҖҒж—…йӨЁгғ»иҲ№гғ»жұҪи»Ҡгғ»ж—…йӨЁгҒЁеӣӣжіҠгҒ®й•·ж—…гӮ’зөӮгҒҲгҒҰд»Ҡж—ҘгҒҜгӮӮгҒҶдёғж—ҘгҖҒжң¬еҪ“гҒ«гҖҒдёүеҚғйҮҢгӮ’и¶ҠгҒҲгҒҰйҒҘгҖ…гҖҠгҒҜгӮӢгҒ°гӮӢгҖӢжқҘгҒҹгӮӮгҒ®гҒЁгҒ®е®ҹж„ҹгҒҢжІёгҒ„гҒҰгҒҸгӮӢгҖӮ
гҖҖгҒ“гҒҶгҒ—гҒҰз§ҒгҒҹгҒЎгҒ®еӨ–ең°гғ»жңқй®®гҒ§гҒ®з”ҹжҙ»гҒҜе§ӢгҒҫгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒӮгҒЁгҒӮгҒЁгҖҢжҢҒгҒЈгҒҰжқҘгӮӢгӮ“гҒҳгӮ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖҚгҒЁеҳҶгҒҸгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢиІЁи»ҠдёҖжқҜгҒ®е®¶иІЎгӮӮгҖҒдёҖйҖұй–“гӮӮгҒ—гҒӘгҒ„гҒҶгҒЎгҒ«еҲ°зқҖгҒ—гҒҰгҖҒгӮҲгҒҶгӮ„гҒҸиҗҪгҒЎзқҖгҒ„гҒҹз”ҹжҙ»гҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖеӯҰж ЎгҒҜгҖҒе·Ҙе ҙй–ўдҝӮиҖ…еӯҗејҹгҒқгҒ®д»–ж—Ҙжң¬дәәгҒ®гҒҝгӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгӮӢе°ҸеӯҰж ЎпјҲеӣҪж°‘еӯҰж ЎпјүгҒҢзӨҫе®…гҒ®еӮҚгҒ«дҪңгӮүгӮҢгҖҒдёҖеӯҰе№ҙдәҢгҖҮпҪһдёүгҖҮдәәгҖҒе…Ёж ЎгҒ§гӮӮдёҖдә”гҖҮдәәгҒ»гҒ©гҒ®е°ҸгҒ•гҒӘиҰҸжЁЎгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒе…Ҳз”ҹгҒҜеҶ…ең°гҒӢгӮүгҒ®жҙҫйҒЈгҖҒгҒҫгҒҹгҒҜзҸҫең°жҺЎз”ЁиҖ…гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖгҒҫгҒҹдёӯеӯҰж ЎгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҖҒеҶ…ең°ж®Ӣз•ҷгҖҠпјқж—Ҙжң¬гҒ«ж®ӢгҒЈгҒҰгҖӢгҒ®гӮұгғјгӮ№гӮӮгҒӮгҒЈгҒҰз”ҹеҫ’ж•°гҒҢе°‘гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒӢгӮүгҖҒж–°зҫ©е·һгҒҫгҒ§жұҪи»ҠйҖҡеӯҰгӮ’дҪҷе„ҖгҒӘгҒҸгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ
гҖҖеӣҪж°‘еӯҰж ЎгҒҜж—ўгҒ«дәҢеӯҰжңҹгҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒж—©йҖҹжүӢз¶ҡгҒҚгӮ’жёҲгҒҫгҒӣгҒҰйҖҡгҒҶгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ
ж ЎиҲҺгҒҜж–°гҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгҒҢе…ҘеӯҰиҖ…ж•°гҒҢдәҲжғігӮ’дёҠеӣһгҒЈгҒҰжүӢзӢӯгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒеў—зҜүгҒ®гҒҹгӮҒдёҖжҷӮжңҹйҙЁз·‘гҖҠгғӨгғјгғ«гғјгҖӢжұҹжІіеҸЈгҒ®еӨҡзҚ…еі¶гҒЁгҒ®й–“гҒ«гҒӮгӮӢйҫҚеІ©жөҰгҖҠгғЁгғ гӮўгғ гғқгҖӢгҒ®еӯҰж ЎгҒЁе…ұеҗҢжҺҲжҘӯгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҖҒжұҪи»ҠгҒ§йҖҡеӯҰгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—е·ҘдәӢгӮӮдәҢгӮұжңҲгҒ°гҒӢгӮҠгҒ§зөӮгӮҸгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒҫгҒҹгҒҷгҒҗе…ғгҒ®ж ЎеҗҲгҒ«жҲ»гҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ
гҖҖгҒ‘гӮҢгҒ©гӮӮгҖҒжҳӯе’ҢдәҢеҚҒе№ҙе…«жңҲгҒҫгҒ§гҒ»гҒјдәҢе№ҙгҒӮгҒЈгҒҹеӯҰж Ўз”ҹжҙ»гҖҒзү№гҒ«жҺҲжҘӯгҒ®еҶ…е®№гӮ’гҒӮгҒҫгӮҠиЁҳжҶ¶гҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒҜдҪ•ж•…гҒӘгҒ®гҒӢгҖҒеҲҘгҒ«еӯҰж ЎгҒҢе«ҢгҒ„гҒ гҒЈгҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гӮӮгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ—гҖҒд»ҠгӮӮгҒЈгҒҰдёҚжҖқиӯ°гҒӘж°—гҒҢгҒ—гҒҰгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮ
гҖҖгҒҹгҒ дҝ®иә«гҒ®жҷӮй–“гҒҢгӮ„гҒҹгӮүгҒ«еҺігҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҖҒеҶ…ең°гҒЁйҒ•гҒЈгҒҰгҖҢеҘүе®үж®ҝгҖҠгҒ»гҒҶгҒӮгӮ“гҒ§гӮ“гҖӢгҖҚгҒҢз„ЎгҒӢгҒЈгҒҹгҒӢгӮүгҖҒжҜҺжңқгҖҒжқұеҚ—гҒ®ж–№еҗ‘гӮ’еҗ‘гҒҚгҖҢе®®еҹҺгҖҚйҒҘжӢқгҖҠгӮҲгҒҶгҒҜгҒ„пјқйҒ гҒҸгҒӢгӮүжӢқгӮҖгҖӢгӮ’гҒ•гҒӣгӮүгӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҖҒе§ӢжҘӯејҸгӮ„ж——ж—ҘгҒ«гҒҜгҖҒж Ўй•·е…Ҳз”ҹгҒҢжҒӯгҒ—гҒҸжҚ§гҖҠгҒ•гҒ•гҒ’гҖӢгҒ’гӮӮгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹжјҶеЎ—гҖҠгҒҶгӮӢгҒ—гҒ¬гӮҠгҖӢгӮҠгҒ®й»’гҒ„з®ұгҒӢгӮүгҖҒгҖҢе·»зү©гҖҚгҒ®ж•ҷиӮІеӢ…иӘһгӮ’еҸ–гӮҠеҮәгҒ—гҒҰиӘӯгӮҖгҒ®гӮ’гҖҒй ӯгӮ’дёӢгҒ’гҒҰиҒһгҒӢгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒҫгҒҹеӢ…иӘһгҖҠгҒЎгӮҮгҒҸгҒ”пјқеӨ©зҡҮгҒ®иЁҖи‘үгҖӢгҒҜиҒһгҒҸгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸжҜҺж—ҘгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жҡ—иӘҰгҖҠгҒӮгӮ“гҒ—гӮҮгҒҶгҖӢгҒ•гҒӣгӮүгӮҢгҒҹгҖӮ
гҖҖгҖҢгғҒгғігӮӘгғўгӮҰгғӢгғ»гғҜгӮ¬гӮігӮҰгӮҪгӮігӮҰгӮҪгӮҰгғ»гӮҜгғӢгғІгғҸгӮёгғ гғ«гӮігғҲгғ»гӮігӮҰгӮЁгғігғӢгғ»гғҲгӮҜгғІгӮҝгғ„гғ«гӮігғҲгӮ·гғігӮігӮҰгғҠгғӘгғ»гғҜгӮ¬гӮ·гғігғҹгғігғ»гғЁгӮҜгғҒгғҘгӮҰгғӢгғ»гғЁгӮҜгӮігӮҰгғӢгғ»гӮӘгӮҜгғҒгғ§гӮҰгӮігӮігғӯгғІгӮӨгғ„гғӢгӮ·гғҶгғ»гғЁгғЁгӮҪгғҺгғ“гғІгғҠгӮ»гғ«гғҸгғ»гӮігғ¬гғҜгӮ¬гӮігӮҜгӮҝгӮӨгғҺгӮ»гӮӨгӮ«гғҶвҖҰгғҠгғігӮёгӮ·гғігғҹгғігғ»гғ•гғңгғӢгӮігӮҰгғӢгғ»гӮұгӮӨгғҶгӮӨгғӢгғҘгӮҰгғӢгғ»гғ•гӮҰгғ•гӮўгӮӨгғ•гӮ·гғ»гғӣгӮҰгғҘгӮҰгӮўгӮӨгӮ·гғігӮёвҖҰгӮӨгғғгӮҝгғігӮ«гғігӮӯгғҘгӮҰгӮўгғ¬гғҗгғ»гӮ®гғҘгӮҰгӮігӮҰгғӢгғӣгӮҰгӮёвҖҰгӮұгғігӮұгғігғ•гӮҜгғ§гӮҰгӮ·гғҶгғ»гғҹгғҠгӮҪгғҺгғҲгӮҜгғІгӮӨгғ„гғӢгӮ»гғігӮігғҲгғІгғ»гӮігӮӨгғҚгӮ¬гӮҰпјҡгӮ®гғ§гғЎгӮӨгӮ®гғ§гӮёгҖҚгҖҒеҪ“жҷӮж„Ҹе‘ігҒҜжӯЈзўәгҒ«гҒҜи§ЈгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢд»ҠгҒ§гӮӮгҒҷгӮүгҒҷгӮүеҮәгҒҰгҒҸгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®жҹ”гӮүгҒӢгҒ„й ӯгҒ«еҫ№еә•зҡ„гҒ«еҸ©гҒҚиҫјгҒҫгӮҢгҒҹгҒҠйҷ°гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮ
гҖҖдҪҸгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹеҢ—дёӯйқўе…ғеі°жҙһеҚ—жҘҠеёӮгҒҜгҖҒе·Ҙе ҙгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒҫгҒ§гҒҜйқҷгҒӢгҒӘз”°ең’ең°еёҜгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒЁжҖқгӮҸгӮҢгҖҒжқұеҚ—гҒ«дҪҺгҒ„еұұдёҰгҒҝгҒҢгҒӮгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҖҒгҒ»гҒӢгҒҜгҒ©гҒЎгӮүгӮ’иҰӢгҒҰгӮӮеӨ§гҒҚгҒҸй–ӢгҒ‘гҖҒзү№гҒ«йҙЁз·‘жұҹгҒ®гҒӢгҒӘгҒҹгҖҒиҘҝгҒ®еӨ§ең°гҒ«еӨ•ж—ҘгҒҢиөӨгҒҸжІҲгӮҖйўЁжҷҜгҒҜгҒ“гӮҢгҒҢеӨ§йҷёгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹйўЁжғ…гҒ§гҖҒе°‘гҒӘгҒҸгҒЁгӮӮж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜеҲ°еә•гҒҠзӣ®гҒ«гҒӢгҒӢгҒӢгӮҢгҒ¬еЈ®еӨ§гҒ•гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖжңҖеҲқгҒ®й ғгҒҜгҖҒиЎ—гҒ«иІ·гҒ„зү©гҒ«еҮәгӮӢгҒ®гӮӮеҝғй…ҚгҒ§гҖҒж—ҘеёёдҪ•гҒӢгҒЁйқўеҖ’гӮ’гҒҝгҒҰгҒҸгӮҢгӮӢжңҙгҒ•гӮ“гҒ«жЎҲеҶ…гӮ’й јгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҒҢгҖҒ次第гҒ«иЁҖи‘үгӮ„з’°еўғгҒ«гӮӮж…ЈгӮҢгҒҰгҒҸгӮӢгҒЁгҖҒеҸӢйҒ”гӮ„дёЎиҰӘгҒЁеҮәгҒӢгҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮеӢҝи«–з”ҹжҙ»гҒ«еҝ…иҰҒгҒӘзү©е“ҒгҒҜж®ҶгҒ©зӨҫе®…гҒ®дёӯгҒ«гҒӮгӮӢеЈІеә—гҒ§иІ·гҒҲгӮӢгҒҢгҖҒзү©зҸҚгҒ—гҒ•гӮӮжүӢдјқгҒЈгҒҰжһңзү©гҒӘгҒ©гҒҜиЎ—гҒ§иІ·гҒЈгҒҰгҒҚгҒҰйЈҹгҒ№гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖзү№гҒ«гғһгӮҜгғҜз“ңгӮ„иҘҝз“ңгҒӘгҒ©гҒ®жһңзү©гҖҒзӢ¬зү№гҒ®е‘ігҒҢгҒҷгӮӢйЈҙгӮ„йӨ…гҒӘгҒ©гӮ’иІ·гҒ„йЈҹгҒ„гҒҷгӮӢгҒ®гҒҢжҘҪгҒ—гҒҝгҒ§гҖҒеҪ“然гҒӘгҒҢгӮүгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж©ҹдјҡгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰиЁҖи‘үгӮӮжҶ¶гҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒЁгҒҜгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒж–Үжі•гҒҢи§ЈгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гӮӮгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§иҒһгҒҚиҰҡгҒҲгҒҹеҚҳиӘһгӮ’дёҰгҒ№гӮӢгҒ гҒ‘гҖӮеҗ‘гҒ“гҒҶгӮӮгӮҲгҒ»гҒ©гҒ®иҖҒдәәгҒ§гҒӘгҒ„йҷҗгӮҠж—Ҙжң¬иӘһгҒҢи§ЈгӮӢгҒӢгӮүзөҗеұҖгғҒгғЈгғігғқгғігҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҖҒгҖҢгӮўгғігғӢгғ§гғігғ»гғҸгӮ»гғ§гҖҚгҖҒгҖҢгӮігғһгӮ№гғҹгғҖгҖҚгҒӘгҒ©гҒ®жҢЁжӢ¶гҒҜгҒ„гҒ„гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҖҢгғһгғғгӮ«гғ»гғҒгғ§гӮ»гғ§гҖҒгҒ„гҒҸгӮүпјҹгҖҚгҖҒгҖҢй«ҳгҒ„гӮҲгҖҒгғҠгғғгғ—гғігӮҲгҖҚгҖҒгҖҢйЈҙгҖҒгғҸгғҠгғ»гғҒгғ§гӮ»гғ§гҖҚгҒӘгҒ©гҒЁгҖҒгҒҫгҒ“гҒЁгҒ«дёҚеҸҜжҖқиӯ°гҒӘдјҡиӘһгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
гҖҖгҒ„гҒҡгӮҢгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҰиЎ—гҒ«еҮәгҒҹгӮҠгҒ—гҒӘгҒ„йҷҗгӮҠгҖҒзӨҫе®…гҒЁеӯҰж ЎгҒЁгҒ„гҒҶж—Ҙжң¬дәәзӨҫдјҡгҒ®дёӯгҒ§йҡ”йӣўгҒ•гӮҢгҒҰз”ҹжҙ»гҒҷгӮӢжҷӮй–“гҒ®ж–№гҒҢиүҜгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒзөҗеұҖжңҖеҫҢгҒҫгҒ§жӯЈгҒ—гҒ„жңқй®®иӘһгӮ’е„„гҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒд»ҠгҒ«гҒ—гҒҰжҖқгҒҲгҒ°иӘ гҒ«ж®ӢеҝөгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҖҖ

гҖҖжҳӯе’Ңпј‘пјҷе№ҙгҒ®жҳҘпјҹгҖҖиҮӘе®…зҺ„й–ўгҒ«гҒҰ
гҖҖзҲ¶гҒҢж’®еҪұгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒҹеҶҷзңҹгҖӮеҫҢеҲ—е·Ұз«Ҝгғ»йҳІеҜ’еёҪгҒҢз§ҒгҖӮ
--
з·ЁйӣҶиҖ… пјҲд»ЈзҗҶжҠ•зЁҝпјү